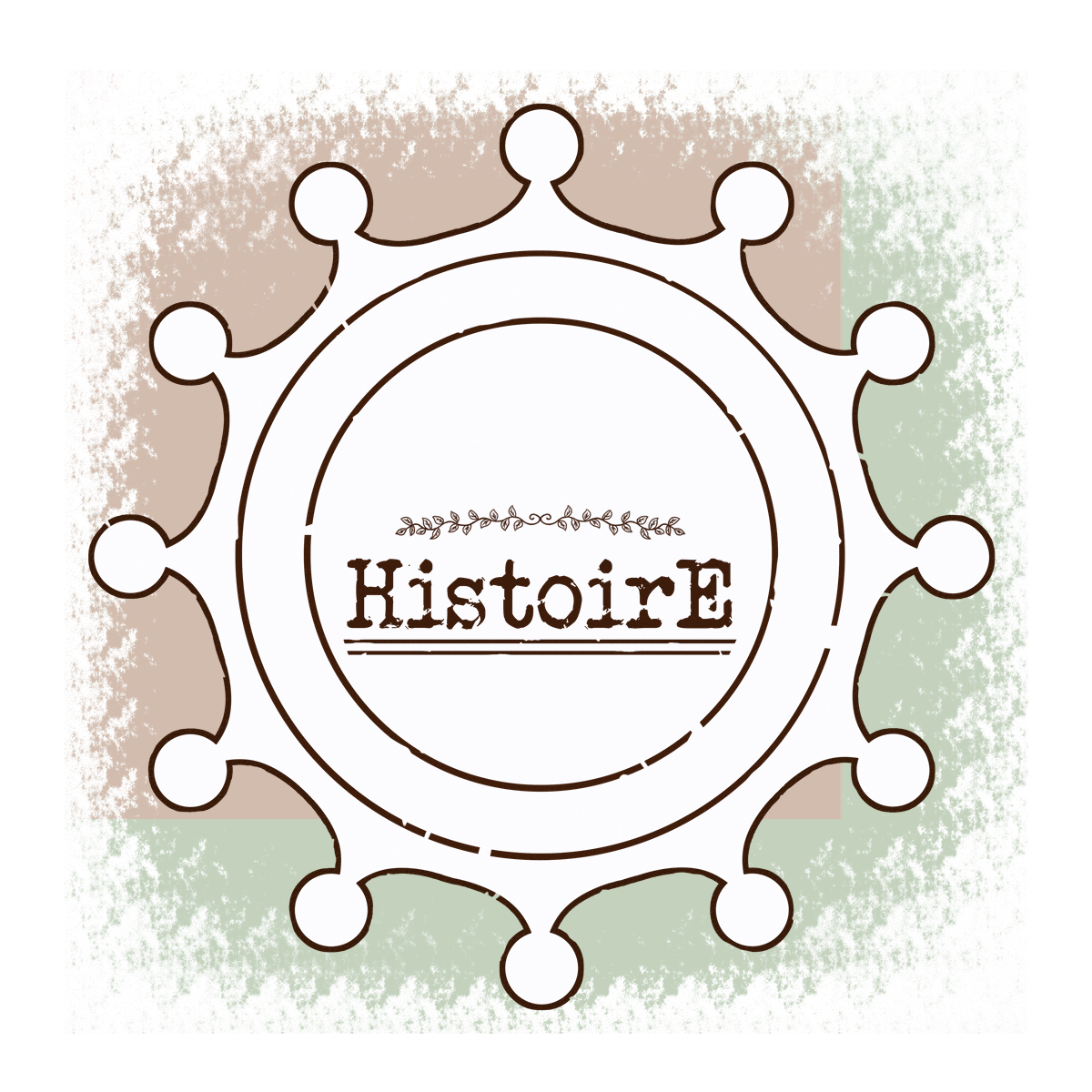※出血等の表現を含み、プレイアブルキャラクターが死にかけます。苦手な方はご遠慮ください。
※ティナリのキャラスト記載内容を一部含みます。ネタバレを嫌う方はご注意下さい。
ちょきん、ちょきん。
白銀の髪に鋏を入れる。細くて柔らかだが、風雨に晒されたそれは傷んでしまっている。綺麗なのにもったいないな、という思いはあるが、それを手入れすることを許された喜びもこの胸には確かにあった。
ティナリがセノの髪を切るようになってしばらく経つ。始まりはばっさりと髪を切り落とされ、あまりにも不恰好な状態で顔を見せた時だ。エルマイト旅団との戦闘で切られたらしい。その時のティナリの胸中を占めたのは髪で済んでよかった、という安堵と、あの綺麗な髪を、という怒りだった。もちろんそのエルマイト旅団の者たちはセノ自身が捕縛したということだから、恐ろしい目に遭っているのは間違いないのだが。
怪我の手当てをしたあと、切られた長さに頭髪全体を切り揃え、パツンと刃で切り落とされた跡が残らないように毛先を調整する。
「僕は理髪師じゃないから、不恰好でも文句を言わないでよ」
そんな保険をかけたことを覚えている。構わない、とセノが微笑んだことも。
人に髪を触らせるというのは、その間に信頼関係が結ばれている証明になるとティナリは考えている。セノにとって自分はその中に入るのだと知ることができて、それがまた嬉しかった。
「というか、今まで髪を切る時はどうしてたの?」
ふと浮かんだ疑問を投げかければ「自分で適当に切っていた」と返ってきた。なんとなく予想していたとはいえ答えに呆れていると、だが、とセノが続けた。
「これからはティナリに切ってもらうのもいいかもしれない」
そんなことを言うものだから、ティナリも「僕は暇じゃないんだけど?」なんて言い返した。でも――手のひらからさらさらと滑り落ちていく髪に視線を落として、この美しい白銀の糸が無造作に切り落とされるのもなんだかな、と思い直す。結局「でもいいよ。また切ってあげる」と付け足したことで、その後セノがティナリを訪ねる理由に「髪を切ってもらう」が追加されたのだ。
ちょきん、ちょきん。
ぱらぱらと白い髪が落ちていく。無造作に切られていた時と比べると、こうしてティナリが髪を切るようになってからセノは幾分か身なりが綺麗になった。まあ正しくはティナリが整えているのだが。例えるなら捨てられてボロボロだった犬が拾われて、丁寧に洗われ、毛並みを整えられていくような、そんな変化だ。
いつも伸ばしっぱなしの前髪は顔が隠れてしまうのでは、視界が悪いのでは、という心配があったが長い方がいいという、珍しく見せたセノのこだわりを聞き長めに切り揃える。後ろの髪も綺麗に靡く程度に長さを揃え、鋏を置いたあとはティナリが普段使っているヘアオイルを塗ってやる。雨林と砂漠を行き来する大マハマトラだ。風雨や砂埃、陽の光に晒されて傷んでしまうのを少しでも防げるようにと。
「できたよ」
両肩を軽く叩いて声を掛ける。我ながら随分手慣れたものだ。セノはどうやらいつの間にか眠っていたらしく、体がびくりと跳ねる。
「っふ、大丈夫?」
そのことに思わず吹き出すと、セノは「すまない……」と言って決まり悪そうに前髪を引っ張るが、残念ながら今切られたばかりの髪は数刻前より少し短くなってしまっている。
「疲れてるのなら休んで行けば? 急がないのなら、だけど」
セノの体を覆っていた大きめの布を取り払い、切り落とされた髪を纏める。小さな山になったそれを袋に入れ、あとは払い落として布を畳む。こいつの次の出番は、次にセノが髪を切りに来た時だ。
「いや、睡眠は十分だ。最近は少し落ち着いているからな。ただ、髪を触られていると少し……」
そこでセノは口をつぐむ。彼の言わんとしていることがなんとなく分かって、ティナリはあとを引き継ぐように尋ねてみる。
「少し、ふわふわする?」
「ふわふわ……うん、そうだな。そんな感じだ。なんとなく心地よく感じるんだ」
その感覚にはティナリも覚えがあった。子どもの頃だったか、母に髪を切ってもらっていた時に、気が付くと眠ってしまうことがあった。
「今日は天気もいいし、暑くなってきたとはいえ十分過ごしやすい気候だからね。外でいい感じに、日向ぼっこをしているような気分になったんじゃない?」
うーん、とティナリはセノが座っていた椅子に畳んだ布を掛け、伸びをする。気持ちがいい。
「ティナリもそういうことがあるのか?」
「僕? んー、まあそうだね、子どもの頃、髪を切ってもらってる時に眠っちゃったことがあったかな。あと、尻尾の毛を梳かしてる時とかも気分がいいかも」
今日みたいな日は特にね、とセノを見て、陽に透けた髪に思わず手を伸ばす。きちんと手入れをすれば絹糸のようにもっと美しく、滑らかな肌触りだっただろうに。もちろんセノにそこまで求めていないけれど。
「それにしても、セノの髪は綺麗だね」
「ティナリが手入れをしてくれているからじゃないか?」
「自分でもできるようにしなよ」
けらけらと笑って言うが、ティナリとしてはそれなりに願っていることだ。できることなら自分でやってほしい。が、そんなティナリの気持ちなど知る由もないセノはとんでもないことを宣う。
「ティナリがやってくれるからいいじゃないか」
さも、それが当たり前であるかのように。なんの疑問も持たない声が、言葉が飛んできた。
「僕は君のお母さんじゃないんだよ? だいたい、いつまでも僕がセノの近くにいるわけじゃないんだから」
その時の、セノの表情は忘れられない。
「……どこかへ、行く予定があるのか?」
「は?」
「いつまでも近くにいるわけじゃないって……」
置いていかれる子犬のような顔をするセノに、ティナリは少々面食らう。どうしてそんな寂しそうなの? それでもティナリの口は言葉を紡ぐことをやめてくれない。
「今だってそうだろ? 君は一応シティ、僕はガンダルヴァー村を拠点にしてる。そりゃあ、こうやって会うことはできるけどお互い忙しい身だし、もしかしたら将来それぞれもっと遠い場所に行くかもしれない。そうしたら、こんなふうには会えないよ」
もちろんティナリはこのアビディアの森のレンジャー長として生きていくし、セノも恐らくマハマトラとして生きていくのだろう。でもその過程で、他国に行くこともあるだろうし、想像もできないがそれぞれ所帯を持つ可能性だってゼロじゃない。今のように会おうと思えば比較的簡単に会える距離にいて、世話を焼いたり食事をしながら世間話をしたりする回数は減っていくかもしれない。
「そう、だな……」
セノの表情はそれらをまったく想像していなかったことを物語っている。ティナリからそんなことを言われるとも思っていなかったのだろう。
「何? そのいつまでも僕の世話になろうとしてたみたいな言い方。自分でできることを増やしなよ。セノは自分に無頓着すぎて放っておけないんだから」
まったく、と腕を組んで、ティナリは唇を尖らせる。
「そういうわけじゃ……。ただ……」
「ただ?」
先を促したティナリは、ぽつりと溢されたセノの胸中に目を見張ることになる。
「ただ、……どうしてだか、この先もずっと、俺はティナリと一緒にいるものだと信じて疑わなかったんだ」
セノが重傷を負った。
特別危険な任務だったわけじゃない。準備を怠ったり、油断していたわけでもない。だが予測していた以上の人数の敵に囲まれ、隙を突かれた部下であり後輩でもある仲間のマハマトラを庇って腹部を袈裟斬りにされたという。傷も深いが出血量も酷く、ビマリスタンに運び込まれた時は当然意識不明、呼吸は浅く、生きているのが不思議なくらいだったという。幸いにして運よく一命を取り留めたが、連絡を受け、ガンダルヴァー村での仕事と自分が不在の間の連絡をしたティナリがようやく駆け付けた頃には、セノが傷を負って既に半日が経っていたが、未だ意識は戻らないままだった。
ガンダルヴァー村に出した手紙の返事によれば、レンジャーたちは村のことは任せろと譲らなかったし、コレイからはティナリ宛に花を加工したしおりと、セノがよく身に付けているローブのフードを被ったキツネのようなぬいぐるみが、見舞いの品として手紙と共に届いた。彼らの心遣いと温かさに感謝しながら、コレイのぬいぐるみをセノの病室に置いた。
祈るような思いでセノの手をぎゅっと握りしめて、月が沈み太陽が昇るだけの時間を過ごした。
それから更に三度、陽が昇っては沈み、月が昇って沈みを繰り返して。朝露が植物の葉を濡らす頃に、セノはようやく目を覚ました。
ぴく、と指が動いた気配がした。まるでそこだけ止まったかのようだったセノの周りの時間が、ゆっくりと動き出したみたいな感覚だった。
「セノ!」
瞼がゆっくりと持ち上がり、少しずつ緋色の瞳が現れる。焦点の定まらないそれは、ここがどこなのかを探っているようだった。
「セノ」
そうしてもう一度名前を呼んだティナリを見つけたセノは安心したような、かと思えば不安そうな顔をした。
「ティナリ、か……ここ、は……?」
「ビマリスタンだよ。セノ、四日も目が覚めなかったんだからね」
よかった……と、ぎゅっとその手を握り直す。僕はここにいる、君は生きている、それを実感してもらうために。
起き上がろうとするセノを制して、ティナリは医者の顔で説明をする。
「駄目だよ起き上がっちゃ。僕が駆けつけた時には処置は終わっていたけど、君、本当に酷い怪我なんだから」
布団の下、入院着のその下は包帯がぐるぐるに巻かれている。止血に輸血、合併症を予防するための薬の投与。二度に渡る手術で当然腹部は何針も縫われている。任務地で応急処置をしたマハマトラ達は優秀だったのだろうと思うし、あの日ビマリスタンで処置してくれた医師への感謝はしてもしきれない。心臓が無傷であったことがせめてもの救いだ。
「生きているのが不思議なくらいだ、って言われてた。正直僕も同感だ。少なくともしばらくは絶対安静。もし少しでもベッドから起き上がろうとしてみようものなら、ロープで括り付けるからね」
分かった? とぴしゃりと言うと一度皆へ報告するために個室を出る。ビマリスタンの医師たちに、ガンダルヴァー村のレンジャーたち。コレイは個人的にセノと関わりがあることもあっていっとう心配していたから、村への手紙を書いて瞑彩鳥を飛ばさなきゃ。
扉を閉めると同時に鼻がつんとした。目の周りが熱を持ち、徐々に視界が歪む。込み上げる涙は、恐怖と安堵からくるものだ。
怖かった。このままセノが目覚めないんじゃないかと思って。
良かった。目覚めてくれて。生きていてくれて。
こんな思いは二度と御免だと思うが、セノがマハマトラでいる限り、いつまたこんなことが起こるか分からないのも事実だ。彼は彼なりの覚悟を持って今の仕事をしている。それをティナリの我儘で口を出すようなことはできない。
扉の向こうのセノが何を考えているのかは分からない。でも今は、どうか体を治すことだけを考えてほしいと願う。
ぐい、と目元を拭い、顔を上げる。これ以上泣いてなんていられない。
セノに重傷を負わせたエルマイト旅団が捕まったと報告を受けたのは、セノが目覚めた次の日だった。
セノが目を覚まして一ヶ月が経った。
容体は安定しており、消化の良いものであれば食事もできるようになった。傷付いてしまった内臓があったため食事は慎重だったが、順調に回復している。とはいえまだたったのひと月だ。快復には相当の時間がかかる。ティナリは主治医のような形で日々経過観察を続けており、ティナリがセノのそばを離れる日は他の医者に一時的に預けるような形になっているが、くれぐれも目を離さないことと、何か無茶なことをしようとしたらそれを止めるのに容赦はしないことを念入りに頼んで。
週に一度、ティナリはガンダルヴァー村に戻っていたがレンジャーの仕事も暇ではない。近頃とある花の乱獲が発生しており、その対抗策を何か打ち出さなくてはならないレンジャーたちは頭を悩ませている。ティナリは彼らをまとめる長だ。彼らから寄せられるアイディアについて、それらが効果的かどうかやリスクの有無、物理的財政的に可能かなど様々な点について判断する必要があったし、当然自分自身も何か案を出したいと頭を捻っていた。セノが目覚めて二週間を過ぎた頃からは、シティから近い区域のパトロールが割り当てられている日は現地合流という形ではあるがそれにも参加していた。
花の件のほかに気掛かりなのはコレイだった。長いこと彼女に授業をしてあげられていない。村に帰った時や手紙では「あたしのことはいいから、今はセノ様のことを優先してくれ」と言ってくれていたが、彼女の大切な時間は今この瞬間も過ぎていく。可能な限りテストや練習問題を作って渡してはいるが、本当はきちんと教える人間がそばについていてあげるべきだ。村に戻る度に彼女の病状も診ているが、魔鱗病の症状は安定しており、進行もない。それだけがティナリの救いだった。
それでも、ティナリはセノのそばをできる限り離れたくはなかった。許す時間のすべてをセノの病室で過ごし、彼の怪我の経過を見守った。書類仕事はセノが眠っている間にしてしまえる。多忙ではあったが、セノのそばにいられるだけで幾分ティナリの心は安らぎを得ていた。セノが起きている時間は彼と話すことも多かった。普段は離れていることに加えて時間が限られていたが故に、会った時はいつも近況報告やコレイの様子が話題の大半を占めていたが、毎日たっぷり時間があるおかげで何気ない会話が増えた。ティナリは雨林の植物やその研究、毒キノコをうっかり口にしてしまった冒険者が村で起こした珍事件やレンジャー隊の中で流行っている歌について。セノは砂漠の星空や地形の移り変わり、七聖召喚の最近の世間の流行などについて、時々つまらないジョークを交えながら。ちなみに、セノがどうしてもと言うため彼が思い付いたジョークを愛用の手帳に書き留める係をティナリは務めたが、正直なところ書き留めたところでどうするんだ、とは思っていた。もちろんセノとはただ世間話をするだけではなく、会話の中で彼の様子におかしなところはないかを観察する目的もある。
セノが目覚めて二ヶ月。経過が良好なセノをビマリスタンの医師たちに託し、ティナリはガンダルヴァー村へ戻ることを決めた。レンジャー長の仕事や問題は山積み、コレイの授業の再開……やることが日々積み上がっていく現状をこれ以上放っておくことはできなかった。
もちろん村へ戻るといっても週に一、二回は顔を出すつもりだ。ティナリは自分の患者を放り出す医者ではないし、怪我をした友人を孤独に晒す薄情者でもない。
セノにはベッドの上では起き上がったり自由にすることに加え、少しであれば歩行も許可した。今も七聖召喚のカードを見たり、ジョークを帳面に書き付けている姿を度々見かけるほどであるから、あの様子ならそのうち事務仕事だけでも再開しそうだ。当然、前線に出ていこうものならティナリが矢を射ってでも止めるが、書類仕事ならば、無理をしなければ問題ないだろう。それでもベッドを降りるのならあまり動かさないようにと釘を刺してある。せっかく塞がった傷が開いてしまえばまたベッドに縛り付け生活に逆戻りだ。
「ティナリ」
そんな生活を続けているうちにセノが事務仕事を再開した。目覚めて三ヶ月。傷が開くこともなく、自立歩行もスムーズになった。順調だ。
面会に来たティナリが帰ろうと立ち上がった時に、セノは徐に声を掛けてきた。
「どうしたの?」
近頃は例の花の問題について動いていて、シティで花を売る露店と連絡を取ったり実際に足を運んだりなどの仕事が多かったため、ティナリは出来るだけ自らシティに赴き、仕事を終えてからビマリスタンに顔を出すようにしていた。あまりにも頻繁にティナリが現れることを不審に思ったらしいセノに聞かれたことがある。事情を説明すれば納得はいかない様子ではあったが理解したようで、それ以上何か言われることはなかった。ついでに、セノの病室にはドライフラワーの装飾がコレイのぬいぐるみの隣に増えた。
「次に来たら、髪を切ってくれないか。仕事をするのに邪魔なんだ」
そういわれてみれば、最後にセノの髪を切ったのは彼が怪我をする二週間ほど前だった。前髪も後ろ髪も好き放題に伸びてしまっている。今は耳の下で緩くひとつにまとめているが、やはり煩わしいのだろう。
「そうだね。分かった」
じゃあ次は鋏を忘れないようにするよ、と手を振ってティナリは病室を後にした。
ちょきん、ちょきん。
ビマリスタンの裏手から鋏を通す音が聞こえてくる。椅子に座ったセノに、彼の体をすっぽり覆う布を掛け項のあたりで結ぶ。
時間が開いて伸びた分、切り落とした髪はいつもより長くなる。とさ、と。少し重みのある音を立てて落ちていく。
「ティナリ」
あとはいつも通りオイルを塗って仕上げるだけ、という段階になって、セノがティナリを呼んだ。少し、声が硬いように感じる。セノの前に回り、膝に手を置いた中腰の姿勢でセノの顔を正面から見つめる。
「なに?」
「今切ったその髪はティナリが持っていてくれ」
「え?」
告げられたのは予想だにしていなかった言葉で。ティナリは咄嗟にその意味を理解しきれなかった。
「マハマトラは危険な仕事だ。任務中に命を落とすこともあるだろう。どこかで買った恨みが返ってくるかも知れない。遺体だって残るとも限らないし、そもそも俺がお前に残せるものなんてたかが知れている。だからその髪は俺の形見だと思って――」
「認めないよ、そんなの」
セノの言葉を遮って、ティナリは語気を強めて言う。セノの言いたいことは徐々に分かった。でも、そんなことは認めない。
「ティナリ」
まるで言い聞かせるように呼ばれる。これではどちらが患者でどちらが医者か分からない。それでもティナリは振り払うように続ける。姿勢を崩し、膝を伸ばして立ち上がる。
「駄目だ、認めない。形見なんて必要ない。君は必ず、毎回僕のところに帰ってくるんだ。絶対に」
じゃなきゃ許さない。まるで我儘を通そうとする子どもみたいにそう突っぱねる。視界は歪み、セノが今どんな顔をして自分を見ているかも分からなくなる。それでもティナリは譲れなかった。
ティナリは植物学者だが、医者でもある。医者は、患者が亡くなったあと、自身の内臓を誰かに提供してほしいと意思表示されればそれに従う。そうして、新たな場所でその人は生き続ける。セノは形見として自分の髪を持っていてくれと頼んできた。それはある意味、彼らの内臓と同じだ。
認めたくない、そんなこと。形見なんてそんなもの、要らない。生きているセノと一緒にこれからもごはんを食べたり話したり笑ったりしたい。ティナリが願うのはたったそれだけだ。
それでも、もし、という恐怖がティナリのどこかにあったのは確かだ。セノの望みを踏み躙ることもできない。形見を受け取ってほしいと言われたことに心のどこかでほっとした自分がいることに嫌気が差す。違う、これは僕の望みじゃない。
医者は命を守る番人でもあり、患者が生きる気力を持ち続けるように言葉をかけるのも仕事である。
――君は必ず、毎回僕のところに帰ってくるんだ。
それはティナリの願いであるが、同時にセノが自分の命を諦めないようにするための御守りでもある。
いつだったかセノが言った。「この先もずっとティナリと一緒にいるものだと信じて疑わなかった」と。そのセノが別れ――それも永遠の別れを仄めかした。今回の怪我を、セノなりに受け止めた結果だろう。これがセノが自分を省みるきっかけになってくれたらいいと思っていた。だが、それは甘い考えだったのだと思い知る。
ぎゅっと、拳を強く握りしめる。
「……僕は。君に、君自身を大切にしてほしい。今回の怪我は仲間を守った結果だ。僕は君のその優しさと強さがとても好きだよ。仲間を大切に思う気持ちも、仕事を重要視していることも知ってる。だけど君が大切にしている物の中に、セノ自身はいるの?」
「俺のことは――」
それがティナリの逆鱗に触れた。何かがぷつりと切れる音がして、歯止めが効かなくなる。
「俺のことは、何? 気にする必要はないって言いたいの? セノ、前に言ったじゃないか。この先もずっと僕と一緒にいるものだと信じて疑わなかったって。それって、セノがそれを望んでくれてるってことじゃないの? 僕だって、セノと一緒にいたいよ。でも、僕が一緒にいたいセノは僕を置いていこうとする」
世界が滲んでいくのに、言葉は止まらない。
「してない」
「してるだろ。僕の大事なセノのこと、セノが一番大事にしてないじゃないか!」
つい声を荒げてしまう。ぽろぽろと涙が落ちていく。溢れた感情は俯いたティナリの瞳から溢れる粒となり、頬を伝うことなくそのまま草原の大地を濡らし、溶けて消える。
「……それを言うならお前だって、もう何ヶ月も無理をしているだろう」
「……はあ?」
その言葉に思わず顔を上げる。それが自分を心配し、泣いている友人に言うことか?
「頻繁にガンダルヴァー村とシティの往復を繰り返している。ここに詰めていた時は村の仕事と俺の治療でほとんど寝ていないような状態だったはずだ」
「僕はいいんだよ、元気なんだから!」
「過労も過ぎれば命に関わる」
「セノに言われたくない。自分の体のことくらい分かってるよ。問題ない」
「俺だって! ……俺のせいで大切な人が傷付くのは見たくない」
「……ぁ…………」
珍しくセノが声を荒げた。まるで傷付いたみたいに、その表情は不安げに、苦しげに揺れている。
その言葉に、表情に、掛ける言葉が見当たらない。
「俺はティナリが大事だよ。だからお前を傷付けたくないし傷付いてほしくない。お前の強さは知っているが、それでもいつでも強くいられるわけじゃない」
ティナリ、と。その静かな声が囁くように呼ぶ。風に吹かれて消えてしまいそうだ。セノが手を伸ばしてくる。布に覆われていて、その小麦色の手は見えないし、ティナリには届かない。そのまま行き場を失って、それは下ろされた。だがその手が何をしようとしたかくらい分かる。
「……すまなかった」
ティナリを見上げていた頭を下げて、ただそれだけを告げた。
「セノ……」
「分かっているんだ。俺のこの気持ちが、お前が俺に抱いてくれている感情と同じだということは」
互いに心配をして、心配をするようなことをしてほしくない大事な相手なんだ、と。ティナリは黙って頷く。
ティナリだって分かっている。互いに抱く心配も不安も、相手が大切であるが故のもの。自分と同じものを、セノもまたティナリに対して想ってくれている。信じていないわけじゃない。でも、いつ何が起こるのか分からないのも事実だ。
「だが、これは譲れない」
そう言いながらセノは首元に落ちる自身の髪を顎で示す。静かだが、確固たる意志を感じる声だ。
「俺からティナリに渡せるものは多くない。だから……」
だから、これを。どうか受け取ってほしい。
まるで懇願するような言い様に、ティナリは遂にため息をついた。膝を折り、自分の手をセノのそれに重ねる。
お互い厄介な相手に捕まったものだ。ティナリもセノも頑固でそう簡単に譲らないのだ。それでも一緒に歩いていくには、どちらかが譲歩するしかない。
「……仕方ないから、形見じゃないなら貰ってあげる」
顔を上げたティナリは、困ったように眉をハの字にして。それでも笑っていた。
北に見えるチャトラカム洞窟から吹く風がここまで届く。セノに被せた布がバサバサと音を立てて靡いた。太陽は傾いていて、西陽が眩しい。風は少し冷たくて、冬が近いことを知らせる。一年を通して他国よりも熱帯気候にあるスメールだが、さすがに気温変化がないわけではないのだ。
ティナリの黒とセノの白銀とが風に吹かれて舞う。
早く終わらせて戻ろうか、とティナリは愛用のヘアオイルへ手を伸ばした。
***
「ねえセノ、さっき僕のこと大事だって言ってくれた?」
「そういえば、言ったな」
「それってどういう意味?」
「どう、とは? 友人として以外に何かあるか?」
「なんだ、自覚なしか。残念だなあ」
「ティナリだって同じようなことを言ったじゃないか。お前こそどうなんだ」
「セノが答えに辿り着いたら教えてあげるよ」
――好きだよ。
「?」