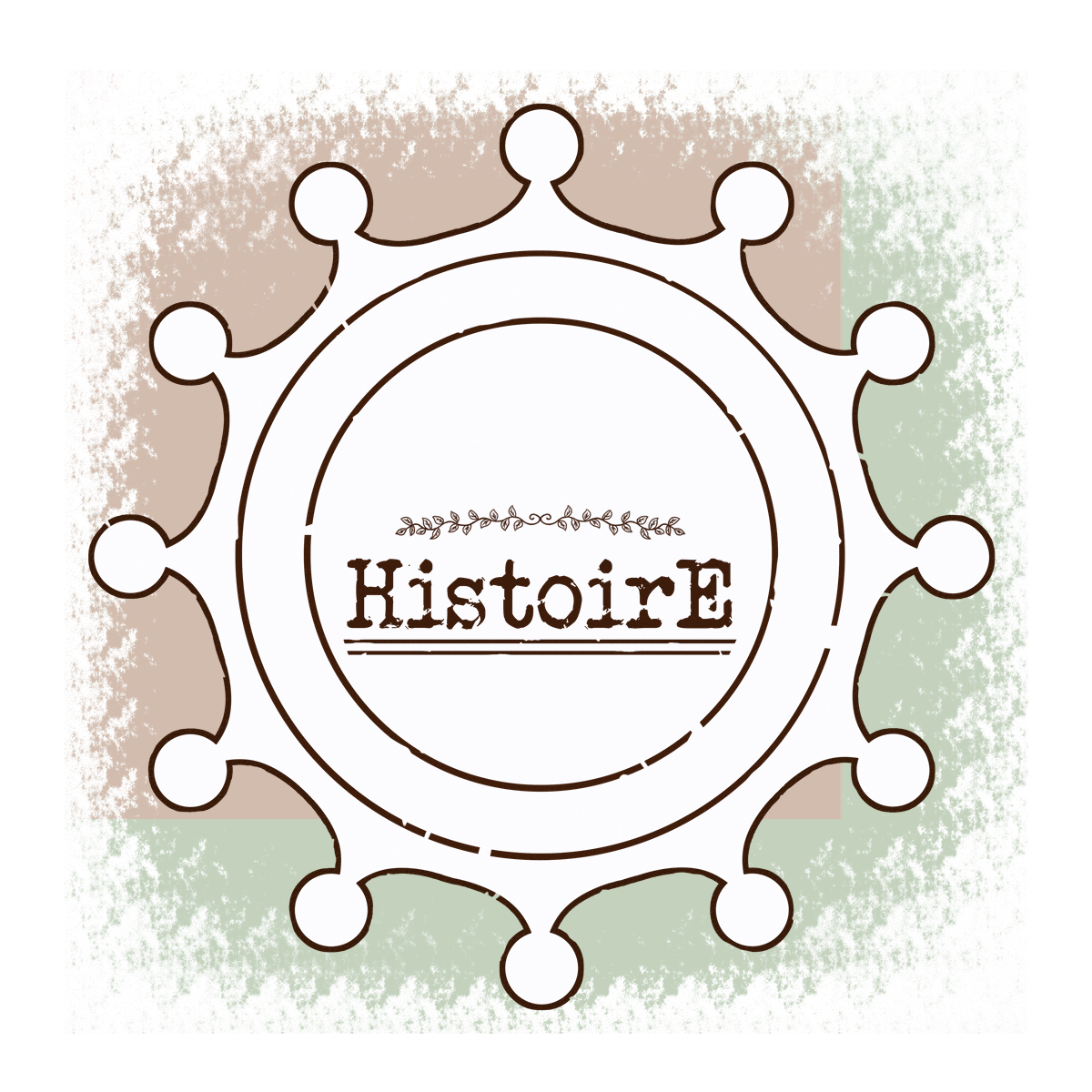レンジャーというのは体力の必要な仕事だ。そのため自然と若い者が多くなる。若者はエネルギーに溢れ、活発であり、時に恐れを知らない。ティナリは常に、慎重でありながらも必要以上に臆病にはなるなとレンジャー隊の皆に説いてきた。時には大胆になることも大事だ。
……だが、こんな意味で大胆さを披露する必要はない。
「レンジャー長聞いてくださいよ! ついこの間シティに住んでる彼女とデートしたんですけど、」
「ティナリレンジャー長、昨日彼氏から手紙が届いて、仕事でしばらくスメールを離れるから会いたいって言われて」
「そういえばおまえ告白したい人がいるとか言ってなかったか? ほら、オ――」
「ちょっと! 何勝手に言いふらそうとしてんのよ! あんたこそ気になる人がいるとか言ってたわよね」
酒の席とはいえ、男女問わず右も左も恋の話。エネルギーに満ち溢れていることは結構だが、ティナリには縁のない話だ。少しガヤガヤするなあ、耳が痛いかも、と思い始めた時だった。
「そういえば、ティナリさんはそういう浮いた話ないんですか?」
誰がそんな愚かな質問を投げ入れたのかはもはや記憶にない。というかどうでもいい。問題は話題の中心と皆の興味が自分に向いてしまったことだ。先程までガヤガヤと騒がしかったはずの宴席は途端に静かになり、皆の視線が突き刺さる。まるで針の筵じゃないか。どうでもいいなんて前言は撤回する。後でアミルは説教だ。
「確かに聞かないな」
「そもそもレンジャー長の恋愛話って想像できないかも……」
「彼女いるんですか?」
「あ! それ私も気になる!」
唯一の救いはこの場にコレイがいなかったことだ。酒の席だからと今日は成人したレンジャーのみが集まっている。
「あぁもう! いっぺんに喋らないでよ! あと僕に恋人はいないから!」
堪らず大きな声を張り上げてしまい、その場がしんとしてはっと我に返る。そんな大きな声で恋人いない宣言をしてしまうなんて。自分では酔っていないつもりだったが多少、場の空気にあてられてしまったのかもしれない。
「じゃあ好きな人は?」
「こんなに顔がいいのに……!?」
「学生時代は? いたんですか?」
静まり返ったのも束の間、再びどっと質問が押し寄せる。君たち、その熱量を普段から発揮して欲しいんだけど。
「あの、コレイをここに連れてきた人は? よくレンジャー長を訪ねてきますよね。ほら、黒いフードの……」
控えめな声だが、はっきりとティナリの耳はその質問を拾い上げる。
コレイをガンダルヴァー村に連れてきた、僕をよく訪ねてくる黒いフードの人間なんて一人しかいない。
「セノのことを言ってるの!? あいつ男だよ!?」
弾かれたように、思わず立ち上がって叫ぶ。どうしてそんな質問が出たのかすら分からない。
「えー、でも今時珍しくないと思いますよ。同性カップル」
「確かに」
「ていうかあの人との距離いつも近いような気がしてたからてっきりそうなのかと」
「並んだ姿に違和感ないもんな」
「むしろお似合いって感じ」
皆口々にそんなことを言うが、好き勝手に感想を聞かされてもこちらとしては困る。
「と……とにかく、僕とセノはただの友達! そういうのじゃないから! あと、そういう話に僕を持ち出さないで!」
ぴしゃりと言い放って、ティナリは席を立ち、輪から離れる。夜風が頬を撫でて、熱をさらっていった。
…………あれ?
思わず頬に手の甲を当てると、そこは普段よりも熱く感じた。どうして?
突然話の矛先が自分に向いて、驚いたからだろうか。質問攻めに遭って混乱したからだろうか。多少酒も入っているし。大声を張り上げて、息が上がっているのかもしれない。違う、そうじゃない。でもそんなはずもない。
心のどこかで答えは見つかっているはずなのに、それを見て見ぬふりをする。いや、だってそんな。
ただの友人で、最も信頼の置ける人間の一人で、立場は違えど相棒のようにも感じている。それだけだ。好きではあるがそれは友達としてであり断じて恋愛対象だとかそんなつもりは――
「〜〜〜〜!!」
考えれば考えるほど、顔は熱を持ち、耳は垂れ下がり、尻尾は丸まっていく。思わず頭を抱えて、そそくさと誰の目にもつかない場所に移動して、そこに蹲った。
僕は、セノのことをどう思ってるんだ?