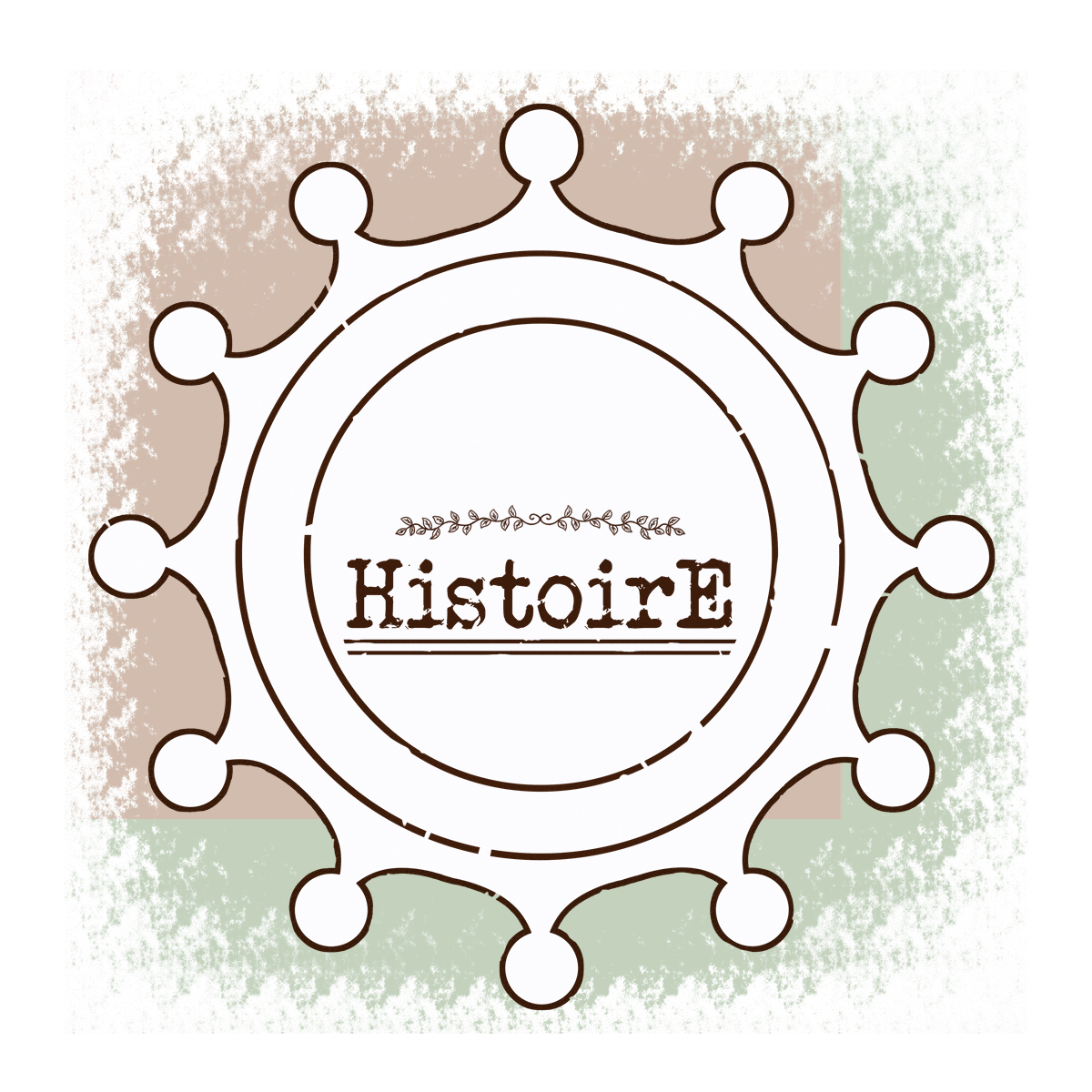世界が揺れる。
まるで走る駄獣に乗っているみたいに、ティナリが座る花のゴンドラはガタガタと揺れ、しばらくしてそれは収まった。一体何だったのだろう、宙を飛ぶ花のゴンドラがあんなに揺れるなんて。強風が吹いたのだろうかと思ったが、ティナリの切り揃えられた黒髪は一糸たりとも乱れていなかった。ゴンドラはやがてガンダルヴァー村の上空にさしかかった。コレイとセノの姿が見えて、おーいと呼びかけて手を振ると、コレイがティナリに気付いて手を振り返してくれた。だがセノは目の前のコレイが手を振っているのにティナリに気付かない。セノ! と呼んでも呼んでも、彼はこちらを見ない。このままでは村を通り過ぎてしまう。ティナリは必死にセノの名前を呼びながら、ゴンドラから身を乗り出して――「せ、の…………」 手を伸ばし、ゴンドラから飛び出したそこで映像に靄がかかる。ぼんやりとしていた意識が次第にはっきりとし、ようやく覚醒したのだと自覚した。ゆっくりと目を開くと、白い糸のカーテンに囲まれ、夕陽色の宝石に見つめられていた。伸ばした手が、よく日に焼けた手に掴まる。
「セノ……?」
そこには今さっき、何度も名前を呼んだ人がいた。
泣き出しそうな顔をして。
ティナリは薬草を採りにアビディアの森の奥へと向かった。以前のカカタのマスター――いや、友人であるアバッドイの隠れ家があった沢の近くに、セノに渡す予定の薬に調合する薬草が群生している。道中にはサウマラタ蓮も集まっているから一緒に集めておこうと、ガンダルヴァー村を出てまっすぐ北上した。 目的の植物を見つけると、根元を覆う土を手で掘り起こし、薬として使う根を採取する。多くは採り過ぎない。解熱解毒の薬効から考えるに、使用頻度は一般的な傷薬に比べても多くない。余分に渡すとして多く見積もっても、二本もあれば十分過ぎるだろう。茎の部分には有害な毒を持つため注意を払いながらも、余計な草花を傷付けないように。そうして無事に目的を達成して帰路についてふと、この辺りで見かけなかった花が視界の端で揺れた。
鮮やかな橙色のそれは、モンドに咲くのセシリアという花と少し形が似ている。以前植物図鑑で見た知識を引っ張り出し、その花がワスレグサという学名であり、精神を安定させ、睡眠の質を向上させる効果があることを思い出す。ついでに、食用として料理に使われることも。
うず、と強く興味を引かれる。耳と尻尾が正直に動いた自覚もあった。
学者の好奇心は止まるところを知らない。時と場合を選ばないわけではないが、今はそれらを考慮する必要はない。急いで帰る用事もなければ、まだ陽も高く、時間もたっぷりある。そわそわしながら近づき、一輪手折る。そこに生えているのが一株であればさすがに手を止めたが、周囲を見るにその心配もなさそうだ。崖を下り、軽く水で流して再び高地へ戻る。この辺りの水辺はスピノクロコが多く、もし眠ってしまった場合を考えると離れておくべきだろう。ガンダルヴァー村のレンジャー隊のパトロールルートにも入っている平地に木を見つけ、その幹に背を預けて座る。もう一度周囲の安全を確認して、それから鮮やかな花を口へ運んだ――
セノは口をきゅっと結んで真っ直ぐにこちらを見つめていた。胸から上が少し高いなと思って横を見ると、どうやら彼の太腿に頭を乗せられているらしい。少し離れたところにあのオレンジ色の花びらが落ちていた。
ティナリはセノを真っ直ぐ見つめ返す。
「なに、そんな泣きそうな顔して」
白く美しい長い髪をまるで天蓋から落ちるカーテンのように垂らして、ティナリの頭の周りを囲う。普段は髪に隠れてよく見えない右目もこの姿勢であればよく見える。綺麗な、緋色の双眸。それが嵌まった顔をセノはくしゃりと歪める。
「ティナリが倒れているのを見つけて、気がおかしくなるかと思った」
その声は常よりもずっとか細く、震えていた。
セノは命をとても重んじる。その尊さを知っているから。その儚さを知っているから。
セノは懐に入れた者に対して、過剰なほど甘く、大切にし、過保護だ。彼が情に厚く、優しい人だから。
ティナリは自分がセノにとって、誰よりその対象であることを知っている。ティナリにとってセノが誰より大切であるように、セノも誰よりティナリを大切に思ってくれていることも。
「……ごめん」
だからその言葉は、自然と音になった。
ティナリからすれば大したことじゃない。ただ催眠作用のある花を食べて、草むらで寝ていただけだ。周囲に危険性はないと十分判断できる場所だったし、それに対してセノの反応が大袈裟なのだと言えないわけじゃない。でもこれがセノという人で、ティナリが好きなセノだ。その人を不安に晒していいはずがないし、それをそのままにしたり、ましてや撥ね付けたりしていいはずもない。
「目が覚めたら俺の不安を、言葉を尽くして思い知らせてやろうと思ったのに」
「……思ったのに?」
拗ねたように言葉を切る。その続きが聞きたくてティナリは先を促した。少しだけ、甘やかすような気持ちで。
「……不満よりもお前がここにいて、こうして体温を感じていることの幸せが勝ってしまった」
その言葉に愛しさが込み上げた。好きだと思う。寂しい気持ちにさせたくないと思う。ずっと隣にいたいと思う。悲しませたくないと思う。笑っていてほしいと思う。傷付かないでほしいし、傷付けたくないと思う。誰より幸せでいてほしいと思う。
「ティナリの体の重みが安心するんだ。この重ささえ愛しい」
セノの手が肩に載せられる。ぎゅっと拳が握られ、その心を占めた不安と恐怖が伝わってくるような気がした。
「大丈夫だよ、セノ」
腕を伸ばしその両の頬に触れる。体温がじんわりとティナリの指先に伝わってきて、自分の体が随分と冷えてしまったことを思い知る。同時にセノがこんなに温かいことも。
「大丈夫。僕はここにいるから。これからもずっと、君と一緒にいるよ」
その顔を引き寄せ、まるであやすように優しく口付けた。
事情を白状させられたティナリが珍しくセノから叱られたのはまた別の話だ。