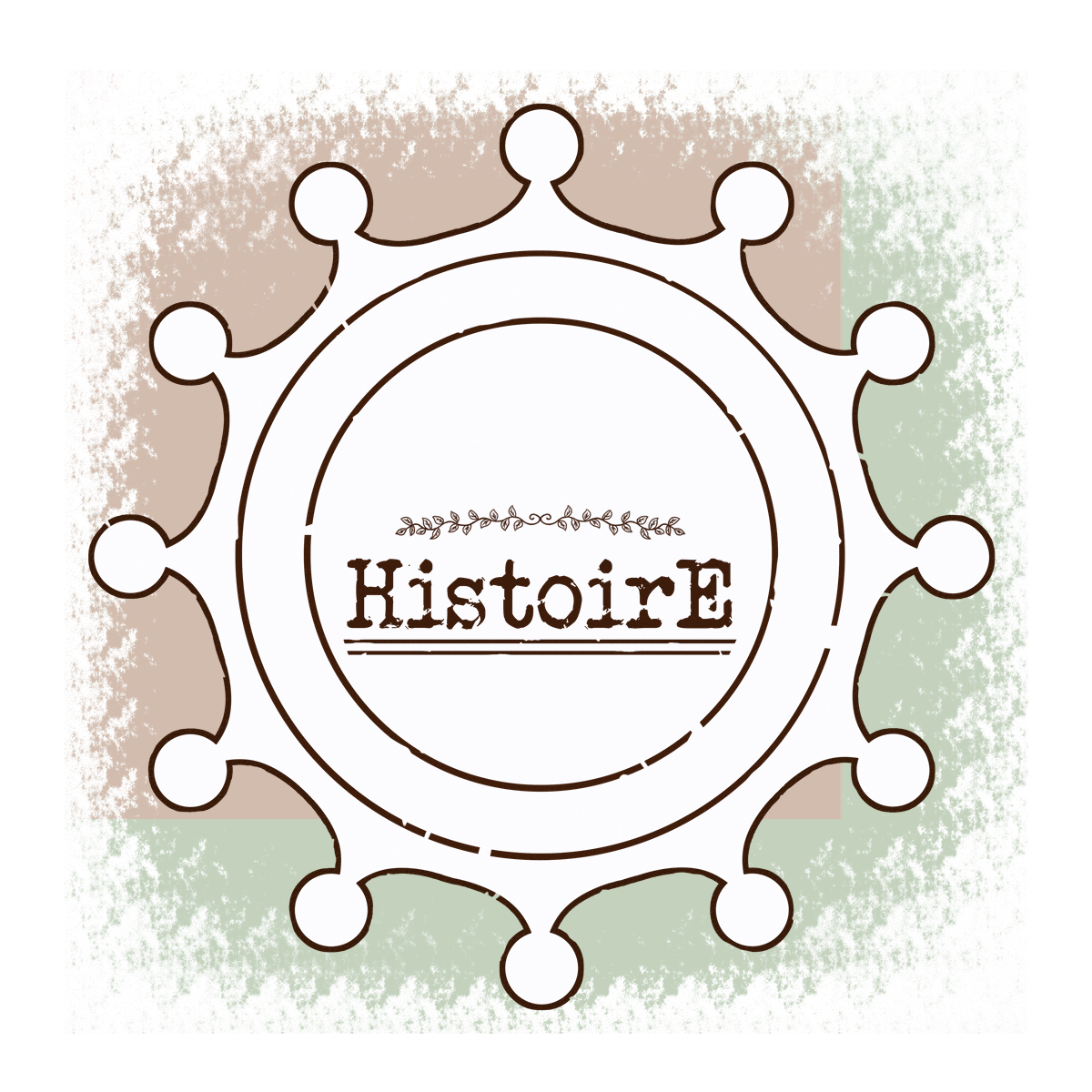ノースメイアから戻ってしばらくしたある日。ブラホワに向けた新曲が社長の手から渡された。
Mr.AFFECTiON。譜面とデモディスクには流れるような文字でそう、タイトルが書かれていた。
「…………」
目を奪われたのは、まるで自分のすべてを見透かされているような、苦々さとこっ恥ずかしさとむず痒さ。だけど胸を張って歌えると、自信を持って言える、自分に振り分けられたとある歌詞。
最初はオーディションを受けると答えた時。マネージャーだけならまだしも、ナギやソウ、リクから頭を下げられた時は正直、こいつらバカだなって思っちまった。俺は競争は得意ではないし、あいつらと競ってまでやりたいことがあったわけじゃない。それに俺みたいな気持ちでいるやつが一緒に並んでたら、おまえらの夢踏みにじるかもしれねえのに、邪魔になるかもしれねえのに、って。でもあいつらはそんな可能性一ミリも考えないで、俺に一緒にオーディション受けてくれって頼んできて──その気持ちに、少なからずあてられたのかもしれないなと、今なら思う。だけど、あの時背中見せて、そのまま帰らなくてよかったとも思うよ。心底。じゃなきゃ、今の俺はいないんだから。
その次はミツに一生懸命を教えてもらって、ドラマの仕事を受けた時。思えば、俺にとっちゃここが一番、アイドル人生が変わった瞬間なんだろう。忌々しい父親と同じ道に進むなんてこと。だけど、そうしてでもあいつらを前に進めてやりたかった。まだどこか他人事で、だけど確実にあいつらが俺にとって大事なもんになりつつあったから。
それから、父親が千葉志津雄だって明かした時。壊してやりたかったはずなのに、いつの間にか俺にとっても芸能界は居場所になっていた。すべてを話して、歳下のあいつらに幻滅されないか、俺がやろうとしたことは赦されるのか、その真実が、それまでのあいつらとの時間も努力も全部全部無に帰してしまうんじゃないかって、考えては怖くなった。だけどあいつらはむしろ、腹を立ててくれた。千葉志津雄に……俺の、親父に。俺が誰の息子だろうが関係ない、ここが俺の場所だって言ってくれた。
少しずつ、少しずつ、あいつらを守ってやりたいなんて大口叩きながら、その実俺も守られて、勇気もらって、今ここに立ってる。リーダーなんて、そんな大層なもんじゃないけど、そこが俺の居場所だって──
「大和さん!」
「………………あれ?」
そこは見慣れた俺の部屋だった。天井が視界いっぱいに広がっている。
「あ、起きました? おはようございます、大和さん」
視界の端から、柔らかく微笑んだソウが顔を覗かせる。特徴的な双葉癖毛が、今日もふよふよと優しく揺れている。
「あー、おはよ、ソウ」
穏やかな朝と、その光がよく似合うこの男にそう挨拶した。
「早くリビングに来てくださいね。もうみんな待ってるんです、か……ら……どうかしました?」
起き上がった俺の顔を見て、ソウは首を傾げて覗き込んでくる。その困り眉が、なにかを変だと告げている。
「え?」
「なにかいい夢でも見たんですか?」
「えっと、なんで?」
「なんでって……大和さん、なんというか、ものすごく笑ってますよ」
「は──」
え?
笑ってる?
「どちらかというと、にやにやと……」
「…………」
追加情報は寝起きの俺の体力ゲージを半分にするほどには、ダメージがあった。
「まじか」
「まじです」
沈黙。時間にしてたった数秒。でもその無言時間は俺のメンタルを更にゴリゴリ削っていく。
まあ、とソウが立ち上がったのと同じタイミングで、俺は言い訳がましく口を開いていた。
「いや、あれは夢というか」
「いい夢だったんですか?」
間髪入れずつっこまれてつい、口をつぐむ。
「……走馬灯の、ような……」
「走馬灯は死の間際に見るもののはずですけど」
「だから、なんつーのかな……夢は夢なんだけど、別にいい夢とかではなくて」
なんだろなあ、と無意識に宙を見つめる。
「なんか、今までのことを振り返るような夢だったんだよ。それで、オーディション受けるって決めてよかったなって思ったの」
「大和さん……」
しんみりした声が降ってきて、ソウを見上げた。目を細めてる。感情は読み取れないけれど、たぶん──
「今も競争は、苦手ですか?」
ポツンと投げ掛けられたその問いかけは、まるで晴れ間に突然降ってきた雨粒みたいだった。
……あぁ。そういえば、ソウには話したんだっけか。
「競争しなきゃ生きていけない世界だからな、してるけどさ、そりゃあできることならしたくないかなあ」
見やれば視線がばちんとぶつかる。
「ソウは?」
「僕は……」
考え込むように、視線を落とす。長いまつ毛がより引き立って見える。
「僕も、同じだと思います」
そしてゆっくり、言葉を選びながら、困ったように笑った。
そうだよな、困っちまうよな。
「なあソウ」
エプロンの裾を掴む、なんてそんな仕草、二十二の男がしたって可愛くないのは百も承知だけど。
「あの日……おまえさんたちと初めて会ったあの日が、俺が最初に覚悟を決めた日だよ」
それを伝えたところでどうしてほしい、ってこともないけれど。
「ありがとうございます、大和さん」
だからそんなふうに礼を言われるとは思いもしなかったし、なんの礼を言われているのかも分からなかった。
「えっ、と……」
「アイドリッシュセブンになってくれて」
手が、取られる。
「甘えてくれて」
「っ……」
それはかつて俺がソウにかけた言葉に似ているような気がした。
「まったく、大人になっちゃって」
そんな呟きは眼鏡の下に隠して。
少しだけの覚悟を積み重ねて、俺は今ここに立っている。