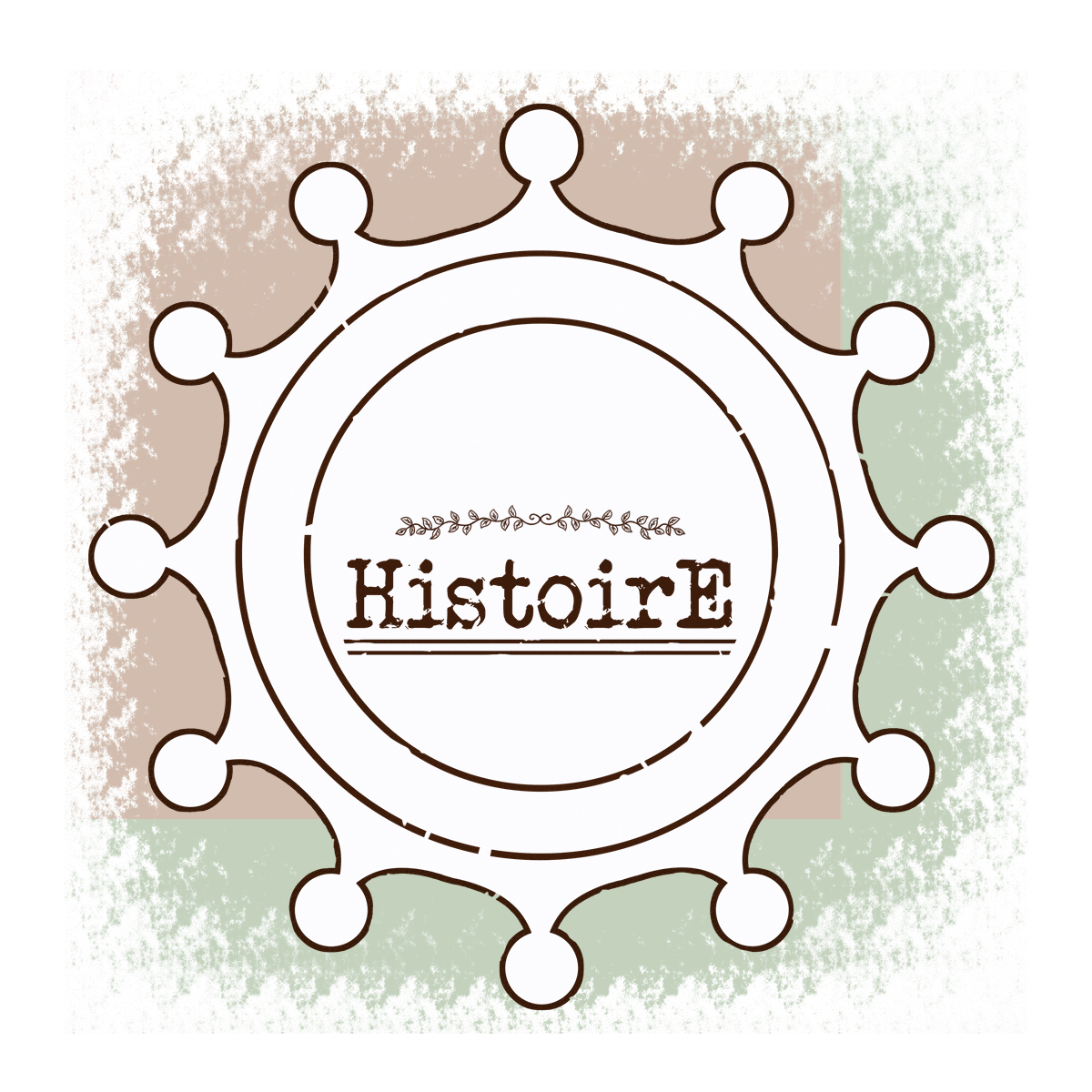ある日突然、俺の世界から人が消えた。人間も魔法使いも問わず、皆平等に。
初めはみんなのいたずらだと思った。姿を隠して、俺をからかっているんだろうと。けれどいたずらにしては不可解な点があった。街に出てみても人一人いないからだ。そもそも、そんな悪戯をするような者はいない。いたとしてせいぜいムルくらいだ。
声だけは聞こえるのにその姿はこの目に映らない。すぐ近くに気配は感じるのにどこを探しても俺には視認できない。
それが〈大いなる厄災〉と戦い、そして負けたことによって俺が負った奇妙な傷だった。
日常生活は不便だ。それでも事情を知る者は頼めば俺に触れて、その素敵な笑顔を見せてくれる。事情を知らぬ、わざわざ明かす必要のない者が相手であっても、気配でしのぐことも難しくはないし、それなりに誤魔化されてくれる。
しかしそれは平時だから何とかなっているに過ぎない。有事にこの目は、仇となる。味方や守るべき者を、守れないどころか傷つけてしまうかもしれない、敵の剣に斬られるかもしれない……「視えない」とはそういうことだ。
「おはようございます、カイン」
明るい声が聞こえて、廊下に賢者様がいることを知る。足音で誰かがいることは察していたが、それが賢者様だったらしい。声の響きからしてそう遠くないところにいるのだろう。
たたっと駆け寄ってきた賢者様が俺の手にハイタッチする。ぱっ、と目の前で落ち着いた色の髪が揺れた。
「おはよう、晶」
「はい。おはようございます」
朗らかな声は一片の曇りもないように感じた。この人は異界から突然、たった一人きりで見知らぬ世界に呼び出されたにも関わらず、いつだってその背中はしゃんとして、瞳は真っ直ぐに前を向いていた。明るい声と瞳に、俺も頑張らなきゃなと励まされる。
「朝ごはん、何ですかね」
楽しみですねと嬉しそうに笑う晶の声が弾んでいる。食堂からの香ばしい香りが扉の外まで漂っている。ベーコンはありそうだなと、胸を高鳴らせた。
「騎士様」
不気味な声が響く。この魔法舎でそんな言葉を口にするのはたった一人。同時に、その声がそう呼ぶ相手が俺だということも分かっている。
「……オーエン」
中庭の木の根元に白い外套に身を包んだ男が脚を伸ばして佇んでいた。真っ赤な宝石と蜂蜜、異なる色の瞳と視線が交わる。
――唯一、
「ねえ騎士様、僕今とっても退屈しているんだ。話し相手になってよ」
「お断りだ」
唯一、俺がその手に触れることなくこの瞳に映すことができる相手、それがオーエンだ。本来、こいつの左の蜂蜜色の瞳は俺のもので、俺の左の、ルビー色の瞳はオーエンのものだ。
北の魔法使いが魔法舎で共同生活を始めてしばらく経つが、その中でも特にオーエンはことあるごとに俺に構ってくる。ミスラやブラッドリーと比べても俺となんて話題が特別多いわけでもないだろうに。オーエンにとって俺はただの遊び道具に過ぎないのだろう。
「ひどいなあ。そんなに冷たくしないでよ」
「おまえと話をしても、俺にとっていいことなんてひとつもないだろう」
自分でも思った以上に尖った声が出てしまった。確かにオーエンのことはあまり好んで関わりたいと思うような相手ではないけれど、少しやりすぎたかと決まり悪くなる。
「ふん。騎士様が聞いて呆れるね。おまえは僕のことを冷たくあしらう。そうやって、嫌いな相手にはそんな態度を取るんだ」
大袈裟に、傷つけられたみたいな口ぶり。そうは言いながらも、その両の目と口は楽しそうに、意地悪く細められる。これ以上俺が何を言っても、こいつを楽しませるだけだろう。それほど悔しいことはない。
「用がないなら俺は行くぞ」
「無視しないでよ。話聞いてなかったの? 話し相手になってって言ったんだよ。本当ひどいよね、騎士様は」
どの口が言うんだ、と思いながらも怒る気にもなれない。それこそオーエンの思う壺だろうからだ。それに、こいつの物言いに俺もいい加減慣れてきた。
「ねえ騎士様、いつになったら僕と勝負してくれるの? この目、返してほしいんでしょう?」
にたにたと音が聞こえてきそうな、試すような笑い方でまだ話を続ける。退屈していると言ったのは本当らしい。そうは言っても、たとえオーエンが暇だろうと俺も同じというわけじゃない。
「それはまだ先だ。俺がもっと強くなって、おまえに勝てるようになったら。……その時は正々堂々、おまえに勝負を挑んでやる」
「ふうん、そんな悠長なこと言ってたら、何百年経っても僕に勝てないんじゃない? そうしたら一生、この目は僕のものだね」
「どう言われようと構わないさ。……だけど、そうだな。俺からもひとつ言っておきたいことがある」
「……なに?」
俺から何かを言われるのが意外だったのか、オーエンは少しの間きょとんとして目をまん丸に見開いた。その表情がまるで幼い子どものようで、不意をつかれる。けれどすぐにいつもの不機嫌そうな表情に戻って、そのことに少しだけ安心する。
今の表情はまるで、こいつの奇妙な傷を思い出すから。
「俺は必ずおまえから目を奪い返してみせる。だからそれまでは絶対に石にならないでくれよ」
俺の目を嵌めたまま石になられるなんて、たまったものじゃない。
自分の左目を指差して、願うような、どこか挑戦的な言葉で告げる。
「………………は?」
それは、想像していた地獄の底から響いてくるような声ではなかった。思わず振り向けば、そこでオーエンは虚をつかれたように、さっきよりももっとポカンと、口まで開けてこちらを見ていた。
「え」
あれ? 俺、何か変なこと言ったか?
まさかそんな反応が返ってくるなんて露ほども思わなかった俺は「あ、えっと」なんて意味のない言葉を口からぽろぽろ溢してしまう。なんというか、拍子抜けにもほどがある。
「騎士様なんて知らない」
そうして俺がああでもないこうでもないと頭をぐるぐるしている間に、オーエンはふらりと姿を消してしまった。
どうしてあんな言葉を口走ったのだろうか。今となってはそう思う。思い返してみれば傲慢だった。だからオーエンはあれ以来、俺の前に姿を見せないのだろうか。
数百年を生きるオーエンに比べてみれば、たったの二十二年しか生きていない俺は、オズにも言われたが赤子のようなものだろう。今のままじゃ、魔法も到底敵いっこない。なにせ相手はあの北の魔法使い、オーエンだ。オーエンにしてみれば、そんな箸にも棒にも引っかからないような相手に「俺と戦うまで死ぬな」と言われるだなんて。きっと誇りを傷つけただろう。
謝りたいと思った。たとえ自分の目を勝手に奪っていった憎らしい相手であっても、ここで謝らなければ俺自身も己の誇りを守れない。
だがここ数日、その肝心のオーエンが俺の前に姿を見せない。北の魔法使いは任務に出ていないし、暇さえあればミスラと諍いを起こしていたはずなのにそれすらも見かけない。そのミスラにオーエンを見なかったかと尋ねれば普通にその辺で見かけると言う。今までは暇さえあれば俺に絡んできたものだから、俺が避けられているのは明白だった。
どうすればいいかと思案し、中庭で姿の見えないオーエンに――というより宙に向かって話しかける。俺を避けて姿を消しているのであれば、逆に俺のことが見える場所に常にいるはずだ。
「オーエン! おい、オーエン! 話がしたいんだ! 出てきてくれ! オーエン! ……いないのか!?」
どれだけ呼びかけても、どれだけ辺りを見回してみても、ほかの場所で同じことをやっても、白い外套も、左右で色の違う瞳も、銀灰色の髪も見つけられない。空気が揺れる気配すらもない。かくりと肩を落として、その日は結局部屋に戻った。
朝、目が覚めた瞬間、俺は世界に一人取り残されている。
ずっと誰かがいる世界を生きてきた。それが突然、鏡写しの双眸を持つ男のほかは誰もいない世界に塗り変わった。……オーエンがいないと、俺は俺の世界の中で本当に一人になってしまう。
朝陽が射し込む魔法舎を歩く。静まりかえったそこには確かに人の気配があるが、恐らくまだ皆ベッドの中だろう。日課のハイタッチをする相手もいない中で鍛錬を始める。今日は任務もないし、アーサーが城での仕事で魔法舎にいないからオズの授業もない。終日一人で鍛えるのもいいかもしれない。そのことに少しだけほっとする自分がいることに気づく。
賑やかな場所に身を置くことが多いから気がつかなかったが、俺は――言葉として適当かどうかは定かではないが――孤独に対しての耐性がない。特にこの目に起こっている厄災の傷のように、周囲に人がいるはずなのに俺だけが独り取り残されているという状況が、かなり精神的にきつい。それならいっそ、少しの間だけでも完全に一人きりなる方がよっぽど落ち着く。今がまさにそんなタイミングだった。こんな時、まだまだ未熟だなと思い知らされる。
……そうだ、俺は未熟者なんだ。鍛錬が足りない。魔法も、剣術も、何もかも。強くならなくてはいけない。強くなって、主君も仲間も賢者様も、国も街も人々も、世界も、みんなみんな守ってみせる。理由なんてない、それが騎士だからだ。
がむしゃらに、走り込みをして、筋力トレーニングをして、剣を振るって、オズに繰り返し指摘された魔法の調整を連続する。何度も何度も何度も……。気がつけば日は落ちて、大きな月が頭上で輝いていた。
「っ、はっ……、はあ……」
仰向けに寝転がって、両手足を投げ出す。確か、この格好のことを前の賢者様は大の字と言っていただろうか。
「でっかい月だなあ」
思わずそう漏らして、それから目を細めた。
俺の瞳はあの月と同じ色だ。厄災討伐の夜が来るたび……いや、夜になって月を見るたび、左目を取り替えられた日を思い出す。忘れた日なんてない。目と騎士の身分を奪われて、やってきたここであいつと再会した時も、爛々と輝く金色の左目が俺を見ていた。なぜ俺を見ている? それは俺の目なのに。鏡合わせの赤と金の瞳に射抜かれるのはひどく不可解な感覚だった。
オーエンは魔法舎には滅多に近寄らなかったし、厄災の夜にしか姿を現さなかったから、断とうとしても簡単に断ち切れない因縁を結ばれたのに俺はあいつのことをよく知らなかった。ただ、オーエンは悪名高い魔法使いとして名を馳せていたから悪い噂は絶えなかったし、実際俺はあいつに痛い目を見せられている。俺の左目に嵌め込まれた紅の瞳はオーエンとの繋がりを象徴するようなものだ。周囲の人間からはだんだんオーエンに呪いをかけられているんじゃないか、操られているんじゃないかと囁かれるようになって、片目を隠すようになった。これ以上、人々に不安を与えたくなんてなかったし、オーエンは確かにいけ好かない奴だが、今は賢者の魔法使いの仲間でもあるし、あいつの悪い噂を立たせたくない気持ちがなかったわけじゃない。
……俺にとって、オーエンは仲間でありながらいつか勝つべき相手ではあるが、それ以上にはなり得ない。はずだった。そのはずなのに、
「どうして」
オーエンだけが見えちまうんだ。
紋章の刻まれた手首で目を覆った。
翌朝、いつもより早めの朝食を終えるとすぐに、魔法舎の塔に賢者様と俺、ヒース、シノ、ファウスト、ブラッドリー、ミチル、フィガロが集まっていた。任務に出発するためだ。東の国の北との国境いの村に魔獣が現れているのだという。
被害の内容は主に農作物が食べられるというものだった。魔獣は夜行性らしく、人間がいない時間に畑に現れては農作物を食べるそうだ。だが、夕刻に魔獣と鉢合わせた数人の村民が怪我、二日前には遂に死者が出たらしい。
「フィガロはまず怪我をした人間の治療とその傷痕の観察をしろ。ミチルはその手伝いを。シノとカインとブラッドリーは周辺の調査、ヒースは賢者と一緒に村で聞き込みをしてくれ。ああ、賢者は一度怪我人の様子を見てからだ。僕も賢者に同行する」
エレベーターで東の塔に向かい、そこから箒で北上する。目的の村へ向かう空の下で、ファウストがテキパキと到着後の役割を分担した。依頼は昨夜遅くに舞い込んだもので、急を要する依頼だったため魔法舎で話し合っている時間はなかった。できることならミスラに頼んで空間の扉を繋げてもらうべきだったのだろうが、生憎ミスラは機嫌が悪く、それどころではなかったのだ。今同じ方向を向いて飛んでいる顔触れも、今日は運良く何も任務が入っていない日だったからベストメンバーが揃ったが、医療知識のあるフィガロや夜目の利くシノ、戦闘慣れしている俺やブラッドリーが別の依頼に出ていたら他の魔法使いが出向くことになっただろう。オーエンがいると尚よかったのだが、案の定姿を現すことはなく、オーエンは不参加となった。ブラッドリー曰く、昨夜から見ていないらしい。
「賢者様、寒くありませんか? だいぶ気温が下がってきましたね」
「今のところは平気です。ヒースこそ、寒くないですか?」
「俺もまだ大丈夫です。お気遣いありがとうございます」
太陽が真上に昇りきった頃、国境の山がぼんやりと見えはじめる。目的の村はあの山の手前だ。日はまだ高いのに、頬に当たる風が少し冷たくなってきたなと思っていたら、少し後ろを飛ぶヒースと、彼の箒に乗っている賢者様の会話が聞こえてきた。北寄りの土地ということもあり、それぞれ魔法や服装で防寒対策をしている。
「見えた。あそこだ」
フィガロが眼下に集落を見つけ、指差した。誰からともなく村めがけて徐々に高度を落とし、村の外れに順に着陸していく。最後尾を飛んでいたシノが地面に足をつけたのを確認して村へ向かった。
「最初に村長さんにご挨拶しましょう」
賢者様の言葉に肯き、少し歩くうちに村の入り口で村長の息子だという男に迎えられ、家まで案内される。
村長の家への道中、見かけた村民は片手で足りるほどだった。ひっそりと自然に溶け込むように家々は佇んでいる。村全体が澄んだ空気に包まれており、比例するように人々も控えめだ。まるで何かに怯えるように、簡単に会釈だけをしてそそくさと引っ込んだり、顔を背けられてしまう。村の規模は小さくはないはずなのに妙に静かだった。魔法使い……いや、魔獣の被害が出ているのだからそれへの不安が村全体に立ち込めているのだろうか。
招き入れられた家で村の長に簡単に挨拶を済ませ、用意された昼食を摂りながら事情を聞いたが、魔法舎で聞いた内容がほぼすべてのようで、それ以上の情報は得られなかった。食事を終えたらすぐに空の上で決めた役割に各々分かれる。再集合するのは一時間後だ。
「ブラッドリー、北側を頼めるか?」
「あ? 俺に指図すんじゃねえよ」
廊下に出て、周辺調査を任されたシノ、ブラッドリーと打ち合わせる。村は山脈の麓にあり、北側と西側は山で、特に北側は北の国の国境に近く、気候もそれに類する。気候だけじゃない。特に俺は中央の人間だ。うっかり国境を越えてしまう、なんてことはできれば避けたい。そう考えて、北へ行くならブラッドリーが適任だと彼に頼むが、さすがに一度では了承してくれない。
「北との国境になる。あんたが行ってくれると助かるんだ」
「あれ? みなさんこんなところでどうしたんですか?」
「ああ、ミチル。どこを調べるか、分担を決めているんだ」
そこへ、フィガロと一緒に怪我人の家へ向かう予定のミチルが声をかけてきた。
「なるほど……。皆さんは村の外を見回るんですよね」
「ああ」
ミチルの視線は羨望と、少しの諦めを宿している。僕は弱いから、と、その言葉はまるで呪いのように、ミチルを縛っているようだ。
「なんだ? てめぇも行きたいのか?」
「ぼっ、僕にはフィガロ先生のお手伝いがありますから」
「どの口が言ってんだよ。行きたいって顔に書いてあんぞ」
「かっ……書いてません! そんなこと言ってるブラッドリーさんはどこへ行くんですか?」
「俺様は……」
憧れと挑発の眼差しを受けながら尋ねられたブラッドリーはチラッと俺の顔を一瞥してくる。今まさにそのことを決めていたのだ。
「北側だ」
そう答えたのはほかでもないブラッドリー本人だった。
「こいつらが下手に北の国境を越えちまったらめんどくせえからな」
仕方なくだよ、なんて言いながらも、ブラッドリーは得意げだ。ブラッドリーはミチルをやけに気にかけている。可愛がっている弟分みたいな感覚なのだろう。そんなミチルに、意識的か無意識的かは俺には分からないが、いいところを見せたいんだろう。
「……ちっ。てなわけだ、騎士さんよ。北は任されてやる」
ミチルが廊下の先に姿を消すと、ブラッドリーは舌打ちをしながらも、満更でもなさそうににやりと笑った。
「ははは……助かるよ」
「ならオレは東側へ行く。カインは西へ行け」
「わかった」
南側は道中、箒で上空から軽く見渡していたが特にこれといった異変は見当たらなかった。シノは優先順位が低いと見たのだろう。俺も同意見だった。
地図上で見た限り、東側は緑が深く、実際、森の力が強そうな印象だった。シノが森番を務めていたシャーウッドの森に通ずるものもあるのかもしれない。山も森も、慣れた者が調査する方がいいに決まっている。俺は騎士団の仕事でどちらにも行ったことはあるが、恐らく森の中でシノには敵わない。それならせめて、森は任せた方がいい。なかなか的を射たシノの采配に特に反する理由もなく、俺は二人と別れて村の西側へと向かった。
一時間後、再度集まった各々が集めた情報はよく似た特徴を持っていた。恐らくこれが魔獣の正体に繋がると見て間違いない。
フィガロが診た怪我人の傷、シノが村の東側の森で見つけた足跡、村人が聞いたという鳴き声……
「猪でまず間違いないと思うよ」
「猪だろうな」
「……」
フィガロとファウストの声が重なる。互いに視線を交差させたのち、肩を竦めたフィガロが手でファウストに先を促すと、一拍置いてファウストが話し始めた。この場は彼が取り仕切るのだろう。
「……シノが見つけたという足跡や、村人が聞いたという鳴き声から猪の類で間違いないだろう」
「聞いてはいたが、蹄は随分大きかったぞ」
「俺が診た傷も、通常の猪の牙のものと比べると倍以上はあったんじゃないかな」
「そういえば大きさの違う足跡があった。少なくとも二頭はいると考えた方がいい」
「厄介だな……」
ファウストが腕を組む。大きさの異なる複数頭がいる――つまり子どもがいる可能性が高いということになる。魔獣であろうが、もし子育て中であればそれだけでも警戒心が強く、気が立っているはずだ。そこへ大いなる厄災の影響が加わればと考えるとファウストの言う通り、厄介だ。過去の例から考えても力が暴走している可能性は高い。
オーエンがいてくれさえすれば、とこんな時になっても考えてしまう。あいつがいれば例え相手が暴走していても、俺たちじゃ言葉が通じなくても、意思の疎通ができる可能性はないだろうか?
……いや、どうにもならないことを考えたところで仕方がない。ぶんぶんと首を振って思考を振り払う。
「村民の話では、日が落ちると唸り声のようなものが響いてくるらしい。依頼書にも夕刻に鉢合わせたとあった。日没前に森へ向かうべきだが」
「俺もファウストに賛成だよ。ま、俺とミチルは賢者様と一緒に村で待機だけどね」
「え!」
ミチルが短く挙げた声には少しの非難が混ざっていた。
「僕は行っちゃダメなんですか?」
「凶暴な魔獣の可能性が高いんだから、危ないだろう? ミチルに危険なことはさせたくないし、もしものことがあったら、ルチルに合わせる顔がないよ。ミスラも怖いしね」
だから、ね? とフィガロはミチルに笑いかけるが、ミチルはそれでも……と食い下がる。
「おいフィガロ、そいつは俺が連れていく」
「ブラッドリーさん……?」
それを見兼ねたのか、ほかに理由があるのか、それともただの気まぐれか、ブラッドリーはミチルを顎でしゃくって指した。
「俺は東の呪い屋と後方に回る。俺の魔道具は銃だし、間合いが長い。強化魔法も後方支援向きだ。相手との距離もあるからそこまで危険じゃねえ。第一、こいつが結界を張るだろ」
「は? 何を勝手に――」
「ブラッドリーの言うことも一理ある」
ブラッドリーに突然こいつと呼ばれ、ミチルの守護を任されそうになったファウストが抗議の声を上げた。が、それはシノの言葉に阻まれる。そうだ。今ここにいる魔法使いを見回せばファウストは後方向きだし、ブラッドリーも間合いは長い。他の魔法使いそれぞれの役割も見えてくる。
「そうだな。オレとカインが前衛、ファウストとブラッドリー、それから……ヒースも後衛だ」
「おっ、東のちっこいのはよく分かってんじゃねえか。それでどうだ? 呪い屋」
「おい、ちっこいって言うな」
各々の成すべきことが着々と決まっていく。その度、緊張に皆の顔が引き締まっていくのが分かる。高まっていく緊張と高揚を感じる、この瞬間が俺は結構好きだ。
「はあ……分かったよ。確かにこの人員ならそれが最適案だ。フィガロ、おまえもそれでいいな」
ため息をつくファウストも、先導者としてはどうすべきか分かっているのだろう。フィガロに確認、の体を取っているがこれは決定事項の報告だ。
「……分かった。そうしよう。ファウスト、ミチルを頼むよ」
納得しているようには見えないが、フィガロも了承する。それに、彼がファウストに投げかけた眼差しは信頼そのものだった。フィガロにとってファウストは、ミチルを預けるに足る相手なんだろう。
「おまえに言われるまでもない」
忌々しげにファウストは眉根を寄せて言い捨てる。それでも彼は役目を放り出さない。それがファウストの元来の気質なのだろうし、彼が中央の建国に関わった聖なる魔法使いではないかと言われているのにも肯けた。
ブラッドリーもそうだ。こうして長い期間共に過ごして見えてきた面倒見の良い人間性は、今までと同じように厄災迎撃の時に集まるのみではきっと見えてこなかった。ずっと、横暴なだけの盗賊団の元ボスだと思い込み続けていただろう。
「それじゃあ、少し休んだら森へ向かおう」
ファウストは告げた。
フィガロと賢者様に見送られ、村を出て森へ向かう。
前衛後衛に分かれるといっても、長距離離れるわけではない。シノが巣の見当をつけたという付近までは六人で移動し、やや手前でファウスト、ミチル、ヒース、ブラッドリーと別れる。もしもの時はブラッドリー、ヒースが援護に来てくれるということになった。
日は傾き、夜の気配がする。淡い橙が、紺色を混ぜたような灰色に覆われようとしている。魔法舎や中央の城よりも標高の高い土地のせいか、高いはずの空がいつもより近く感じた。
さく、と足元の草を踏み鳴らす。草は枯れ、乾いた音が響いた。
「カイン」
「ん?」
「調子が悪いなら無理をするな」
「え――」
「おまえ、さっきの作戦会議中何も言わなかっただろ。いつもは聞かれていなくてもベラベラ話すくせに」
「ベラベラって……」
「騎士団長だったんだろ? ああいう場でおまえの意見は助かる」
次はもっと聞かせてくれよ、なんてまさか俺がそんなことを言われる日が来ようとは、夢にも思わなかった。それを言われる相手がシノだということにも驚きだが。
「そうだな……だが、さっきのシノの采配は見事なものだったと思うぞ」
そうだろ。そう言ってシノは得意顔で振り返った。――その時だった。
「ッ、シノ!!」
「!?」
ズン、と明らかに規格外の重量が地面を踏みしめる音がしたかと思えば、赤土色の大きな獣がそこにいた。咄嗟にシノに呼びかけるのが精一杯だ。
「退がれ!!」
「分かってる!!」
シノはこちらへ一歩飛び退き、俺に並ぶ。
「ブブォオオオオオオオ!!!!!」
こちらを睨み、威嚇の声をあげた猪は俺の知る、成体のそれを恐らく三倍ほどは上回る。間違いない。こいつが村に出没していた魔獣だろう。
俺は剣の柄に手をかけ、鞘から引き抜く。夕陽を浴びて、刀身は黄金色の光を放つ。シノも宙に手を翳し、淡く手元が光ったと思えば、刃に細かな装飾が施され青黒味を帯びた、彼の背丈を上回るほどの大鎌が出現していた。
「はは……それにしてもでかいな」
「そうか? 少し大きいくらいだろ」
思わず漏らした本音に、シノは思わぬ言葉で返してきた。やはりこいつは大物かもしれない。俺は剣を持っていない側の手を差し出し、シノの手がそれを軽く叩く。念には念を入れて、今日二度目のハイタッチだ。
「行くぞ」
「ああ。いつでもいいぞ」
ゆっくりと息を吸い込み、そして吐き出す。例え敵が何者であろうと、その気迫に呑まれてはならない。呼吸を整え、緊張と高揚に逸る心を落ち着かせる。自分の唇の間から漏れる、スーっという音がやけに大きく聞こえた。
――ザッ!
「〈アドノポテンスム〉!」
足を一歩踏み込んだ瞬間、どこからか聞き慣れた呪文が飛んできて、まだ魔力を込めてもいないのに魔道具でもある剣に力が集まるのを感じる。――ブラッドリーだ。
「〈サティルクナート・ムルクリード〉」
「〈レプセヴァイヴルプ・スノス〉」
ファウスト、ヒースの呪文も続く。別れる前にもファウストは守護のまじないをかけてくれたが、これはどういうものなのだろうか。
間合いに走り込み、剣へと魔力を集中させる。
「〈グラディアス・プロセーラ〉!!」
剣が光を帯び、ふわりと風が吹き抜けるような感覚がやってくる。魔力を込め、剣を振り上げ――
「っ、くッ!」
振り下ろした剣はキィン! と甲高い音を立てて猪の牙に受け止められる。固い……!
「カイン!!」
後ろから呼ばれ、飛び退く。
「〈マッツァー・スディーパス〉!!」
シノの呪文が耳元で聞こえる。見開いた瞳に映ったシノは魔獣の足元めがけて、鎌を横へ薙ぎ払うように振っていた。その刃は体毛に覆われた前脚にわずかに赤い線を入れるが、目の前の猪はびくともしない。
「こういう生き物はまず足元から崩すのが定石だ! 脚を狙え!」
「分かった!」
賢者の魔法使いに選ばれる前にも魔法生物を仕留めたシノの言うことだ。頼もしい助言に従わない理由はない。
「随分と固いな」
「ああ。だが、これくらいが張り合いがあっていい」
「同感だ」
なんとなく、シノとはいいコンビになれそうな気がする。気が昂って口角が上がるのを抑えられず、唇は自ずと弧を描く。ああ、こんな感覚は久しぶりだ。不謹慎かもしれないが、今、とても楽しい。
バンッ!!
背後で銃声が鳴り、続く銃の持ち主の呪文がやけに響いた。一瞬敵の動きが止まり、思わず揃って振り返る。
「ったく、援護してやる。けど、とっとと仕留めねえと俺が撃ち殺しちまう、ぞ!」
再び銃声が鳴り響く。ブラッドリーの魔力がこもった銃弾は強力なようで、獣は痛々しく地鳴りのような悲鳴を上げた。
「あいつに手柄をやるもんか。行くぞ、カイン!」
「ああ!!」
前に一歩踏み込む。柄を握る手に力を込め直し、もう一歩。指の先の先まで魔力を集中させ、また一歩。そうやって左右の脚を前へ前へ――
「〈グラディアス・プロセーラ〉!!」
脚へ力を込め跳び上がる。袈裟斬りに振り下ろした剣にざくり、と確かな手応えがあった。
目の前の、山のような巨体が轟音を立ててわずかに沈む。前脚を崩した!
「シノ!!」
「ああ! いっ、くぞ!!」
敵の後ろに回り込んだシノが鎌を振るう。間もなく、魔獣からは再び唸り声が上がる。直後、ブラッドリーの銃が鳴いた。猪は抗うように暴れ、そして何かを訴えるようにもう一度轟音を上げる。何か……
「シノ! こいつ今……!」
「ああ! 恐らくもう一体――」
すぐ近くにいる。直感すると同時に見回したそこに小さな猪がいた。……子どもだ。
「……っく!」
小さいと言っても魔法生物でない猪の成体くらいの大きさはある。考えるよりも先に、身体が動いていた。
「カイン!!」
「シノはでかいのを頼む! あっちは俺が行く!」
俺は駆ける。完全に日が暮れた森を。月明かりを受けて銀色に輝く剣を持って。
――この子猪を殺すために。
「〈グラディアス・プロセーラ〉!」
ひやりとした空気が鼻先を撫でた。さすがは北との国境。日中も中央より気温は低い方だったが、朝晩は比べ物にならないほどだ。
「これは寒いな……」
つい、いつもの癖でタンクトップ一枚で外に出ようとしてしまったが、思わず扉を閉めた。さすがにあのまま外に出ていては風邪を引いてしまう。
練習着に袖を通して改めて外に出る。昨晩はあんなに疲弊していたのに、なぜだか早く目が覚めてしまった。まだ精神が昂っているのだろうか。確かにあまり眠れていない気がする。
あちこち歩き回るのは気が引けるが、近くを軽く散歩するくらいならいいだろうかと足を踏み出した。
「ふー」
近くを軽く、のつもりが、結局山道の途中まで来てしまった。昨日の調査でも足を踏み入れた山だ。道から少し外れたところに見つけた大きな樹の幹に背を預けて、根元に腰を下ろす。深く息を吸い込めば、樹々や草花、木の実、岩や土、朝露の香りが鼻腔を通り、肺を満たす。
村を出るまで誰とも会わなかった。……いや、会わないようにすぐに道を外れたのは俺だ。誰かとすれ違ったとしても俺には相手が見えない。足音が鳴れば誰かがいることくらいは分かるが、それもすべてを補えるわけではないだろう。誰かの目に映った俺がその誰かに気が付けなかったら、その人にとって賢者の魔法使いは挨拶をしない存在になってしまう。そんな誤解は生みたくない。だから人目を避けた。
はー、と長く息を吐き出す。
人が見えなくなった世界で浮かび上がるのはいつだって紅と金の一対の瞳。あいつ、今どうしてるんだろう。
オーエンが姿を見せないことなんて今に始まったことじゃない。むしろ最近では頻繁に見かけるくらいだ。だからこそ色鮮やかな世界にたったひとつの真っ白な姿は際立つのだが。
誰もいない世界の朝は、静かで、寒かった。
「……っ、三百二十四、……三百二十、五……!」
なかなか寝付けないまま、窓の外が徐々に明るくなる。地平線が淡い紫色に染まる頃、魔法舎の前で腕立て伏せをしていた。どれだけ体を動かしても眠気はやってこない。机仕事が苦手だからというのを逆手にとって、筋トレを始める前に机の前に座ってみたりもしたが特に変わらなかった。
「……カイン、今日は一段と早いな」
聞き慣れたスロートークが頭上から降ってきた。レノックスだ。
「あぁ……レノックス。おはよう。ちょっと、眠れなくてな」
「……寝ていないのか?」
声にやや心配の色が滲んだ。おおらかで優しい彼らしい。
「まあ、そんなこともたまにはあるだろう。これからランニングか? 俺も付き合うよ」
「しかし……」
危ないという制止の声を無視して、俺はレノの背をバシリと叩いて、行こうぜと笑った。今は何も考えず体を動かしていたかった。
任務を終えて一泊、昨日の昼過ぎには魔法舎に戻った。遅めの昼食を遠征のメンバーで囲んだ後解散の運びとなり、それぞれの足は自然と私室へと向かった。
同階のヒースとシノとはそれぞれ部屋の前で別れ、俺も自室の扉を開けた。眠ろうとしてベッドへと身体を沈めてみたが、どうしても意識は残ったままだった。
……子どもの猪は、俺の剣の一突きで倒れた。恐らく子の死を親に見せれば更に親猪は錯乱し、暴れ狂うだろう。俺の身体を盾に、親猪の目から事切れた子の体を出来る限り隠して木の影に移動させた。そして再び、巨大な獣に対峙する。猪は脚が使えなくなっても牙でシノに応戦していた。それだけでも十分な脅威だった。だからこそ確実に倒さなければならない。どこからか魔法の弾が飛んでくる。ブラッドリーの銃の火薬ではなく、ヒースの魔法の匂いが鼻をかすめた。ヒースは攻撃魔法が得意じゃない。それでも援護してくれている。まだまだ動ける。足も腕も動く。やることは、ひとつだった。剣を、構えた。
人間の味方でいるために、人間に害をなす相手の命を刈り取る。今までだって同じことをやっていたはずなのに、昨日はどうしてもその手が鈍るのを感じた。もちろん手は抜いていない。あの猪の親子は、一緒に俺たちが殺した。きっとそれしか方法はなかった。一体だけ残して再び村を脅かされても、村の人間たちも俺たちも困るし、子どもだけを生き残したところで親もいないのに生きていけるかも分からない。三者にとって一番の選択肢を選んだつもりだ。
それでも、これが正しいことだったのかと、性懲りもなく一人で堂々巡りを繰り返した。考えていたら、夜が明けようとしていた。
たまらなくなって、部屋を飛び出した。
「……馬鹿なの?」
俺を罵る声が聞こえる。けれどそれは至極もっともな言葉で、今回に限っていえば申し開きのしようがない。
寝不足で危ないという忠告を聞かぬままランニングをして怪我をするなんて呆れる。騎士団時代に部下たちには口酸っぱく注意していたくせに、自分がこの様ではあまりにも情けない。
「情けないね、騎士様」
その通りだ。返す言葉もない。
フィガロに診てもらったところ軽い捻挫ということだったが、しばらくは安静にしていろと釘を刺された。フィガロの治癒魔法ならこの捻挫を治すのはわけもないらしいが、彼が言うには全身を休める意味も込めて敢えて治してくれないらしい。曰く、オーバーワークとのこと。
それが五日前のことだ。
「……」
声の主は、俺の瞳が唯一映す相手。中庭で右腕に刻まれた紋章を見つめていたら気配を感じて、視線だけでその姿を確認している。
ふらりと現れたその男を、俺はずっと探していた。こいつには言いたいことがあった。
俺は騎士団長だった。いつも誰かの前にいて、誰かを引っ張っていた。自分で言うのもなんだが、中央の国では未だ人気は根強く、街で声をかけられることも少なくない。出身である栄光の街に行けば更に声をかけられる回数は増すばかりだ。生まれてからずっと、人に囲まれて生きてきた。親にも友人にも仲間にも恵まれたと思っている。
……それでも。
それでも、どこかに孤独を感じた。
男女を問わず人に好かれる自覚はあったし、そんな人々にとって俺は特別だったのかもしれない。けれど俺にとって特別だった人はいなかった。
気配がする。声が聞こえる。それでも、視覚情報が占める割合は大きい。この目に視えないものをそこに「在る」とはなかなか認識し難い。何も視認できず、自分しかいない世界を、もしかしたら少しだけ――心のどこかで心細く感じていたのかもしれない。ひとりぼっちが寂しいのは、人間も魔法使いも、男も女も、何百年生きていようがきっと変わらない。
だから、今までと何ひとつ変わることなくそこにいる唯一の存在がたとえ因縁の相手であったとしても、俺は知らず知らずのうちに安堵していた。ひとりきりじゃないと思えた。相手が相手だけにまるでおかしくて笑ってしまうが、認めざるを得ない。むしろ因縁のあるこいつだからこそ、俺たちは何があっても互いが他と外れた意味で常に特別であり続ける。
分かっている。答えはすぐそこにあるような予感があった。俺の唯一になってくれる存在は手を伸ばせば届くそこに――
「……は?」
手を伸ばして、思いっきり抱き寄せる。
肉付きの悪い身体は、力を込めると今にもポッキリ折れてしまいそうだ。
「ちょっ……! 何するんだよ。離せよ!」
「いやだ」
「はあ!?」
「離したくない」
「ふざけるな、急に抱きついてくるなんておまえはけだものにでもなったの?」
「何とでも言え。何を言われても構わない。……構わないから、しばらくこうしていたい」
「……っ、馬鹿じゃないの!?」
吐き捨てるように言いながらも、腕の中のオーエンはおとなしくなる。
目に映すだけじゃ足りない。この手に触れて確かめたい。触れなくても見えるから今までは触れてこなかった。
だけどそうじゃない。
見えていたって、そこにこいつがいることを今この手に触れて確かめたい。
ひとりぼっちは、寂しいんだ。
✧✧
epilogue
「この間はすまなかった」
「は? 何の話?」
「俺がおまえに勝負を挑みに行くまで死なないでくれって言ったことだよ。何百も歳下の俺が言うことじゃなかった。生意気だったなと思ってる」
「……ああ、そのこと」
「? 随分、あっさりなんだな」
「他のことに気を取られて忘れてたよ」
「他のこと?」
「ぁ……何でもない。今のことは忘れろ」
「でも」
「…………………………死ぬな、だなんて……。初めて言われた」
「…………は?」
「知ってるだろ。僕は死なない。だからミスラは容赦なく僕を殺そうとしてきて──実際何度も死んでるし、オズやブラッドリーも容赦がない。まあ僕がブラッドリーに負けるはずはないけど。そもそも間違ってるんだよ。僕に対して死ぬなって思うことが。それなのに騎士様は自分の目を奪った相手にまでそんな言葉をかけるから馬鹿馬鹿しくって」
「……違うだろ」
「何が。違わないよ」
「本当のことを言えよ、オーエン」
「本当のことだよ」
「違う。本当に馬鹿らしく思っているなら、おまえはあの場で俺を嘲笑したはずだ。それなのに笑いもしなかった。まるで、どうすればいいのか分からなくなったみたいに、戸惑っていた」
「……ほんとむかつく」
「おい――」
「……そうだよ。どうすればいいのか分からなくなった。僕に死ぬな、なんて言うやつは初めてだった。きっと賢者様も同じことを言うんだろうね。だけどそんなこと言われたことがなかった僕は心が変に動いて、ぐちゃぐちゃになって気持ち悪かった。今までもそういうことはあったけど、なんだか今までとは違った。あんなふうになったのは初めてだったし……だから呆気にとられたし、騎士様の顔を見ていたくなかったんだ。……これで満足?」
「…………ぶっ」
「は? 何笑ってるんだよ」
「いや、別に」
「ふざけるな。僕に無理やり話をさせておいて、挙句それを笑うなんて騎士様には人の心がないの?」
「違う違う!」
「何が違うって言うんだよ」
「だっておまえ……」
「僕が何」
「言われて嬉しかったんじゃないのか?」
「……は?」
「だから、死ぬなって言われたのが――」
「うるさい。黙れよ。それより騎士様こそ目を取り返すまで死なないようにしなよね」
「え……?」
「……なに」
「いや……オーエンが心配してくれるなんて思わなくて……」
「はあ!? 僕がいつおまえなんかの心配をしたって?」
「あ、いやっだから」
「もういい、やっぱり騎士様なんて知らない」
✧✧