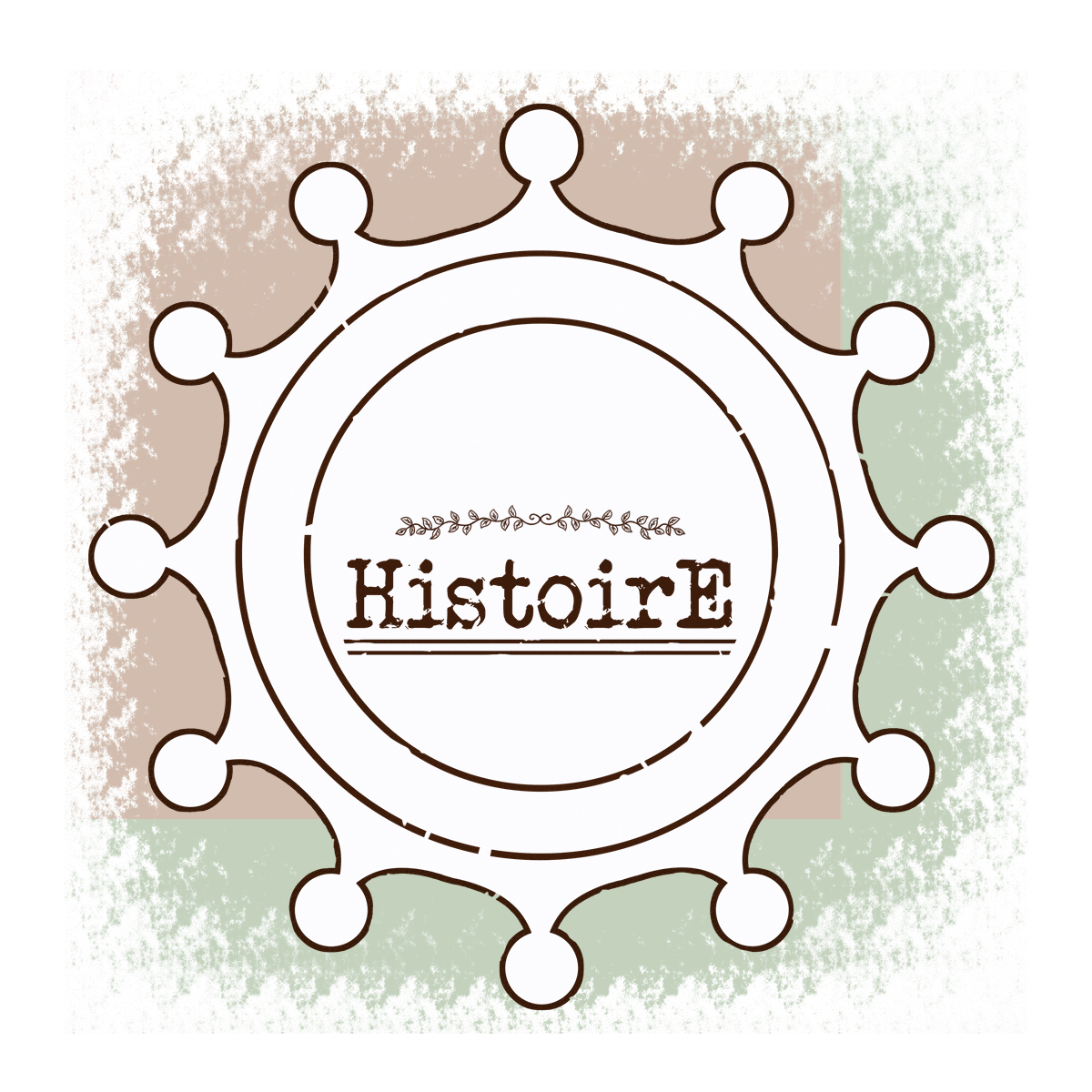「環くん、もう起きなきゃ」
耳に心地のよい音色が名前を奏でる。環の意識はその声に引き寄せられるかのように、だんだんと、浮上していく。
「ん……そーちゃん……?」
七月九日。午前九時三十二分。いつもよりやや遅めの覚醒。まぶたを持ち上げるとすみれ色の水晶玉がふたつ、柔和な微笑みをたたえて環の顔を覗き込んでいた。
「うん。おはよう」
「はよ……ってぇ」
「え?」
起き上がろうとベッドに手をつくと、ジンと腕が痛む。外的な痛みではない。恐らく何かの筋肉痛だ。
「や、そーちゃんじゃない……なんこれ……めっちゃ痛い…………」
「……あっ、もしかして、筋肉痛?」
環が腕をさすっていると、壮五は何かに思い当たったようで眉をハの字に下げたまま問いかけてくる。
「え、うん。たぶん」
「やっぱり。僕もだよ」
「そーちゃんも?」
思いもよらぬ言葉に、環はおうむ返しで聞き返してしまう。
「……というか、たぶん全員だと思う」
「へ?」
それはもっと予想外で、間抜けな声が漏れる。全員って、アイドリッシュセブン全員?
「昨日のライブで、ほら、みんなタオルを回しただろう? だから……」
「え、それ!?」
二日間に渡ったドームライブのアンコールで、アイドリッシュセブンはTHANK YOU FOR YOUR EVERYTHING! を披露した。ライブTシャツに着替え、同じくグッズのマフラータオルを文字通り振り回しながらステージの上を駆け回った。確かに環に限らずメンバー全員が腕が千切れそうなほど回しまくったが、筋肉痛となって痛むほどだっただろうか。
「だけど、ほかに心当たりもないし」
「まぁ、確かに…………」
壮五の言葉は否定のしようがない。ダンスは日々練習を積んでいて、満を持しての披露だった。今更筋肉痛になどなるはずもなかった。当日だけに限ったタオルのほかに、この痛みを引き起こした原因として思い当たるものもない。
「うわぁ、でもまじかー」
言葉にされ、事実として突き付けられると実感が湧いてくる。感嘆なのか何なのか、大した意味もない言葉が漏れる。
「ふふっ」
が、
「そーちゃんなんで笑ってんの?」
壮五はなぜだか笑っている。それが純粋に不思議で尋ねたのだが、恐らく環が気分を害したと勘違いしたのだろう、壮五は表情を強張らせて決まり悪そうに目をそらす。
「あ、いやその……」
「言ってみ?」
目を伏せた壮五の長いまつ毛を見つめ、なるたけ柔らかい声音で促す。隙間から覗く深い紫の瞳は、窓から射し込む夏の朝の陽射しを受けてキラキラと輝いていて、幻想的にすら思えてくる。環はこの瞳が好きだ。
「…………うん……その、ね。これって、すごく幸せな痛みだなあと思って」
「幸せな痛み?」
躊躇いがちに、しかし愛おしげに、その一聞すると矛盾した言葉を壮五は紡ぐ。
「うん。あんなに楽しくて、夢中になってタオルを振り回して……実を言うと僕は顔も痛いんだ。その……笑いすぎたみたいで……あんなに大規模な、トリガーさんやリバーレさんとの合同ライブができたのもファンの皆さんがずっと応援し続けていてくれたからで……それだけでも十分幸せなことなのに、そのうえあんなに楽しいなんて。だからこんなに腕や顔が痛くても……むしろ痛いくらいの方が、あの楽しかったことが夢じゃないって思えるから。それってすごく幸せなことだなって思うんだ。…………それに、きっと僕らより四時間近くもずっとペンライトを振り続けてくれたお客様の方がきっともっと痛いと思うよ」
壮五はこれは経験則、と付け足した。恥じらうように眉を下げて笑う姿が愛らしい。
「じゃー、これはその、幸せな痛み、なんだな。へへっ、勲章みたいでかっけー」
ライブに来てくれたみんなと俺らだけの特別なやつ。その感覚は嫌いじゃない。
「勲章か、確かにそうだね」
その言葉を壮五も繰り返す。
願わくば、この幸せがまた訪れますように。