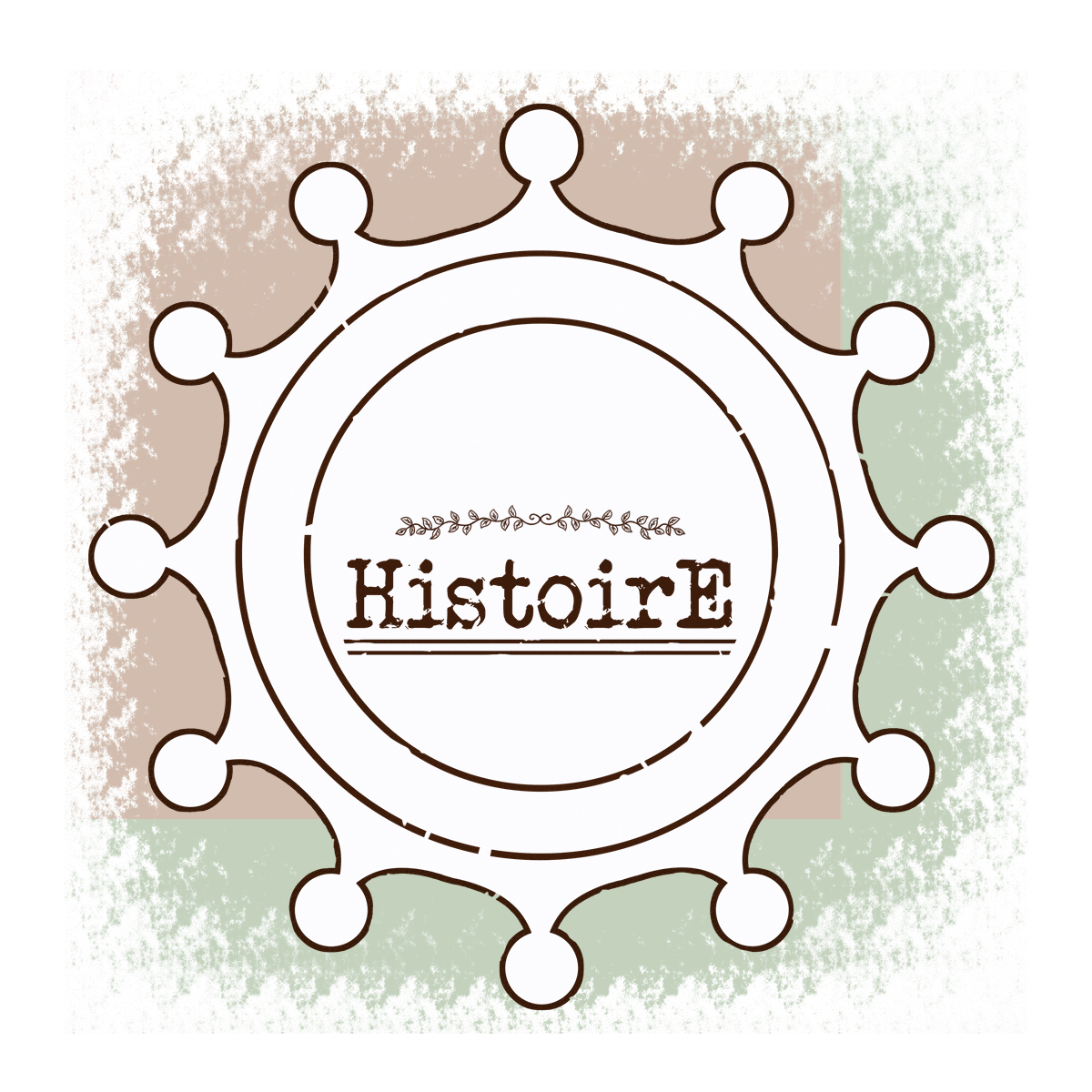隣国の璃月では新しい年になって最初の満月の夜に海灯祭という国を挙げた盛大な祭りが行われるらしい。人々は英雄を祀り、霄灯と呼ばれる灯籠に願いを込めて空に放つという。
「それがその霄灯ってやつ?」
七聖召喚の決闘招待を受けモンドに赴いた帰り、セノはちょうどその海灯祭を目前にした璃月港に立ち寄った。大陸随一と言われる港町は賑わい、数多の霄灯の温かな光が夜空を彩る。そのつもりで立ち寄ったわけではないセノもその光景には目を奪われた。スメールという国を出、相手が教令院の学者でなければセノはただの一般人に過ぎない。気軽に話しかけてきた露店の商人から記念に霄灯を買い、国境を越えてすぐのガンダルヴァー村でそれを土産としてティナリとコレイに渡した。おまけにモンドと璃月で見かけた野草も添えて。
「君の分は?」
ありがとうとティナリは受け取ったが、それはそれとして、とセノにじっとりとした眼差しを向けた。ティナリは自分だけが施しを受けることをやけに嫌がる。特にセノに対しては。
「俺は璃月港で書いてきた。持ち帰ってはいないが、願いは託したよ」
璃月港の総務司という機関が海灯祭を運営しており、セノはそこへ霄灯を預けてスメールへ帰ってきた。海灯祭当日、彼らがセノの願いを乗せた灯りを空へ放ってくれるはずだ。
「何を願ったの?」
その質問に、セノは一瞬躊躇う。願いの内容に関する本人にそれを告げるのは些か照れ臭さが混じるのだ。
「……言わなければいけないか?」
「大マハマトラともあろう人が隠し事するんだ?」
「それは……」
そう言われるとセノが痛いことをティナリは分かっている。当然それが本心でないことをセノも承知しているが、だとしても、セノはティナリに弱いのだ。
「冗談だよ、別に強制はしな――」
「お前たちの……ティナリとコレイの願いが叶うようにと」
案の定、ティナリは無理強いをしなかったが、隠す必要がないのも確かで。セノはティナリの言葉を遮るように自身が捧げた祈りの内容を告げた。それを聞いたティナリは眉を顰める。聞いてきたのはお前の方だろう。
「……自分のことを祈りなよ」
「これが俺の願いだ」
「はあ〜〜〜〜」
がくりと肩を落としてティナリは大きなため息をついた。
自分自身に望むことなどない。自分にとって大切にしたいと思える人が幸福であってほしい。それがセノが願うことだ。――ああでも、七聖召喚の賽や手札の引きが良くて困ることはないな。
始まりがどうであれ、今のセノにとってティナリは良き友人であり、コレイは責任を持つべき存在だ。そこに情が介入するのは簡単で、おまけに元来の優しさが加わればセノはみるみる彼らを気にかけ、愛し、甘やかし、尽くすようになる。結果が今のこれだ。
「なら僕は君とコレイのことを願うよ」
「お前らしいな」
「お互い様でしょ? 君たちの無事が心身ともに僕のためになる。何度も言わせないで」
まったく、とティナリは唇を尖らせる。そのままペンを手に取り、インク瓶に漬ける。
――僕の大切な人たちが無事に元気でいて、その努力が報われますように。
清廉な文字で綴られたその祈りは宣言通りのものだ。
「分かってるよ」
それを見ながら、セノは答えるが、ティナリはさっと振り返って訝しげにセノを見上げてくる。
「本当に分かってる?」
「ああ」
「なら、次に君が怪我した時の言い訳を楽しみにしてるよ」
そう言い放ったティナリの顔の得意げなことといったら、七聖召喚で勝ちを確信したプレイヤーのそれとまったく同じだった。
「言っておくけど、体が無事だったらいい、なんて考えは駄目だからね」
駄目押しとばかりに追加されたその言葉はセノの首を捻らせるのに十分だった。
ティナリの――少なくともセノについての祈りが叶うにはまだ道のりが遠そうだ。
「さて、コレイも願いを書き終えた頃かな」