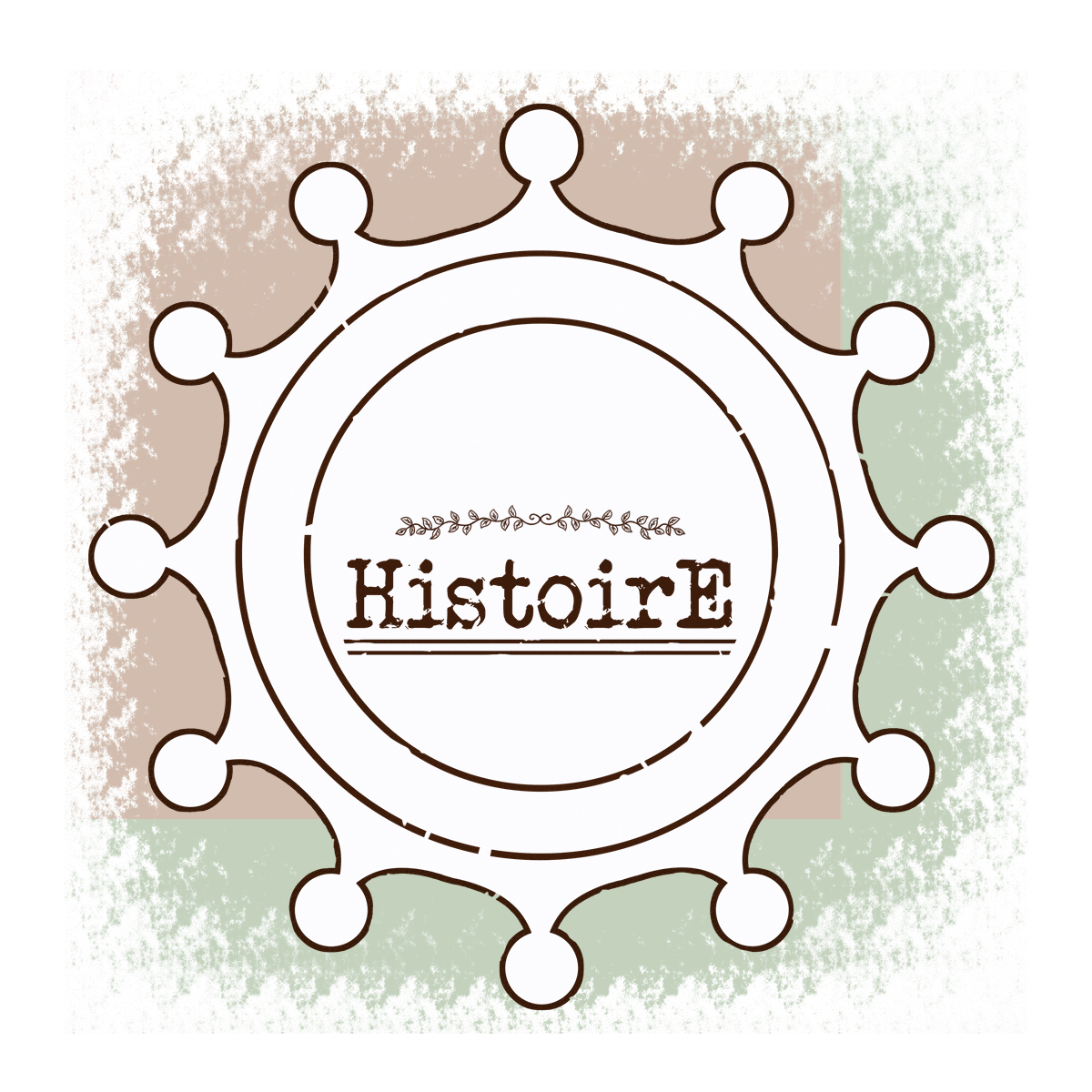金色の髪と瞳を持つ旅人とその小さな銀色の友人がスメールを訪れてしばらく経った。二人はスメール中を旅し、仲間たちと共に草神の救出と復権、そして一部の賢者たちによる創神計画などという馬鹿げた目論見の阻止を同時に成した。渦中にあった彼らは皆英雄となり、元より教令院に所属していたアルハイゼンは現在代理賢者を務め、セノは大マハマトラへの復帰を果たした。
一方ディシアと旅人は自由を好み、今もスメール――テイワット全土に及ぶかもしれない――を渡り歩いているようだ。旅人は当然スメールにもよく立ち寄るようで、その度に顔を見せにやって来る。珍しい植物や遠い海の向こうの稲妻料理が楽しめるのは二人のおかげだ。
金髪の旅人と銀色の友人はスメールの旅の中で、雨林だけでなく砂漠の奥深くまで足を踏み入れたらしい。ティナリには一生のうちに到底その土を踏むことなど叶わないであろう地なものだからと、二人の口から語られる冒険譚を夢中になって聞いたものだ。
当然、雨林の中でもティナリが知らないような世界に入り込んで冒険をしたという。それらの物語はどれも幻想的で、ティナリがいつか夢に見た世界のようでさえあった。
「で、なんだけど」
ティナリは腰に手を当て、仁王立ちをしてその大樹を見上げた。
「君はこれをどう思う? セノ」
「俺はお前の生徒じゃないが」
質問にそう返されて、ティナリはついあっけらかんと笑い声を上げた。確かに今のは先生が生徒の意見を聞く時みたいだった。
「あははっ、確かにそうだ」
セノはティナリの生徒ではなく、誰よりも強い絆を結んだ友人であり、共に居たいと願った愛する人でもある。
「だけど、こんなの見ちゃったらさ、聞きたくなるものだろ?」
パルディスディアイから北に一山越えたところにある七天神像から西に向かおうとすると、かつてそこは水没していたはずだった。それがいつの間にか水が抜かれ、近くに古代の装置が淡い光を放っていた。こんなことができるのは旅人とパイモン以外にはいない。ティナリはアビディアの森が主な活動地域であり、足を伸ばしても行くのはせいぜい研究拠点の一つでもあるパルディスディアイまでだ。それ以上西となると行く先は少し南下してキャラバン宿駅で、日常的に北へ向かうことはほとんどない。それが先日、永らく死域の拡大により延期を繰り返していたフィールドワークを再開した傍からこれを見つけた。冒険者というものはこうも好奇心に素直なのか、と思い至ったところで学者が言えることではないなと考え直したのだった。
古代の装置は滝の上にあり、滝を降りてそのまま進むと旅人たちがよく使っているワープポイントという、これもまた過去の文明による利器があった。道はまだ先へ続いている。遺跡らしき人工壁を横目に進むと、視界が開けて、広場のようなところに出た。そこに、この大樹が静かに佇んでいた。樹、と呼ぶにはあまりにも樹木らしからぬその姿は、どこか神秘的でこの世のものとは思えない。樹の前に人為的に作られたような小さな階段や広場を囲うような壁の跡あることから何かの象徴か、崇められた存在だったであろうことは推測できる。
螺旋状に巻いて空へ向かうのは幹か枝か。まるでいくつかの樹が互いに巻き付いて支え合っているかのような姿は神秘的ではあるが特別な力は感じない。観察を続ける中で、その小さな広場がやけに居心地がいいことに気が付いた。今度、セノを誘ってここに来よう、と思うほどには。
今日がそれを実行した日なわけだが、ティナリとセノは相変わらず大樹を見上げたままである。
「コレイがね」
ティナリは徐に口を開いた。先日ここを見付けてから考えた上での仮説がある。
「? ああ」
「アランナラ、って言葉をたまに口にするんだ。ほら、タンジェさんの絵本にもなってるあれ」
僅かに思考を巡らせたのち、セノはああ、と返してきた。その声音から思い当たったのだろうと、ティナリは続けた。
「スメールの大人たちは彼らを想像上の生き物で、実在はしないと考えてると思うけど僕はそうは思わない」
「見たことがあるのか?」
ティナリの言葉に、セノは僅かに目を見開く。だが、ティナリは首を横に振った。
「いや、ないよ。だけど以前、旅人からもその存在について聞かれたし、……ハイパシアも、口には出さなかったけど、たぶん彼らと交流があるんだろう」
アビディアの森でサティアワダライフの修行をしていた明論派の後輩がいる。ハイパシアという名の彼女は修行に夢中になりすぎて空腹で倒れることがしばしばあったため、ティナリも気にかけていたのだが、訪ねて行ったティナリを時たま平気な顔で迎えることがあった。そのことについて尋ねてみて返ってきた答えは「隣人」と呼ぶ存在による助力だった。ハイパシアは隣人と呼んでいたが、あの辺りでガンダルヴァー村以外の住人がいるなんて聞いたこともない。レンジャー長のティナリがそれを知らぬはずはないのだ。とすれば、答えは自ずと見えてくる。
「コレイは絵本で読んで会いたいと密かに思ってるみたいだけどね。だけど、旅人たちは彼らと交流があるみたいな、なんとなくそんな気がするんだ」
旅人とパイモンが時々、遠い目をするのをティナリは知っている。それは二人が旅人の片割れを探す果てのない旅の最中にあるためだと、初めは思っていた。だが、それは少し違ったらしい。二人はスメールの森に、木々に、草花に、少しだけ想いを重ねているようだった。以前、普段と少し様子の違った二人に大丈夫かと尋ねたことがあった。今考えるとあんな漠然とした質問、よく聞けたものだと思う。体調なのか精神的にか、それすらも曖昧な問いだ。だが、二人は困ったように笑って答えた。「大丈夫だよ。森が全てを記憶しているから」と。
「あの二人に、僕らに明かせない秘密があったり想像もできないような冒険をしてきたのは知ってる。その中に、この雨林のアランナラもいるんじゃないかって思うんだ」
「ティナリは、これはそのアランナラと関係があると考えているのか?」
「そうだね。植物学的にも、こんな樹木は存在しない。存在しないというか、見たことも聞いたこともなかった、と言うのが正しいかな」
再度、樹を見上げる。セノもティナリに倣ってそれを見上げているようだった。
「だが今俺たちの目の前に、確かに存在している」
「そう。信じられそうにもないだろ。だけど信じるしかない。これは夢じゃないからね」
セノの言葉を首肯する。夢のようであって、夢じゃない。神秘的な森は今、現実の目の前に広がっているのだ。それがティナリを魅了して離さない。
「旅人の言う『森は全てを記憶する』って言葉。僕は的を射ていると思うよ。森を理解しているからこその言葉だ。木々はその幹に年輪を刻み、枝葉を伸ばす。花は実を残し、土に帰れば再び芽を出す。全部そうやって森を形作ってる。全てその土と草木が覚えているからできることだよ。そういうふうに進化してきた」
視線を地面に落として、森の植物たちを見回す。足元を覆う草花、空に向かって高く伸びる木々。ティナリが共に生きていきたいと望んだものたちだ。
「旅人が今までの旅の中でその言葉を見出さなかった可能性がないとは思わないよ。だけど、初めて会った時とあの言葉を口にした時とで二人は違う目をしていたから、きっとスメールでの何か新しい冒険と発見がそう言わせたんだろうね」
振り返って笑うと、突然口が塞がれる。視界いっぱいに薄い瞼が映る。その向こうには白いまつ毛に縁取られた緋い宝石のような瞳が隠れているはずだ。口付けられたのだと理解してからティナリがその甘く優しい感覚を楽しめるほどには長い間そのままだったセノは、ちゅ、と小さな音を立ててようやく離れていった。
「……なに、いきなり」
「無性に、お前が好きだと思って」
「なにそれ」
ふ、と思わず笑いをこぼした。真っ直ぐにそんなことを伝えてくるセノが心から愛しく感じる。
「これも森は記憶するんだろうか?」
大真面目な顔で、顎に長い指をあてて考える彼にティナリは手を伸ばす。もしもこの森にアランナラという精霊がいるのだとしても、ティナリには見えないのだから今は関係ない。
「それはないかな」
僕らだけの秘密だからね、と。今度はティナリからキスをした。