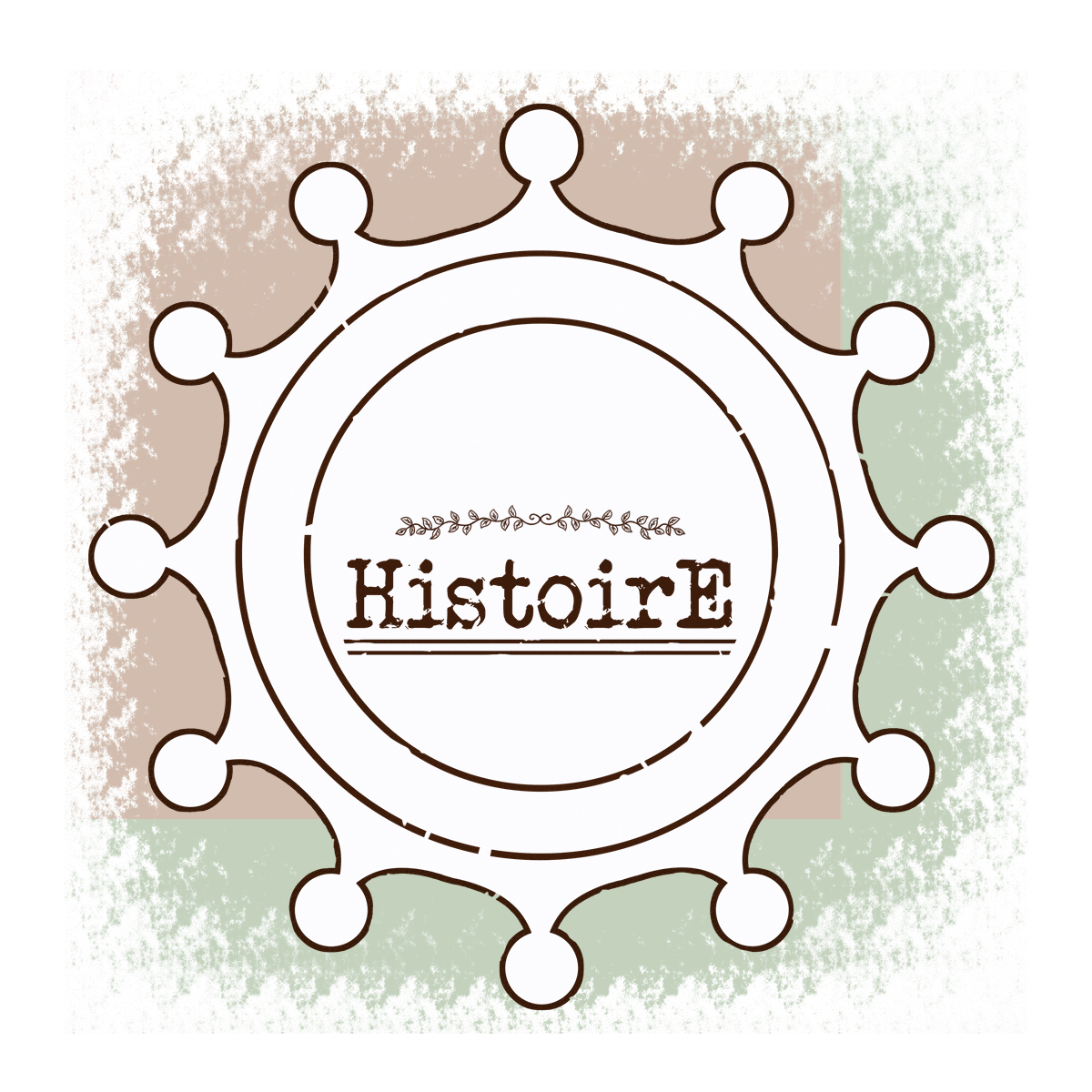「セノ、今日はどうする?」
セノがガンダルヴァー村に来て食事をするのは珍しいことじゃない。とはいえよくあるわけでもない。何せスメール中を縦横無尽に駆け回る大マハマトラだ。わざわざ自身の居住地でもない村に、友人とはいえレンジャーを訪ねて頻繁にやってくるなんてことはないのだ。
「明日は朝が早いから戻るよ」
もちろんそれは友人としてやってくる場合の話であり、仕事や互いの立場が絡むと話は別だ。これもよくある話ではないが、マハマトラがレンジャーに対して、何かしら協力を求めてくることはある。そんな時は当然、マハマトラ側の責任者であるセノが顔を見ることだってある。大マハマトラとガンダルヴァー村のレンジャー長は、その間にある強固な信頼のもとに素晴らしい連携を見せるのだ。
さて、前置きが長くなったが今日のセノは友人としてティナリの元を訪れた。七聖召喚に興じ、共に炊事場に立ち、夕食を囲む。穏やかな休日だった。セノがティナリの家に泊まることもそれほど多くもなかったが、過去になかったわけでもない。今日はどうするのかと聞いたところで、先の返答だ。
「そっか。分かった」
「次来る時はのんびりさせてもらうよ」
セノはそう言いながらピタを口へ運んだ。
「お前まで来る必要はなかったのに」
「僕がもう少しセノと話してたいんだよ。気にしないで」
夕飯を終えて、セノが帰ると言うのでティナリは村の出口まで見送ることにした。大した理由なんてない。ただ、もう少しだけ一緒にいたいだとか、話していたいだとか、それだけだ。名残惜しいだとか、そんな大層なことじゃない。
虫の鳴き声が静かな森に響き渡る。風は草木を揺らし、木々の間をひゅうひゅうと吹き抜ける。遠くで獣の鳴き声や動く音がしたり、風が木の葉を揺らしてざわざわと音を立てたりすると人々は不気味がって家へと戻るものだった。村人たちが寝静まるにはまだ少し早いが、それでもこの時間に外へ出ている人間は二人のほかにはいない。そのせいか、まるでこの世界にはティナリとセノの二人だけであるかのような錯覚すら覚える。ふといつもより少し暗く感じて上を見ると、月が細く細く欠けていた。まるでよく切れる刃物みたいだ。
「今日は月が随分細いね」
「え? ……ああ、そうだな」
ティナリの言葉で同じように空を見上げたセノはうなずいた。
「だがその分、星が見やすい」
「星?」
のんびりと並んで歩きながら、夜空について語る。静かで不思議で、まるでおとぎ話みたいだとティナリはぼんやりと思った。
「俺が今日砂漠にいたなら、これだけ月が暗く星が見やすいとありがたいと思うだろうな」
その付言に合点がいく。
「なるほど。確かにそうだろうね」
砂漠の景色は日々移り変わるうえ、どこも似た景色が続くせいで方角を見失いやすい。そのために、星は標となるのだ。そもそも夜の砂漠を移動するのは危険だが、セノはそれすらも厭わないためか人より少し星には詳しかった。
「そういえば、昔セノと二人で砂漠に行った時も一緒に星を見たよね」
まだティナリが教令院の学生だった頃の話だ。砂漠の自生植物を見たいと、セノに付き合ってもらって五日に及ぶ旅をした。砂漠で見る星空は雨林のそれとはまったく違って見えて、ティナリは何度かセノを天体観測に付き合わせたのだ。
「あの時の解説はとてもよかったな」
「からかわないでよ……砂漠を縦横無尽に移動する君が、あの程度のことを知らないはずないのに、僕ときたら……」
思い出すだけで恥ずかしくなって耳が垂れてくる。当時ティナリは入門書に書かれているような、星空の基礎的な知識を語ったのだ。セノがそれを知っているかもしれないという想像もせずに。
「確かに知っている知識も多くあったが、その理論や原理についてはあの時初めて聞いた。おかげで俺もまたひとつ学びを得た」
そう褒められると、今度はまた違った意味で少し恥ずかしくなる。
「そ、っか……」
恥ずかしい、けど嬉しい。
感情が尻尾に伝わって、ぶんぶんと揺れる。それに気が付いたのか、セノはふ、と笑った。少し暗い夜空の下だが、生憎ここは集落だ。道を照らす灯りくらいはある。
「ちょっと、笑わないでよ」
「悪い。だが、今日のティナリはいつもよりもいろんな顔をするなと思って」
照れたり、喜んだり、拗ねたり。と、優しい声で言うものだからティナリもそれ以上唇を尖らせるのはやめた。
村の出口はすぐそこだからだ。そんな顔でセノを見送るのは気が引けた。
「ねえセノ」
「ん?」
ティナリはさっき、ふと思い付いたことを切り出した。
「また砂漠に行こうよ。今度はコレイも一緒にさ。砂漠の植物も、星空の色彩も、こことはまるで違うから、あの子にも見せてあげたいんだ」
ティナリは気に入ったものは大事な人と共有したいと思う人間だ。あの忘れられない景色を、新たにできた大切な弟子にも見せてやりたい。彼女の体を蝕んでいた病は完治したのだから、もうどこへでも行けるはずだ。
「それはいいな」
振り返ったセノは、次に来た時は旅の計画を立てようとふわりと笑う。ティナリは彼にお別れのキスを落とした。
「じゃあね」
「ああ、また」
星が煌めく道を、セノは帰る。その黒い後ろ姿が見えなくなるまでティナリはそこに立っていた。
どうか彼の行く道が、少しでもその標にまっすぐでありますようにと願いながら。