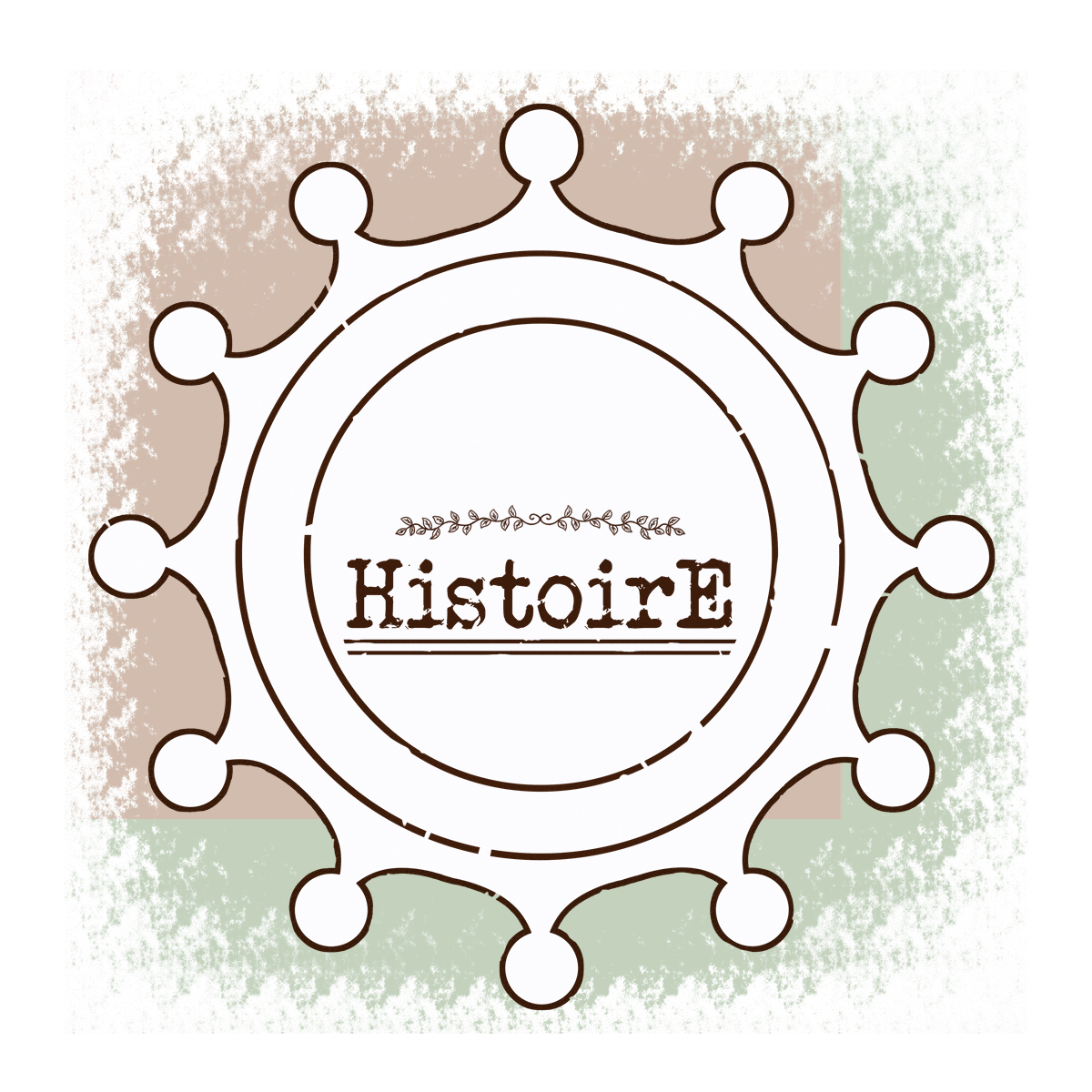コンコン、とノック音が響く。扉の向こうから足音が聞こえていたため、その人がドアを叩くのをティナリは知っていた。
「どうぞー」
ガチャリと音を立てて開いたドアの向こうから顔を出したのは、予想通りの褐色肌だった。
「調子はどうだ」
「まあまあかな。少なくとも、行き詰まって進まない、なんてことは起こらなさそうだよ」
論文から顔を上げて答えると、そうか、とセノは満足げに相槌を寄越した。がさりと音を立てた小さな紙の袋を差し出してくる。
「差し入れだ」
思わずそれを受け取る。程よい重さのそれからティナリの苦手な強い香辛料の香りはしない。袋の口を開いて中を覗けば、狐色のケーキが入っていた。グランドバザールで見かけるタフチーンによく似ているが、その形は店で見かけるものとは大きく異なる。
「ありがとう……どうしたのこれ」
お店のものじゃないよね? と聞けば、セノは少し驚いたように目を開いた。
「分かるのか?」
「一応ね」
そう答えると、セノは逡巡してから口を開く。
「……俺が作ったタフチーンだ。ティナリの口に合うといいんだが……」
その答えに、思わず本音が漏れる。
「セノって料理できるんだ……」
「似合わないだろう?」
そう言うセノの口元は僅かに笑っている。自嘲している様子ではなさそうだが、その表情にどこか申し訳なさを感じる。
「ごめん、ちょっと意外で……」
「構わない。マハマトラの仲間にも驚かれるんだ」
どうやらあの笑みは本気で面白がっているものだったらしい。人間、何度も同じことを驚かれると愉悦を感じるものだ。
「大したものじゃないよ。だが料理が特別得意というわけでもないから、口に合わなかったらすまない」
先ほどと似たようなことを言って、セノは僅かに眉を下げる。だが手に伝わる重みからセノの気持ちを感じて、ティナリは心が温かくなる。
「そんなことない。気持ちが嬉しいよ。ありがとう、セノ」
「――ってこともあったよね」
学生時代を振り返ったティナリは最後にそう締めて、次のキノコに手を伸ばした。
夕食の支度をそろそろ始めようという頃に、セノはガンダルヴァー村に顔を出した。元から共に食卓を囲む約束をしていた日だったが、彼の到着が予想よりも早まることは珍しい。疲れているだろうにとティナリが止めるのも構わず、セノは用意された食材を手に取った。見たところ怪我もしていないようだし、と結局ティナリの隣に立つことを受け入れたのだが、いつの間にか昔話に花を咲かせていた。セノは今ツルツル豆の下処理をしている。
「そういえば、そんなこともあったな」
「夜食に一口食べたら止まらなくなっちゃってさ。また作ってくれーって、その後しばらくせがんだろ?」
「あの時のティナリはかなり子どもっぽかったな」
過去の所業をそう指摘されて、ティナリはつい唇を尖らせた。というかそんなふうに思ってたのか。ものすごく微笑ましそうに語る口元が恨めしい。
「うるさいよ……そういえば、しばらくご馳走になってないよね。セノのタフチーン」
あの独創的な形に積み上げられた米の山はピラミッドを表現しているらしい。道理で見慣れぬ形に切り分けられるはずだった。
店で作られるものには香辛料が使われており、ティナリの舌にはあまり合わない。その点、セノが作ってくれるものは繊細な味わいでティナリは好きだった。彼の優しさが料理にも滲み出ているような気さえする。
「話してたら食べたくなってきちゃったな。でも今日は食材が足りないや」
「食材があったら作らせたのか?」
まさか、とセノは驚いたような声音だ。
「今だって手伝ってくれてるんだから変わらないだろ? こうして一緒に料理するのも楽しいしさ」
まあ、タフチーンは確か結構手間のかかる料理だし、仮に材料が揃ってても今から作ってもらうようなことはしないよ、と付け足す。
だがセノと食事をする時はガンダルヴァー村か、シティや宿駅であれば店に入ることがほとんどだ。彼の手料理を食べられる機会はなかなか巡ってこない。そこまで考えたところであ、とティナリは思い出す。この後予定を聞こうと思っていたことだが、別に今尋ねたところで変わりはしない。
「来月、シティに何日か滞在する仕事があるんだ。君の家に泊めてもらえると嬉しいんだけど、もし良ければその時に作ろうよ」
その提案に、セノはああ、と微笑んだ。