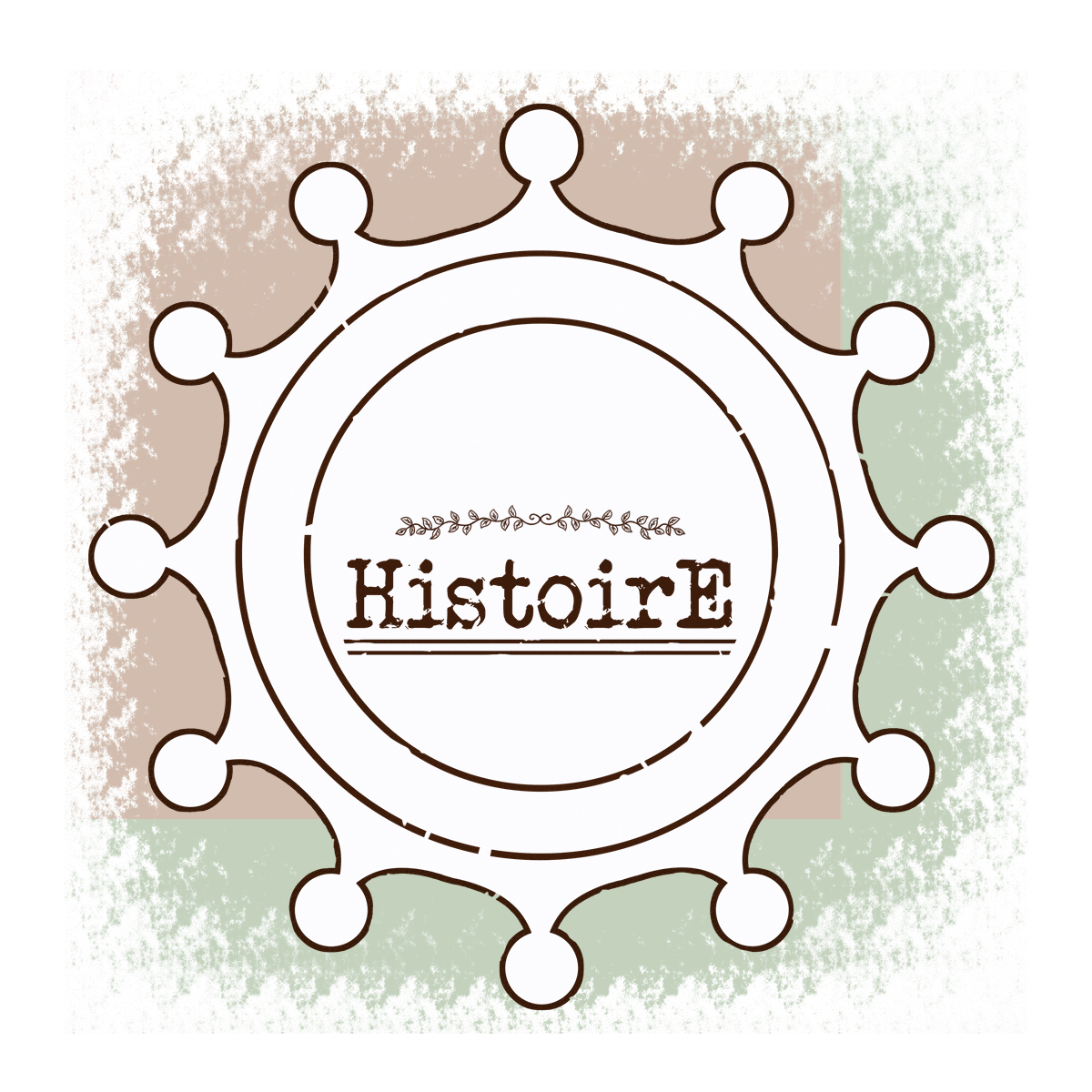それは突然だった。
「あ、セノ。いらっしゃい。予定よりちょっと早く着い――」
「ティナリ、家族になろう」
「は?」
◎◎◎
ガンダルヴァー村の、ティナリの家で約束をしていた。特にこれといった用はない。あるとすればティナリとコレイの顔を見に。時間が空けばアポイントも取らずにふらりと立ち寄るが、そのせいか会える確率は低かった。事前に約束をすることもあるが、だからといって毎回重要な理由があるわけでもない。だが、ティナリとセノはお互い忙しい身であるが、だからこそその合間を縫ってでも会って話すことを大切にしようと決めていた。
言い忘れていたが、ティナリとセノは現在交際関係にある。周囲へは隠しているわけではないが触れ回るようなことでもないので、聞かれれば答えるがわざわざ自分たちから明かすようなこともしていない。
コレイを除いては。
元々深い信頼関係があったからこそ、セノはモンドから連れ帰ったコレイをティナリの元へ預けた。二人はいわばコレイの保護者の立場にある。その二人が深い仲なのだと明かされたコレイの心情を思えば、少なくとも彼女が成人するまでは、何があってもこの関係は黙っておこうということも決めた。祝福はしてくれるかもしれないが複雑な気持ちを抱かせてしまう可能性もある。何より二人が恋仲となったのはコレイがまだ魔鱗病を患っていた頃だ。何より体調の回復を優先させたい中で、その情報は与えるべきではないだろうとの判断だった。
話を戻そう。ティナリの家で会う約束をしていたセノがガンダルヴァー村へ到着すると、コレイが視界に入った。魔鱗病が完治した今もなお、コレイはセノを少し怖がっている。魔神の力を封じた儀式を思い出すためだろう。首の後ろがチクリとする、と時々漏らしていると聞く。声をかけたかったがぐっと堪えて再び歩き出そうとしたその時だった。
「お母さん……」
コレイの呟く声が聞こえて、思わず立ち止まる。
コレイの生い立ちについてはおおよそ知っている。彼女の両親が恐らく、ファデュイの手によりこの世を去っているであろうことも。身寄りがなく医学を学びたいと言ったコレイをセノの元に置いておくのは彼女のために良くないと、モンドからスメールへの旅の中で判断した。セノの知る中で最も適した人物、それがティナリだ。ティナリはコレイを引き取ることを何度も断ってきたが、それでもコレイをガンダルヴァー村へ連れてきた時、ティナリは「これからはここが君の家で、ここのみんなは君の家族だよ」という言葉をかけていた。その言葉を聞いた彼女が嬉しそうな表情を浮かべていたことをセノは覚えている。ここに連れてきてよかったと思った。
それでも、幼い頃から実の母親の胸に抱かれ、頭を撫でられたという温かな記憶はコレイの中にはない。いくらティナリが良き師であっても、母親にはなれない。
◎◎◎
「……それで、家族?」
「そうだ」
「バカなの?」
いきなり「家族になろう」などと言われたものだから説明を求めたが、話を聞いた感想はこれに尽きる。セノなりにコレイのことを思ってのことなのは分かる。彼が世間で想像されるような冷酷な人間ではなく、温かな男であることをティナリはよく知っているから。
が。それはあまりに突飛な提案すぎる。
「だめだろうか」
「コレイは僕らの関係を知らないだろ」
「別に問題ないだろう。俺たちが仲のいい友人であることはコレイもよく知っている。その延長線上で家族という形になるだけだ」
「問題しかないよこのバカマトラ」
ティナリがはあとため息を吐けばセノはむうと小さく唸る。
「ティナリは俺と家族になるのはいやなのか?」
「そういうことは言ってな……は?」
別の角度から投げられた問いに、ティナリは思わず固まる。ちょっと待って、それはどう解釈すればいい質問?
「そうか、それならよかった」
反応に困る言葉ばかりが返ってくる。今日は何かの日だったか、頭の中で必死に探すが答えは見つかりそうにない。
「ん? ティナリ、どうした?」
「いや、なんでもない……」
固まったままのティナリを不思議に思ったらしいセノが尋ねてくるが、返事に迷い、結局まともなことは言えなかった。誰のせいでこんなことになってると思ってるんだという気持ちさえ湧いてくる。
その状況にふと心当たりがあって、ほっと胸を撫で下ろす。なんだ、そういうことか。
「……でも、セノにしては面白いジョークだったね。らしくはないけど」
だがティナリの希望は脆くも崩れ去る。セノが少しむっとした表情で首を傾げたからだ。
「? ジョークじゃないが」
だよね……。
「うぅ……」
「やはり、俺とは家族になりたくないか……?」
思わず机に突っ伏したティナリに、セノは不安げに声をかけてきた。頭の中でしょんぼりしたセノを想像するとチクリと心が痛んだ。もしティナリと同じ耳がセノにもあったなら、それはしなりと伏せられていたことだろう。
それにしてもなぜこの男はそんなことも分からないのか。ティナリが本気でいやだと思っているならはっきりと言うに決まっている。それをしないのには理由がある。はあ、とため息をもう一つ吐いて上体を起こす。
「そうじゃない。誰もそんなこと言ってないだろ。……ただ、コレイを理由にはしたくないんだよ。あの子には家族を作ってあげたいけど、僕が君と家族になりたい理由にコレイは関係ない」
ティナリは頭を上げて、セノの目をまっすぐに見据えた。緑と大地の色の瞳が、夕焼け色の瞳を射抜く。
「君のぜんぶが欲しいからだ。だから次は僕から言わせてよ。家族になろう、って」
宣戦布告はどうやら効果覿面だったらしく、みるみるうちにセノの頬は紅く染まる。これで少しはさっきの僕の気持ちを分かってもらえただろうか。