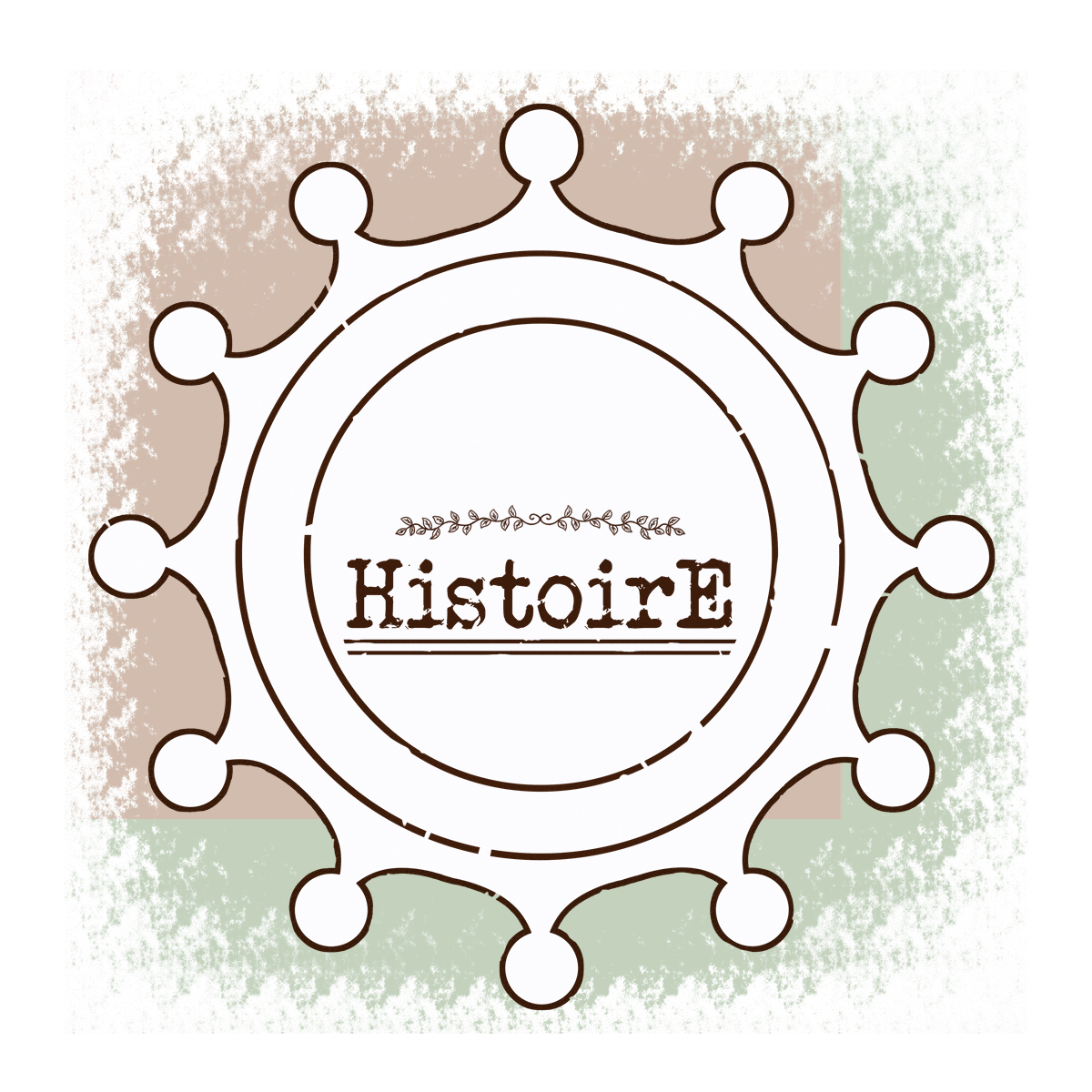春の青空を切り取ったような涼やかな瞳だった。
出会った日はちょうど春の晴天で、どこからか薄紅色の花びらが降っていたように思う。きらきら、きらきら。澄んだ瞳はまるでガラスのようで、ビー玉に似ているような気がした。
夏が終わってしまう前に
IDOLiSH7としてデビューをした夏、七人でのアルバムツアーの合間を縫って僕は環くんと二人、MEZZO”としての仕事で東京と地方を行ったり来たりしていた。ゆっくりとした休息なんてなくて、仕事が終わればホテルへ戻り、次の日の用意をして眠りに落ちる。朝、目を覚ませば簡単に身支度をして仕事へ向かう。それを繰り返して何度目だったか、珍しく陽が落ちきる前に仕事が終わり、宿泊先の宿へ戻る道すがら浴衣を着た子どもたちと何度かすれ違った。
「花火大会とか祭とか、あんのかな」
ぽつり、環くんが呟く。声はそちらへの興味を示していた。
「そうかもしれないね」
だけど明日も移動がある。テレビ局での収録も、ツアー公演もある。心を鬼にして、隣でそわそわしだした環くんに、わざと素っ気ない声で返す。
「そーちゃん、祭とか嫌い?」
それを僕が好まない故だと受け取ったのか、環くんの声は不安に揺れたそれへ変わる。
「嫌い、ではないけど得意ではないかな。それに僕らはあまり人目につくような場所は避けないといけないから……」
「あ、そっか……」
その声はしぼんでいて、先程まで環くんから飛び出しているように見えたきらきらとしたものはどこかへ消え失せてしまっていた。捨てられた子犬のような落胆具合に、僕も少し良心が痛んだのだろう。
「花火大会ならホテルから見えるかもしれないよ」
「んー、そうだな……」
「…………少しだけ、暗くなってから覗きに行ってみるかい?」
「え……まじで? いいの?」
「う、ん……」
僕はつくづく甘いらしい。環くんの瞳は輝きを取り戻す。僕は歳下の相方の、この目が好きでたまらないのだ。
「見て! そーちゃん、光ってる!」
陽が完全に落ちきった頃、荷物をホテルに置いて身軽になった僕らは祭りへ繰り出した。フロントで聞いたところによれば、近くの神社の氏子祭らしい。
楽しそうに環くんは笑顔をこぼす。はしゃぎすぎないようにとか、あまり大きな声を上げないようにとか、歩きながら口酸っぱく言い聞かせていたこともすっかり忘れてしまっているようだった。
……まぁ、仕方ないか。
はっ、と短く息を吐く。ここのところ本当に仕事続きで、息をつく間もないほどだった。環くんはまだ高校生だし、アイドルでなければ今日みたいな日だって、昼間は友達とプールやゲームセンターなんかへ遊びに行って、夜は祭に来たりするのだろう。それが日々、仕事仕事。多少ハメを外すのは目を瞑ることにした。
彼が指差した先には光り物の屋台がある。ぼうっと淡く光る蛍光色がぶら下がっており、前には浴衣姿の子どもたちが集まっていた。
「ああゆうの、今はもう欲しいとか思わねーけど、見てるとやっぱキレーだなって思う」
その視線は懐かしい『いつか』に向いていた。彼の隣には、妹がいる。知らず知らずのうちに僕は拳をぎゅっと、強く握りしめていた。
「なーそーちゃん、ラムネ飲みたい」
「ラムネ?」
出店をひと通り見て回り、たこ焼きやらかき氷やらを平らげてから、環くんはとある一点を見つめて言った。視線の先を追えばなるほど、確かにラムネの文字。
「いいよ、買おうか」
「そーちゃんは?」
「僕? 僕は、いいかな。甘いだろう?」
「そっか……」
環くんは見るからに肩を落とす。 さっきかき氷を食べないと言った時も少し寂しそうにはしていたけれど。
「でも喉は乾いたんじゃね? なんか飲む?」
「それじゃあ、お茶にしようかな」
屋台のおじさんに声をかけて、氷水の中に沈められていたラムネと麦茶をそれぞれ受け取る。キンと冷えていて、火照った肌や乾いた喉に心地いい。
ペットボトルの口からお茶を流し込み、こくんと喉を鳴らす。
からん。
涼しげな音が鳴って、環くんの方を見る。
「ん?」
視線を感じたのか、環くんの動きがぴたりと止まる。口につけようと持ち上げていたラムネの瓶……を模したプラスチック容器をゆっくりと下ろし、こちらへ差し出してくる。
「やっぱ、いる?」
心なしか嬉しそうにも聞こえる。そんな音を奏でられると断れないじゃないか。
「……それじゃあ、少しだけ…………」
「おー」
ん、と更にこちらへ突き出されたラムネの容器を受け取り、麦茶で潤した唇へ運ぶ。
ぱちぱち。炭酸が弾ける。やや遅れてやってきた甘味を飲み下す。
「……あんま、美味くない?」
「そんなことないよ」
「ウソつくの下手くそ」
「っ……」
眉でもひそめてしまっただろうか。表情には出さないようにしたつもりだけどうまくできていなかったらしい。
「でも、後味がスッキリしているから我慢できないってわけじゃないよ」
「ガマンしてまで飲まなくていーし」
ふいとそっぽを向かれた。あぁ、どうしていつもうまくできないんだろう。どうして僕は、環くんを怒らせてしまうんだろう。
「むりやり飲ませたみたいで、やだ」
「え──?」
ぽつりとこぼされた声は雑踏の中でよく聞こえない。
「なんもねー」
手を出されて容器を返すと、環くんは残っていたラムネを一気に流し込んだ。
「これビー玉取れっかな?」
「ビー玉?」
「そ。中入ってるだろ? 飲み口んとこ、回したら……ほら、取れた」
言いながら環くんは中身が空になった容器の飲み口を、ペットボトルのキャップを開けるようにねじる。キャップのような部分が外れて、中からころんとガラス玉が環くんの手の平へ転がり出てきた。
「へぇ……!」
実を言うと僕はこうして祭に出かけたことはほぼない。叔父さんが生きていた頃に数回と、高校時代に一度、同級生と出かけたことがあるけれど合わせても片手で足りるほど。僕はラムネは飲まないし、同級生はラムネを飲んでもビー玉を取り出すなんてことをしなかった。
「このままだとベタベタするし、その辺のトイレでちょっと洗ってくる」
ちょっと待ってて、と環くんは手洗いを探して人混みに消える。
提灯が揺れる。不思議な光景だった。
境内の両端に出店が立ち並ぶ。奇妙な景色だった。
空はあんなに暗いのに、周囲はこんなに明るい。初めて見る世界だった。
祭には出かけたことがあるのに、こんなにじっくりと周囲を見回したこともなければゆったりと過ごしたこともない。それもそうか、祭は賑やかなものなのだから。
もし環くんが来たそうにしなかったら、きっと今日もいつもと変わらず明日の仕事の用意をして、ただ眠りについていただろう。毎日が非日常みたいな仕事をしているけれど、それが僕にとっての日常になっている。まだ慣れないことも分からないこともたくさんあるけれど、それが肌に馴染む日はそう遠くないうちに来るだろう。
それでもこの祭という非日常は、きっと誰にとっても特別なものなのだ。
今日の僕のように。
「そーちゃん」
僕をそう呼ぶ声はこの世界にたったひたつ。
「へへっ、どー?」
得意げに笑ってみせた彼の手には淡く、春の青空の色を湛えたびいどろの玉。
「……それ」
目が離せなくて、無意識のうちに手を伸ばしていた。
「君の瞳の色だ」
両手の平へと置かれた小さな宝石のようなまん丸のそれを見つめる。
「え? ……あ、ほんとだ。これ色ついてんな」
「ついてないのも、あるの?」
「おー、ある」
「そうなんだ……」
でも……
「僕は、この色が好きだなあ」
きゅっと一度握る。
「……気に入ったんなら、やるけど」
そんな僕の様子を見てか、環くんはそう申し出てくれる。
「え、いいの?」
見上げた先で環くんは少し照れくさそうに後頭部をぽりぽりとかいている。
「いーよ。俺ほかにも持ってるし。あんまあっても、しまうとこなくなるし。そんなんでいいなら、やる」
「でも……」
おずおずと返そうと手を伸ばそうとするが突き返された。
「んじゃお願い。それ、もらって」
受け取ってくれと言われてしまえば、それを返す方が申し訳なくて、結局もらうことにした。
「ありがとう」
それは三年間、僕のお守りとなり、今日も鞄の中に入っている。
◇◇◇
MEZZO”でデビューしてから三年経って、僕は二十三歳、環くんもとうとう二十歳になった。
相変わらずMEZZO”は超超超仲良しの看板が下されることはなく、ありがたいことに二人の仕事も絶えない。結成した頃よりもお互いにお互いのことをよく話すようになって、喧嘩もするけれど、それでも以前と比べればずいぶん減った。
環くんはまた背が伸びて、筋肉もついて、髪は少し短くカットするようになった。出会った頃の僕と同じ年齢になったのに、僕にはこんな色気は出せなかったな、なんて思い返しては笑ってしまう。
ただ、それに伴って……ではないと思うけれど、僕はいつの頃からか環くんを意識するようになった。
たれ目がちの透き通った瞳も、ぴょこんと跳ねた髪も、たくましい筋肉も大好きだ。
隣で歌う声も、ステップを踏む足音も、ライトを浴びて汗を流す笑顔も大好きだ。
少し甘さを含んだ声でそーちゃんと呼ばれるのも、王様プリンさんのぬいぐるみを抱きながらスマートフォンでアプリゲームをしている背中を見ているのも、朝なかなか起きてこない環くんを起こしに行くのも、地方で泊まり仕事の時は相変わらず赤ちゃん電気じゃないと寝られないと駄々をこねるのも、そのすべてが愛おしい。
ただ笑いかけられたこと、一緒に現場へ向かいながら朝珍しく寝ぼけたままの一織くんが歯磨き粉と洗顔料を間違えて使っていたのを目撃したと聞いたこと、移動の合間に一緒にカフェに入ってナギくんに勧められたここなちゃんの劇場版を前日に観たら出来がかなりよかったから僕にも観てほしいと言ってきたこと、レッスンで痛めた足を庇ってリハーサルをしていたら誰よりも早く気付いてスタッフさんに調節を頼んでくれていたこと、ソロでの仕事の帰りに甘すぎないコーヒーゼリーを買ってきてくれたこと、雨の日に迎えにきてくれたのに持ってきた傘は一本で、二人で一つの傘に入って帰ったこと……たぶん、他愛もないそんなひとつひとつが重なって、僕は環くんを好きになった。
決定的な何かなんてあるようでなくて、きっかけなんてものは三年間の毎日だった。
日々の中の一つ一つが宝石のように眩しくて。
昨日よりも今日、今日よりも明日、明日よりも明後日。明後日よりも一週間後、一週間後よりも一ヶ月後、一ヶ月後よりも半年後、半年後よりも一年後……日々を積み重ねれば積み重ねるほど、僕の環くんへの好きも重なっていく。春が過ぎて夏が過ぎて秋が過ぎて冬が過ぎて、また次の春が来たら、僕はきっと前の春の四倍、環くんのことが好きになっているだろう。
そんな気持ちを抱えたまま、日々膨らんでいく気持ちを隠したまま、僕は今日も現場へ向かう。隣には、あのビー玉と同じ色の瞳を湛えた環くんがいる。
春の青空を写し取ったかのような、涼やかな青色の瞳が二つ、今日もきらきらと太陽の光を浴びて輝いていた。
「そーちゃん! 新幹線来てる!!」
「分かってるよ! 早く、先に乗っ──」
「こっち持つから!」
ガタガタ鳴らしていた僕のキャリーケースをひょいと持ち上げて、環くんは先を行く。
情けない、とは思う。男として。けれど同時に、そうして環くんが手を差し伸べてくれるのは僕が僕だからだと自惚れた考えも抱くようになってしまった。それはこの三年で嫌というほど甘やかされた結果だ。甘やかしてくれる人が好きだと言う割に、彼は人を甘やかすのが抜群にうまい。残酷なほどに。
「っぶねー……」
ギリギリで新幹線に飛び乗る。今日から二泊三日、地方へロケの仕事だ。地方ロケは数ヶ月ぶりで、少し楽しみでもある。
「キャリーケース、ありがとう……はぁ…………」
息を整えながら、重たいそれを持ち上げてくれた環くんへ礼を述べると、おーと相変わらずどういう意図か分からない声が返ってくる。
どれだけ見た目が大人っぽく、男性らしくなっても環くんは環くんだった。
二日かけて撮影したロケも無事に終わり、移動用のバンで僕らは用意された宿に向かう。一日中主に屋外での撮影が二日間も続き、おまけに真夏、二人とも疲労困憊だった。これがもう半日と考えると目眩でも起こしそうだ。時刻はすでに午後五時を回っているにも関わらず、太陽は未だ燦々と照り続いている。西陽が射して、長くなった影が二つ並ぶ。
「お、」
「あ」
車へ乗り込もうとした時、僕らの間を浴衣姿の女の子が二人駆けていく。
「すみません……」
後から走ってきた母親と思しき女性が僕らにそう言って、子どもらを追おうとして──二度見された。
……まぁ、そうなりますよね。
けれどその人は軽く会釈をして、すぐに女の子たちを追いかけて行く。
「……なぁそーちゃん」
一連の流れの渦中にあった環くんは、女性を目で見送った僕に声をかけてくる。心なしか、声が弾んでいるように思う。
何を考えているかは、分かっていた。だって、
「……うん、僕も同じことを考えてた」
陽が完全に落ち切ってからいつかのように祭へと赴く。
帽子を被り、メガネをかけた環くんは昔のようにはしゃいであちこちをきょろきょろと見回したりはしない。けれど彼が浮き足立っているのは隣から嫌というほど伝わってくる。僕も、顔の半分以上が隠れるほどもあるマスクの下で頬が無意識のうちに緩んでしまうのを感じていた。
「そーちゃん、あの時のこと、もう忘れてると思ってた」
しばらく二人でのんびりと歩いたあと、ぽつりと環くんはこぼした。
「さすがに忘れられないよ。そういえば環くん、あの次の日みんなと合流した時にお祭に行ったことを話して、陸くんやナギくんにずるい! って言われてたよね」
「だって言いたくなんじゃん」
「ふふっ、君らしい」
昔のことを思い出す。毎日顔を合わせているのに思い出話なんて馬鹿みたいだけれど、こんな日くらいは馬鹿になってみるのも一興かもしれない。毎日会うからこそ、思い出話なんて滅多にしないのも事実だ。
「ラムネ、飲みてーな」
「そうだね、僕も飲もうかな」
「やめとけって」
「なんで」
「俺のやるから」
「でも」
「全部飲みきれねーだろ」
「それは……」
「ほら〜」
言葉に詰まった僕をよそに、そーちゃんの負けな、と環くんは出店のおじさんからラムネと麦茶のペットボトルを受け取って麦茶の方を僕へ手渡してきた。
人気のない場所に木のベンチを見つけて、並んで座る。
確かにラムネ一本、自分の分を買ったところで全部飲みきれる自信はなかった。でも、環くんのをもらうならそれは彼が口をつけた飲み口に僕も口をつけることになる。これは潔癖とかいう問題ではなく、僕が意識してしまうから避けたかったのだ。男同士で気にするようなことじゃない。でも、僕は環くんが好きなのだ。気にするなという方が無理な話だ。
「飲む?」
「…………いい」
「いーのかよ」
差し出された容器も、どこか色めいて見える。邪な考えが脳内を埋め尽くす。情けないし、隣の環くんへの申し訳なさでいっぱいだ。
勝手に意識されて、勝手に欲情されて。気持ち悪いことこの上ないだろう。そんなの、絶対に知られてはいけない。
「…………なに? やっぱ欲しい?」
それでも僕が不躾なほどラムネのボトルを見つめていたのは、ビー玉が入っているのか気になって仕方がなかったからだ。
その視線に気が付いたのだろう、環くんは飲むのをやめて尋ねてくる。
「ええと、それにもビー玉って入ってるのかなって」
すると環くんは残りが少なくなった容器を振る。
からりころり、中で軽いものが転がる音が鳴る。
「欲しいん?」
「できれば……」
ビー玉が欲しいなんて、小さな子どもじゃあるまいし。そう考えてしまうと自然と声が小さくなる。案の定、環くんはぷっ、と吹き出した。
「笑わなくったっていいだろう? 僕だって子どもっぽいのは分かってるよ!」
心外だ、と拗ねたふうに眉を吊り上げるが、恐らく嘘モノの演技なんてことはバレバレだ。僕だって本気ではないのを隠す気もない。
「いや、そーじゃなくて。なんつーか、かわいいなって」
「かっ……」
こういうことを言うのが僕の相方で、好きな人だ。何度言われても慣れない。
「じゃー、そんなかわいいそーちゃんには特別大サービスな」
「大サービ……んぅっ!?」
しゅわり、しゅわ。
環くんがラムネを飲んだはずなのに僕の口の中で炭酸が弾けた。口の中だけじゃなく、脳内まで甘さで溶けてしまいそうだとぼんやり考えたところで、キスされたことにようやく気が付く。
「んーっ!」
胸を叩いても離してくれない。つーっ、口の端からこぼれたのは飲みきれなかった炭酸飲料だろうか。
ようやく解放された時には息が上がってしまっていた。
「なっ、なにす──」
「俺が気付いてないと思ってたん?」
「……なに、が」
射すくめるような視線に貫かれる。口角は上がっているのに、目は笑っていない。
「そーちゃん、ウソつくの下手だし、取り繕うのも下手だし、キスも下手な。鼻で息すんの」
鋭い眼光はすぐになりを潜めて、もう僕をからかってくる。
「言わなくていいよ!」
「…………やだった?」
静かな、低い声が少し柔らかい。不安に揺れるそれは、怯えているようにも感じられた。
何を問われているのか、何を確認されているのかなんて考えずとも分かる。
「……や、じゃ……ない」
ふ、と空気が緩んだ気がした。環くんが緩めたのだと思う。
「知ってる」
「どう……」
「俺も、壮五さんのことが好き」
突然の名前呼びにどきりとする。普段は何があってもそーちゃんそーちゃんなのに、こんな時だけ、ずるい。
「壮五さんの、声で、聞かせて?」
俺も、と環くんは言った。つまり僕の気持ちはバレバレなのだろう。一体どうして? 隠せていると思っていたのに。
僕は観念した。ここで取り繕ったところで見透かされているのだ。きっとそんなことをしたって意味はない。
「…………環くんの、ことが好きです……っ!」
ぎゅっと目を瞑る。
「……目、開けて?」
恥ずかしくてなかなか目を開けられない僕の髪に環くんは優しく触れてくる。
そ、っと顎を引いて目を開けばその瞬間、額にキスを落とされる。
「ビー玉洗ってくる」
くるりと背を向けて走って行ってしまった環くんの、一瞬だけ見えた頬はりんご飴よりも提灯よりも、紅く染まっていた。
◇◇◇
「環くん」
「んー? ……って、あんた何やってんの」
ぶっと環くんは吹き出す。
「環くんの目だよ」
「は? 俺の目?」
僕は青空色のビー玉を二つ、両手の親指と人差し指で一つずつ挟んで目の前に置いて、環くんの部屋のドアを少しだけ開いてそこから覗く。視界はビー玉の青に染め上げられていて、実のところ彼が今どんな表情をしているのかは分からない。
「ほら、昔言っただろう? 君の目の色だって」
「そーいやそんなこと言ってたな」
手を下ろして、両の手の平で二つのビー玉を転がす。
「つか、そのビー玉ずっと持ってると思わなかった」
「重たい、よね」
「いや、嬉しい」
僕にとってあれは大切な思い出だし、あの日が今の僕らに繋がっているのは確かだと思う。環くんの瞳と同じ色をしているのはちょっとした付加価値で、だからこそ僕は毎日持ち歩いていたのだと思うけれど、それだけがすべてではない。でもやっぱり、その色でなければずっと持っていなかったとも思う。
「てかこれ、俺が持ってていーん?」
「君に持っていてほしいんだ」
一つを環くんの手の平へ転がす。
「ふーん?」
二つ目のビー玉を僕は一度は受け取った。でも少し考えて、やっぱり一つを環くんに渡したのだ。
「やっぱ理由教えて」
その理由を、八ヶ月経った今も僕は彼に話していない。
「……笑わない?」
「笑うよーなことなん?」
「分からないけど……」
「んじゃいーじゃん。教えて?」
環くんは僕の手をその大きな手で包み込む。甘えるような声音に、僕は白旗を揚げる。
「……二人で、一対になれたらいいなと思って。僕らがいつも一緒にいられますようにっていう、願掛けみたいなものだよ」
すると環くんはきょとんとして、少ししてからくすりと笑う。
「笑った……」
「だって、そーちゃんがバカだから」
「バカ……!?」
そのあんまりな言い草に、つい僕の眉間にシワが寄る。
「だって俺ら、ずっと一緒じゃん。二人じゃねーとなんもできねー。だから、わざわざ願掛けする必要とかねーのになって」
当たり前のように、環くんは言う。太陽が東から昇って西に沈むのと同じだと言うように。日本の季節が春から夏へ、夏から秋へ、秋から冬へ冬から春へと巡るのと同じだと言うように。
僕らは一緒だと。
「でも、そーちゃんが俺に持っててって言うんなら、俺ずっとこれ持ってる」
その甘くてたまらない言葉はあの炭酸飲料のように僕の中でしゅわりと弾ける。
ああもう。どうして僕の愛しい人はまだこんなに好きにさせるんだろう。
「壮五、環、そろそろ始めるぞー」
階下から三月さんの声が飛んでくる。今日はIDOLiSH7のメンバー全員で中庭で花見だ。
「すぐ行きます!」
返事をして、環くんの方を見やる。
「環く──」
行こう、と続けようとした言葉は彼の口の中へ吸い込まれてしまう。
「……いきなりなにするの」
「そーちゃんがかわいーから。今日まだしてなかったし」
そんなことを言う君の方がよっぽと可愛いと思うよ、という言葉は飲み込んだ。可愛い、と言われることを環くんは嫌がる。三つも歳上の男には言うくせに。
「な、そーちゃんからもちょーだい」
そんなことを言う声ははちみつを絡めたように甘くて甘くて仕方ないのに、僕はそれが大好きでたまらないのだ。
噛みついた彼の瞳は閉じられることはない。
雲ひとつない春の晴天を切り取ったような、涼やかな大好きな君の瞳と同じ色の宝物。
きらきら輝くそれを、ずっと一緒に握りしめていられますように。
出会ったあの日と同じように、薄紅色の花びらがはらり、舞い降りた。
今から夏が待ち遠しくて仕方ないよ。
fin.