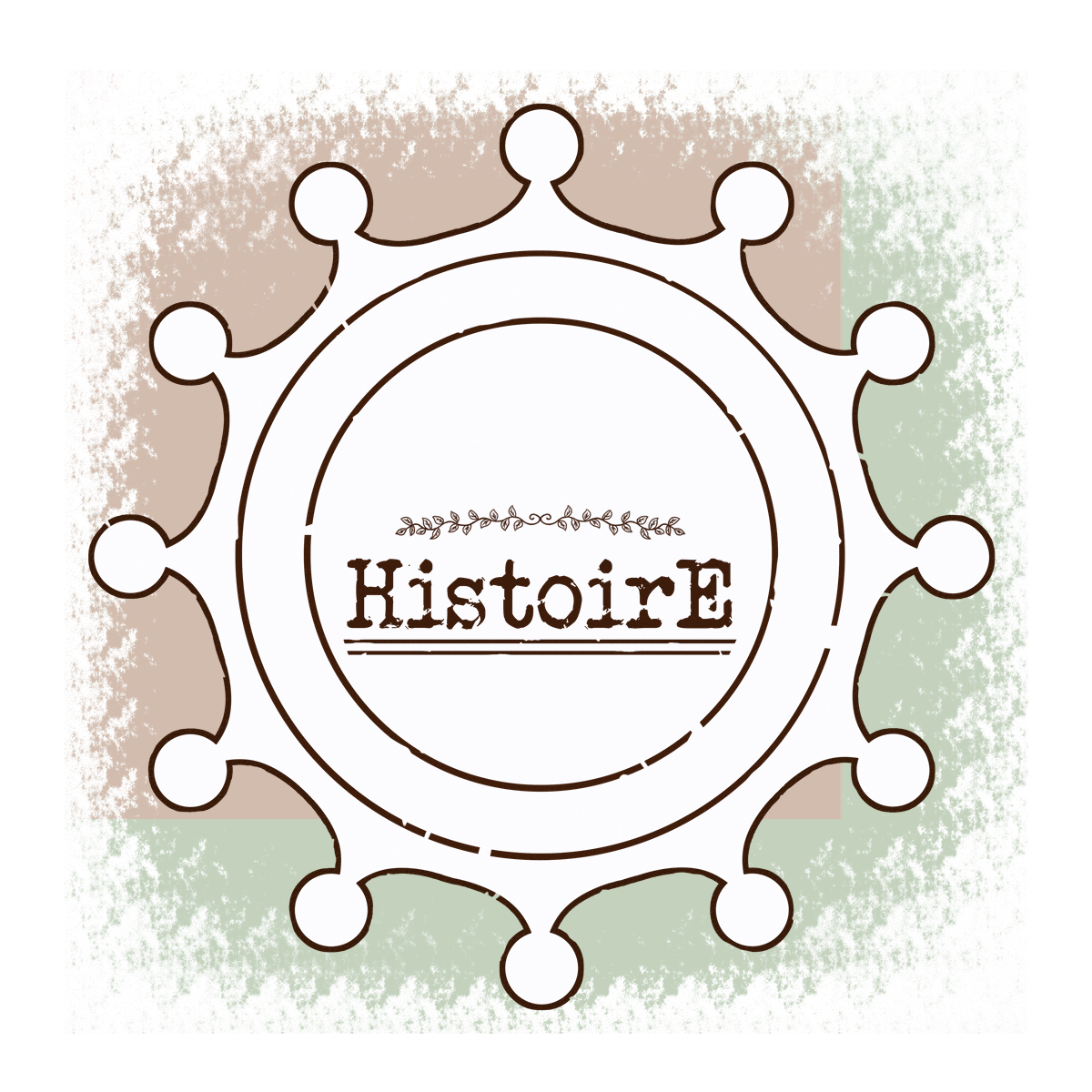とくん、とくん、とくん。
鼓動が脈打つ。それは自身のそれとは異なるが、一定のリズムで刻み続ける。
そ、と髪の上から頭に手を載せられ、滑っていく感覚があった。ティナリの手だ。一見華奢に見えるが、その実ずしりとしっかり重みのある手。
「聞こえる?」
静かで穏やかな声が部屋に響く。普段はきはきと話す時とは一変し、今のティナリの声はやや低く、しとりとしている。
セノは小さく「ああ」と答え、頷いた。それでも、ティナリの左胸に耳を押し付けたまま離れようとはしない。
今日のセノは甘えん坊だね、とティナリは笑って、セノの好きにさせる。ゆっくりと瞼を落とし、緋色の瞳がその奥に隠される。目を閉じて、ティナリの鼓動を聴くことに神経を注ぐ。
とくん、とくん、とくん。
生きている。
生を感じてセノは安心する。
ほかでもない、ティナリの命を感じて。
――セノ。
名を呼ばれて目を開ける。見上げると、ティナリもセノの瞳覗き込んでいた。
「僕にも聴かせて」
君の命を聴きたい、と。
抱き抱えられるようにティナリの膝に座っていたセノが少し身を離すと、今度はティナリがセノの左胸に大きなふわふわの耳を寄せる。人のものよりも柔らかく、体毛に覆われたそれは肌に触れると少しこそばゆい。思わずふふと笑い声を漏らすと、怪訝な顔をされた。
「聞こえるか?」
その柔らかな耳を撫でながらセノが問いかければ、ティナリは頷いた。
「聞こえる。でも正常値より少し早くない?」
激しい運動をしたわけでもないのに。と不審そうにティナリはセノの顔を覗き込んできた。
「笑ったからじゃないのか」
そんなわけないだろ、とティナリには一蹴されるが、その理由を明かすわけにはいかなかった。
恋焦がれる相手に身を寄せ、寄せられて、平気でいられるほどセノの心は凍っていない。
このまま身も心も溶け合ってしまえたらいいのに、と。柄にもなくそんなことを思いながらセノは再び瞼を下ろした。