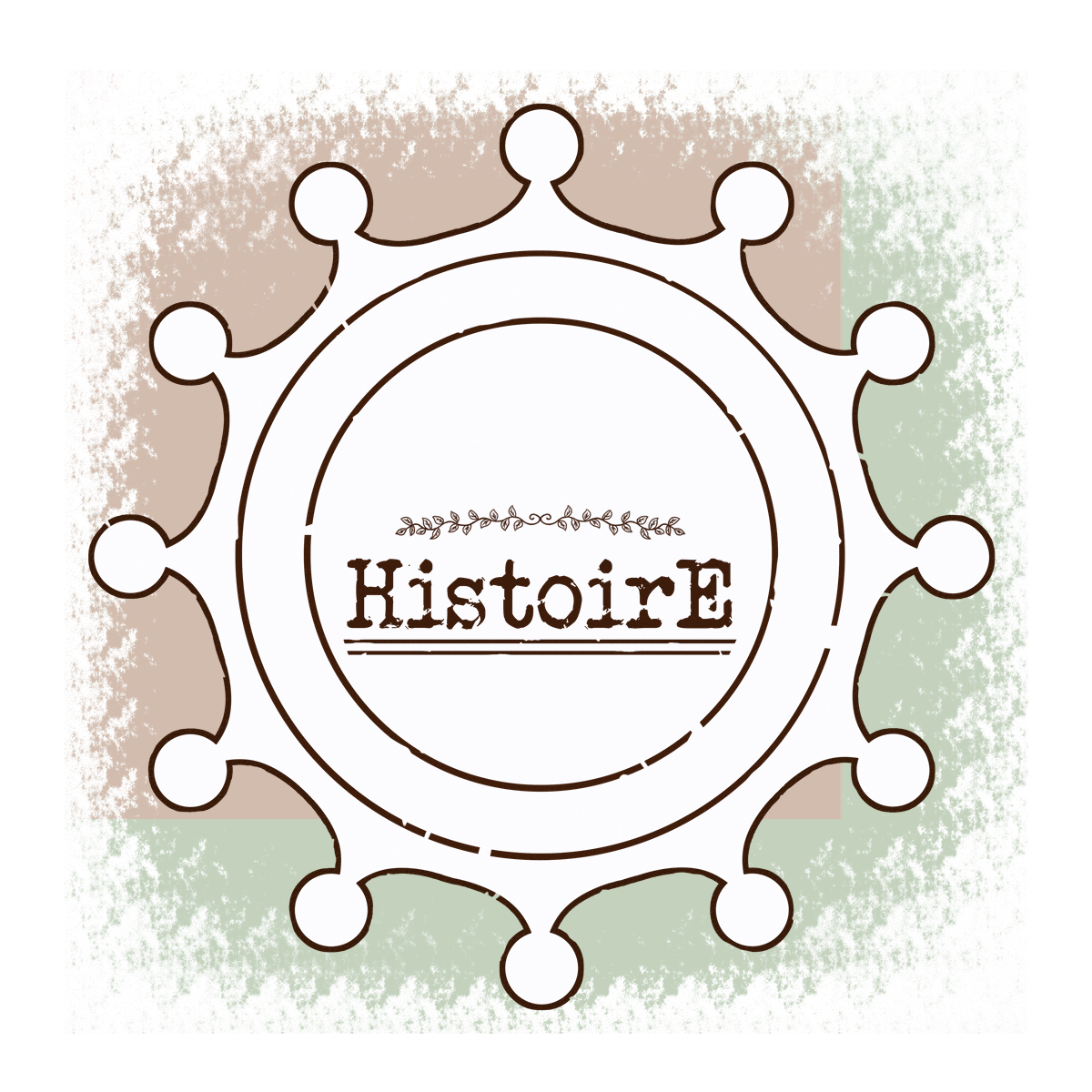きっかけがあったのかなんて、今となってはもう分からない。何事にもきっかけというものはあるだろうから、この話にもそれはどこかにあったのだと思う。だが、気が付けないような、見落としてしまうようなものなのだから、それはきっと些細なものだったのだろう。ホットケーキに添えたいちごの大きさがひとつだけ不揃いでも、複数のプレートに、種類の異なるフルーツと一緒に並べてしまえば、他の皿のいちごとの違いにはなかなか気が付けないのときっと同じだ。
それでもその眼差しは徐々に、尊敬や憧憬の色だけに留まらず特別な熱を帯びていく。
そうして、気付いた時にはもう遅かった。
オレ、モモさんのことが好きだ──
◇◇◇
運動部と称した何人かで集まっては体を動かす活動は不定期で、しかしながら集まる時はそれなりの人数が集まるものだった。
その日以外は。
「いやぁ……」
「まさか……」
『こんなに集まらないとは…………』
二人の声が重なる。思わず顔を見合わせ、揃ってぶっ、と吹き出す。
「あはははははははは!! オレたち息ピッタリだね!!」
「ありがとうございます!! ……ははははは!!」
いつも通り、モモの声掛けにより集まる……予定だった運動部だが、本日はモモと三月の二人だけとなった。都内の公共施設をいくつかローテーションを組んで借りており、今日もそのうちの一つに集まるはずだったのだが壁沿いで笑い転げる二人のほかには誰もいない。
「どうする? せっかくだから身体動かして帰りたいよね」
ひとしきり爆笑したのち、モモはこの後を問うてくる。その提案には大賛成だが、問題は、繰り返しになるがこの場に二人しかいないということなのだ。
「そうですねぇ。二人で出来ること……あ、バスケの1 on 1とかどうですか?」
「お! いいね!! モモちゃん賛成!!」
グッと親指を立ててウインクするその姿が決まっている。さすがトップアイドルRe:valeのモモだ。
「じゃあボール出してきます!」
「ありがと三月!」
追いかけてくる声に一度くるりと振り返り、頭の上で大きくマルを作って飛び跳ねる。手を振ってくれるモモに笑顔を返してから、また倉庫へ向かって走った。
あの笑顔が今この瞬間は自分だけに向けられたものだと考えるだけで胸が高鳴る。随分と重症だな、なんて思って自嘲気味に笑ったのをモモは知らない。
バラエティでのモモの立ち回りが自分の役回りにとって勉強になることが多いと気が付いた三月は、自身はバラエティ番組の中でどう振る舞うべきなのかを学ぶべく、自然と目でモモを追うようになった。時にはRe:valeの冠番組を見学させてもらったりもしていたし、見学に行けなかった時やRe:valeがゲストとして出演したバラエティは録画して見ていた。
きっと誰よりもモモのことを見つめていた。ユキにも匹敵するかもしれない、なんて少し調子づいたことも思ったりした。それでもそれはあくまでIDOLiSH7のためで、仕事のためで、勉強のためで……
だがいつしか、モモを目で追うことが目的になっていた。見学のためと口では言いながら、三月の心の中には明らかな下心があった。それでも、自分でそれに気付かないフリをした。あるいは思い過ごしだと、勘違いだと、思い込もうとしていたのかもしれない。
だって、怖かったのだ。
少しずつ変化していくその感情に自分自身、ついていけなかった。どうしてそんな気持ちを抱くに至ったのか。いつから? そんなことばかり考えて、頭の中がぐちゃぐちゃになって、だけど明確な答えは出なくて。それでも日々、モモへの気持ちは膨らむ一方だった。
だから諦めて、それを認めてしまうことにした。
和泉三月はモモが好きだ、と。
先輩への憧れとかアイドルである彼へのライクではなく、それははっきりと確立された恋愛感情であり、アイドルのモモではなく、モモという一人の男へ抱いた感情だった。
もちろん、それは絶対に誰にも言うつもりもない。アイドルだから、男だから、先輩だから……理由はいくらでも思いつくが、何よりモモが三月に対して同じ感情を抱くことがないことを分かっていたから。
モモにはユキがいる。それが例え三月がモモに抱くものと同じ感情ではないとしても、きっと三月はユキ以上にはなれない。
──いや、Re:vale以上になれない。
焦がれて、ずっとずっと見てきたからこそ分かる。モモがRe:valeという存在を、居場所を、どれほど大切にしているか。モモにとってのRe:vale以上の存在になるのはきっと容易なことではない。
勝ち目のない戦に手は出さない。……などと言えるならカッコもついたのだろうか。言ってもカッコ悪い気がするけど。
キュッ、キュッ──
屋内用の運動靴が床に擦れて甲高い音が鳴る。まるで鳥のさえずりみたいだ。
今ボールの所有権はモモにある。モモは右手でドリブルをしながら、左手は三月の動きを制するように緩く肘を折って手のひらを三月の体へ向けている。
「ッ……!」
硬直状態を脱するべく、三月は足を少し出して軽くフェイントをかけるが、モモは釣られない。
それなら、と今度は大きく踏み込む。身を屈め、手を精一杯伸ばし──
「あっ……」
その先のボールに届く筈だった自身の手は宙を彷徨い、視界が傾く。
「わっ!」
次の瞬間、ドシン! という音が鳴って、倒れたのだということを認識する。あれ? でもどこも痛くない……
ダム、ダム……と重量感のあるボールが跳ねる音が遠く、早くなっていくのを聞きながら目を開けると、目の前には見覚えのある黒のスウェット生地。
「ひたたた……危なかったね〜三月。大丈夫? どこも怪我してない?」
頭のすぐ上から声がした。息がかかるほどの至近距離から聞こえる憧れの人の声。頭を包む温かな体温。何より耳に響くとくん、とくんという鼓動。
それらを合わせれば、モモが倒れる三月を抱き止めてくれたらしく、更に言えば顔面から床に激突する筈だったところを身を呈して庇ってくれたであろうという答えに行き当たるのは容易だった。
カァッ、と顔に血液が集まるのを感じる。耳から、恐らく首の根元までその一帯がよく熟れたいちごのように真っ赤に染まっていることだろう。羞恥と、情けないのと、申し訳なさと、好きなひとに密着している緊張とパニック。それが更に恥ずかしさを呼んできて、あとはそれの無限ループだ。
「……ぅ…………っ」
抑えようとしても、歯止めはきかなかった。
「え……」
こぼれた雫はモモのスウェットシャツにより一層黒いシミを作っていく。
「どこか痛かった!? 顔は守れたけどほかに……あ、膝とか」
「ち、ぢがうんでず……!」
涙でぐちゃぐちゃになった顔、ぐずぐずの涙声。アイドルらしさどころか男らしさすらかけらもない、情けない涙に濡れた姿を晒す。
「どこも、痛くない、でず」
起き上がると、三月はモモの上へ馬乗りの姿勢になってしまう。
「じゃあ──」
こぼれた涙と共に、蓋をしていたはずの感情が溢れ出す。
「お、っ、おれっ……!」
ドミノ倒しが一斉に倒れていくように、堰き止められていたダムの水が川へと流れ出すように、それを押しとどめていたものは脆くも崩れ去り、そして決壊した。
「モモさんの、ことがっ……好ぎ、なんでずっ……!!」
ぽろぽろと、大きな瞳から溢れるのは大きな涙の粒。それはまるで雨のようで、モモは頬で受け止めた。
「……そっ、か…………」
ぼんやりとした、感情の読めない表情で。静かで穏やかな、凪いだ海のような優しい、けれどどこか悲しそうな声で。フランボワーズ色の彼の瞳には、ビー玉のような涙をぼろぼろと落とし続ける三月が映っていた。
「っ……す、すみまぜん……迷惑ですよね、気持ぢ悪いですよね」
止めようとしても、そう考えれば考えるほどむしろ泉のように涙は湧き出してくる。
「そんなことないよ」
普段の彼の声とは違う、低くて、柔らかくて、でもどこか無機質なそれが三月の瞳を揺らす。ゆっくりと、右手が三月の頬へ伸びてくる。
「だけど、ごめん。俺は、三月の気持ちには応えられないよ」
しかしその指は頬に触れることなく宙で揺れる。
分かっていた。思った通り。想像していたそのままの言葉に、わずかに安心さえしている自分がいる。
「へへ……知って、っまし、た」
それでもなお感情はぐちゃぐちゃで、滑稽な自分を笑い飛ばしたいはずなのに涙はとめどなく溢れてくる。しゃくりあげながらハの字に下げた眉は果たしてモモの瞳にどう映ったのだろう。泣いている? 笑っている? それともそのどちらでもない?
「ありがとう」
モモへ向けた好意に対してか、モモの返答を受け入れたことに対してか。その心は本人だけが知るところだが、告げられた返礼は三月の胸へ染み込んでいく。
でも、自惚れているわけではないけれど、これだけは言えるような気がした。モモは相手が三月でなければこんな顔はしなかっただろうし、こんな声でそんな礼の言葉を口にしないだろう、と。
あ、オレ、失恋したんだ。
その瞬間、ようやくそれを自覚した。不思議と、どこも痛みはしなかった。
◇◇◇
最近ミツの雰囲気が変わった。
しばらく前からRe:valeとの仕事の時やRe:valeが出ている番組を見ている時苦しそうにしていたのを見て、またユキさんが要らぬことを吹き込んだんじゃないかって疑ったけれど、どうやらミツの様子がおかしいのはモモさんが原因らしかった。
とはいえ、本人に確認をしたわけではないから確実なことは何も分からない。
分かっているのはモモさんを見る目が少し熱っぽかったことと、先週、運動部から帰ってきた時からそれが消えていることだけだ。
ほとんど分かってるみたいなモンなのは、あいつが分かりやす過ぎるのが悪いのだ。ちっとばかし俺が察しがよ過ぎるのは何も関係ない。たぶん。
その日は久しぶりに七人揃って夕飯を食べた後、子どもらが風呂に入ったり、自室に戻って映画鑑賞会を始めた頃、たまたま洗い物をしていたミツとビールを煽る俺だけがリビングに残っていた。
……ちょっとだけ、聞いてみるか?
一応年長者だし? なんかリーダーとか呼ばれてるし?
「……なあミツ」
「んー?」
ソファに座ったまま、キッチンの方へ顔だけ向ける。
「あのーさ……最近、何かあった?」
ピクリ、一瞬だがミツは動きを止めた。
「なんで?」
ないんでもないふうを装って聞き返してくるけど、残念ながらお兄さんにはもうお見通しだわ。
「いやなんか、雰囲気変わったなって」
すると一瞬の間が空いて、ミツはふ、と息を吐いた。張り詰めていた糸が緩んだような、氷が溶け出していくような緩さを持っている。
「やっぱ、すごいなぁ大和さん」
ミツの口が動くが、水道の水が落ちる音で聞き取れない。
「オレさ、失恋した!」
さっきまでの空気は何処へやら。声を張り上げて宣言するように、ライブの時や俺たちを鼓舞してくれる時みたいに明るい声で言う。ビリリと空気が割れたような気がした。無理してんのか、それこそ自分で自分に気合いを入れるためなのか。
どうしたもんやら、何か言った方がいいのか? 頭の中でぐるぐる考えてたら洗い物を終えたらしいミツが隣へ座る。
あ。
その顔は、強がってるわけでもなければ、悲しみに暮れているようでもなかった。ライブの後みたいな、スッキリした爽快な顔。
こんな吹っ切れた顔したやつに慰めとか要らねーな。
「いい恋だったんだな」
その言葉は自然と言葉になった。
少しびっくりしたように、面食らったみたいに、ミツはもともと大きな瞳をめいっぱい見開く。
でもそれは一瞬だけで、次の瞬間にはニカッと歯を見せていつものあのひまわりみたいな笑顔になる。
「おう!」
それがあんまり眩しくて、こっちがちょっと、切なくなった。
「やっぱおまえさん、めっちゃかっこいいわ」
「惚れんなよ〜?」
それはきっと恋だった
to be continued…?