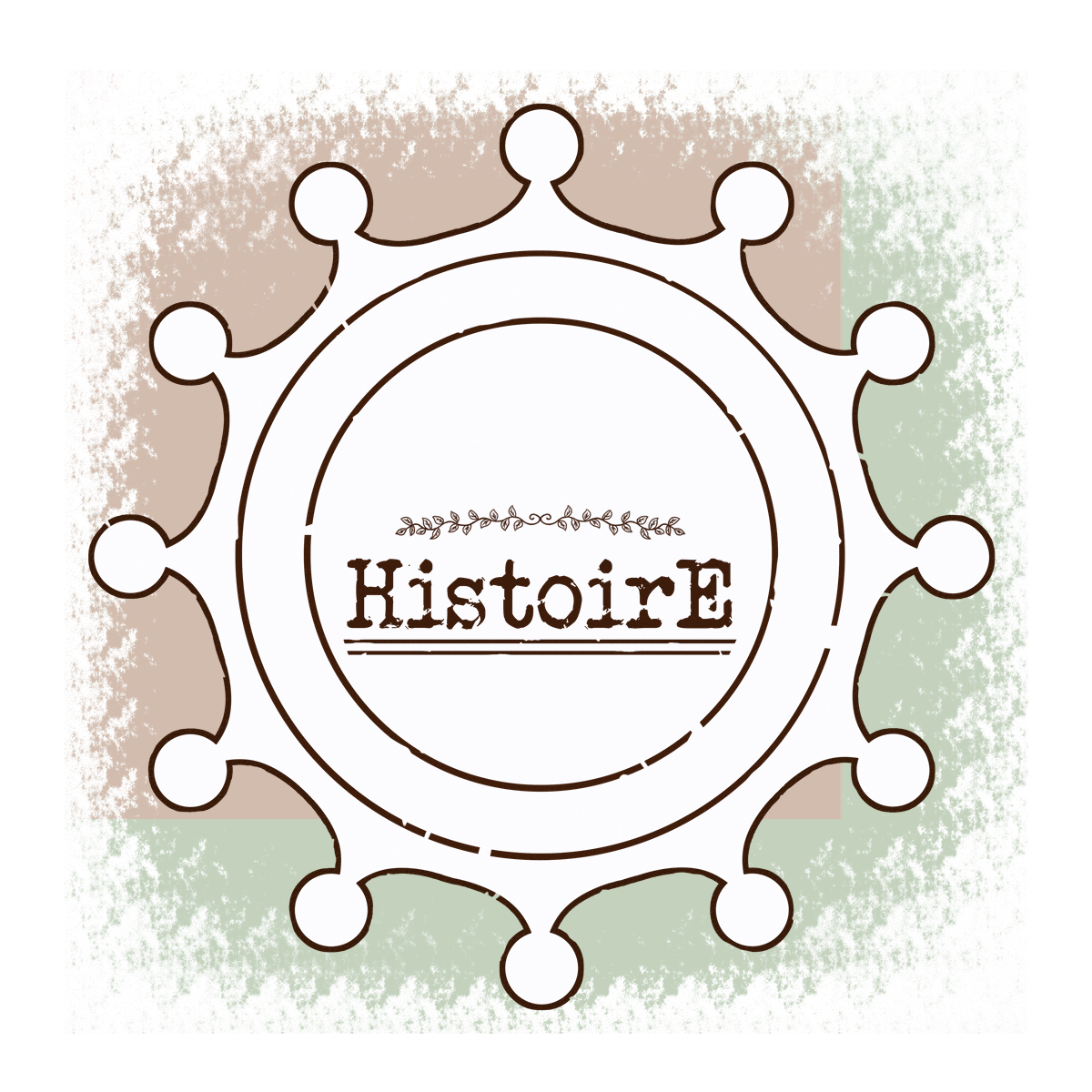環が寮に笹がやってきたと知ったのは壮五からのラビチャだった。
その日、環は一織と共に登校しており、昼休みにスマホの画面を点けると壮五から『寮に七夕用の笹が来ました』というメッセージと共に加工も何も施されていない写真が送られていた。背景から察するに、笹は中庭に設置されたのだろう。
そういえばそんな時期か。確かに最近あった番組収録の現場でもそういう内容のやり取りがあったし、IDOLiSH7の冠番組でも七夕関連の企画があると聞いていたように思う。環はそういうイベント事はどちらかといえば好きな方だから忘れることは少ないのだが、近頃は仕事のスケジュールがやや詰まっていたのと、学校では期末試験が近づいていることから珍しく頭から抜けていた。
『帰ったら一緒に飾りつけしよー』
メッセージを送信し、席を立つ。今日は大和も三月も朝早くから仕事でいないため、購買でパンを買うことになっていた。壮五がオフなので弁当を作ると申し出てくれたが、せっかくの休みに早起きさせるのは悪いと思ったし、何より弁当箱の中が赤くなりそうな予感がしたので丁重に断った。たぶん、丁重だったはずだ。
「なーいおりん」
購買でパンを購入し、釣り銭を受け取りながら隣の一織に声をかける。
「何ですか?」
「いおりんは短冊に何書くん?」
すると一織は「はい?」と聞き返してくる。
「いっつも悩むんだよなー七夕の短冊って何書きゃいーの?」
「知りませんよ」
うんざりしたように一織は眉をひそめて言う。
「じゃーいおりんは何書くの?」
そこではじめの質問に戻る。それは参考にするためでもあったが、このパーフェクトな同い年のメンバーが何を願うのか、純粋に興味が湧いたからでもある。
「言いません」
しかし一織は口を割ろうとはしない。が、そもそも一織も短冊に願い事を書くのだということに環はまず意外性を感じた。
「てかいおりんも七夕の願い事とかすんのな」
「あなたが言ったんでしょう!?」
「わりーわりー」
素直に感想を述べると、教室へ戻る道すがら、廊下のど真ん中で一織が珍しく大声を出した。
「……まぁ、四葉さんなら何かしらあるんじゃないですか? 妹さんと一緒に暮らせますようにとか」
コホンと咳払いをした一織の言葉には説得力があった。なるほど。確かに去年も理のことを書いた気がする。あの時は「理に会えますように」と書いたはずだ。一応、その願いは叶ったということになる。
「そっか。やっぱすげーないおりん」
現状、どうすれば理と一緒に暮らせるのかなど環には皆目見当もつかない。しかしながら、まずはあの九条という男を倒さねば……とメラメラ闘争心を燃やし始めたところで教室に到着した。
突然だが、環は壮五のことが好きだ。
それは相方とか、グループのメンバーとか、友情とか、そういう意味での好きではなく、手を繋ぎたいなとか、抱きしめたいなとか、キスしたいなとか、セックスしたいなとか、そういう意味での好きだ。
そう気がついたのは最近のことだが、環の中にはもうずっと前からあった感情だったようで、自覚してしまえばそれはすとんと胸に落ちた。なるほど、そういうことだったのかと、特に驚くこともなく納得してしまった。
短冊に何を書くか悩んだのには、そのことが関係していた。
理のことは今でも変わらず大切だと思っている。たった一人の家族。たった一人の妹。ずっと探していた。やっと会えた。それなのにどういうわけか一緒には暮らせないと言う。納得などできるはずもない。だが理自身が、今はあの九条という男のそばにいることを選んでいる。環は九条のことを「なんかやばいやつ」と感じてはいるが、今のところ生活に不自由していないらしいのも事実なのだ。何より、不服だが法律上とはいえ今は天が理の兄であり、九条一人に任せるのだけは絶対にありえないが天がいるのならもう少しだけ考えてやってもいいかもしれないと考えている。
それなら環は──兄としては失格かもしれないが――壮五が欲しいと思ってしまったのだ。
そーちゃんも同じ気持ちだったらいいな。そーじゃないなら好きになってくれねーかな。
◇
「ただいまー」
「ただいま戻りました」
一織と仲良く揃って寮へ帰宅すると、壮五が出迎えてくれた。
「二人ともおかえり。暑かっただろう? お茶淹れようか?」
冷蔵庫を開きながら壮五が聞いてくれるので、揃って頷き、ダイニングテーブルに着く。
「ありがとうございます」
「あんがと」
グラスに詰み上げられた氷が注がれた麦茶に溶かされていく。
三人分のそれを置いて、壮五もダイニングに着く。
「うめー」
「今日は逢坂さんお一人だったんですか?」
一織は麦茶を半分ほど飲んだところで壮五へ問いかけた。
「うん。大和さんと三月さんは朝出たっきりまだ戻ってないよ。さっき撮影が終わったって連絡があったから夕飯までには帰ってくるんじゃないかな? ナギくんもモデルの撮影で午前中に出て、帰りに少し寄るところがあるって言ってたよ。陸くんはお昼過ぎに買い物に出てからまだ帰ってきてないし」
「じゃー笹来た時はりっくんと一緒に入れたん?」
環は壮五からのメッセージ送信時間を思い出して問う。確か午前中に送られてきていたはずだ。
「うん。陸くんすごく嬉しそうで、どんな飾り付けしようかってすごく盛り上がっていたんだよ。あっ、二人も短冊にお願い書くかい?」
にこにこと話す壮五を見ていると、陸がどれだけはしゃいでいたのかが伝わってくるようだ。壮五自身も少なからずそわそわしているようで、いつもよりやや口数が多い。
「そーちゃんはもう書いたん?」
「書いたよ」
「えっ? まじかよ! 何書いたん?」
「え……なんでそんなに慌ててるんだ?」
「わたしは明日の準備があるので今日はご遠慮します。逢坂さん、麦茶ご馳走さまでした」
「あ、うん。お粗末さまでした」
席を立ち、グラスをシンクの中に置いて自室へ戻って行く一織を見送る。
「環くん、短冊とペン、ここに置いておくから書くなら書いて吊るしておいで」
そう言って壮五も立ち上がる。
「そーちゃんは?」
「夕飯の用意をするよ」
「そーじゃなくて」
「?」
言い方がまずかった、というか恐らく言葉が足りなかったのだろう。
「そーちゃんの短冊も吊るしてある?」
「え? 吊るしたけど……って、環くん?」
言い直すと壮五が頷いたので、環はガタリと立ち上がる。
「見てくる!」
壮五が背後で何か言った気がするが、環の耳には入らない。靴に履き替え、中庭へ回るとすぐに笹が目に入った。
「なんだ、もうそこそこ飾り付いてんじゃん」
陸が喜んでいたと壮五が言っていたし、もしかしたら出かける前に陸が少し飾り付けたのかもしれない。折り紙や色画用紙で作られた七色の飾りが風に揺れている。その中に一枚だけ、紫色をした細長い紙が揺れている。
笹に近づき、そっとそれを手に取ると裏を向いているのか、そこには何も書いていない。
裏返すと、見慣れた壮五の筆跡が並んでいた。
「──っ!?」
しかし環はその文字の羅列を見た瞬間、カッと頭に血が昇るのを感じた。
何考えてんだあいつ!!
文句の一つでも言ってやらないと気が済まない。どうしていつも、いつもいつも、自分を殺すのか。どうして自分を優先しないのか。
俺は自分のためにあんたと理を天秤にかけてしまうような男なのに。
「──チッ」
舌打ちをしてリビングへ戻る。ドカドカと足音を鳴らして、バン! と扉を乱暴に開けて。
「ちょっと環くん、乱暴にしたら扉が壊れ──ッ」
「あんた何考えてんだよ!!」
壮五の注意など聞いていられない。そのままキッチンへ入り、振り返った彼に向かって吼えた。
「何考えて、って……何のこと?」
「短冊に決まってんだろ! ほかに何があんだよ!」
「そんな言い方しなくたっていいだろう? 何をそんなに怒っているんだ!」
壮五にも火がついたようで、声を荒げた。いや、これは叱るときの彼の口調だ。その言い方にも環は苛立ち、更に声のボリュームが上がる。
「何って……なんであんなこと書くんだよ!!」
「は? あんなことって……君のことだろう!? そんな言い方する必要ないだろう!」
「あんたが自分の願い事書かねーからだろ!!」
「へっ……?」
環の言葉を壮五は予想していなかったようで、急に勢いを失って固まってしまった。
「そーちゃんなんで自分のこと書かねーの!? 別にただの七夕だろ! そんなら、そん時くらい自分の願い書けよ!! 誰も怒ったりしねーよ!」
誰にだって神様やお地蔵様に縋りたい時くらいある。織姫と彦星に願うのも同じ心理だろう。自分の力だけじゃどうにもできないことをそうやって、見えない何かに責任を押しつけることで心に余裕を持ちたいのだ。信じたいのだ。それは自分のせいじゃないと思い込みたいのだ。
それならその逆だって許されるはずだ。願いを持つことくらい初めから自由だが、今まで壮五はきっとそれが許されなかった。けれど責任が生まれない時くらい、今くらい何を願ったっていいはずだ。身も世も関係なく何を望んだっていいはずだ。それなのに、どうしてこの人は人の幸せを願う?
どうして人の願いを自分の願いに勝手に変換してしまえる?
「そーちゃん、欲しいもんとかねーの? やりたいことは? TRIGGERのライブのチケット取れてんの? そもそも行ける時間ある?」
「ちょ、環くん!?」
「そーゆーちっせーことでもいいんだから自分のこと書けよ!……よし分かった」
言葉を紡ぐ最中、環はあることを閃いた。
「そーちゃんに俺の願い事取られたから、俺がそーちゃんの願い事書く。その方が織姫と彦星も叶えやすいだろ。何書く?」
「待って! 環くん待って!!」
矢継ぎ早に環がまくし立てる。そのスピードに追いつけないのか、壮五は両手を前に突き出して待てのポーズをとる。
「んだよ」
それで環の言葉の銃撃は少し落ち着いたが当然待つ気などさらさらない。ストップをかけられたことが不服で、声のトーンがやや下がる。
「なんでそんなに……」
その言葉が引き金になった。
もう、限界だった。
こんな風に言うつもりはなかった。もっとちゃんと壮五にこちらを見てもらえるようになってから、もっとちゃんと準備をして、もっとちゃんと考え抜いた言葉で伝えるつもりだった。
環が壮五のことを第一に考える理由なんて、ひとつしかない。
「なんで? 決まってんじゃん。そーちゃんのことが好きだから」
言葉にしたら実感が湧いて、みるみるうちに顔から火が出そうになった。熱い。クーラーつけてるよな?
「…………は?」
壮五の反応は鈍い。というより恐らく理解していない。
「まっ……待って。好き、って……!」
だが環の表情を見て察したのだろう。壮五は耳まで赤くなったあと、白くなる。それが答えだと言わんばかりに。
「……あの、ね、環くん。何言ってるか、意味が分かって──」
「分かってっし! ついでにあんたが困んのも分かってて言ったし、そーちゃんが俺のことそーゆーふうに想ってないのも分かってる。でも……俺は、そーちゃんが大大大好きだよ」
言葉を重ねているうち、だんだん環は落ち着いてきた。心臓は相変わらず大太鼓のように体の中で響くし、耳までりんごのように赤いけれど、それでも環の声は穏やかだった。
「っ……!」
あれ? と思った。壮五の反応が少し変だ。なんか、思ってたのと違う。
まさかとは思いつつ、わずかな可能性がキラリと光った気がした。
もしかして──
「……そーちゃん、俺、自惚れていーん?」
「ちがっ……そうじゃないっ! そうじゃないし……そもそも僕らはアイドルで、男で、相方で……!」
「あーもー分かった分かった」
きっと壮五はまた余計なことを考えている。その上で自分の好きなものを認めようとしないのだ、たぶん。
いいのに。気持ちを自覚してから確かに壮五が今口走ったようなことを悩んだ。壮五の分まで環が悩んだ。男同士だし。アイドルだし。デュオの相方だし。それでも結論は変わらなかったのだ。
「言っとくけど、そーちゃんがそれ認めてくんねーんなら、それって俺のこと否定してんのと一緒なんだかんな」
「そんなつもりは……!」
「だから、さ──」
環はテーブルに残されたままのサインペンに手を伸ばす。水色の短冊に並んでいく不恰好な文字。
それが環の願いであるし、それでそ
ーちゃんが自分の気持
ちを認められるのならと思う。
やや恥ずかしさはあるが、ほかのメ
ンバーに見つからなければ問題ない。だ
が念のため、もう一枚書いて
おきたい気もしなくはない。そうす
ればこの短冊が誰か
の目に触れる機会が減るかもしれないから。
こんなにわくわくするのははじめてのこ
とだ。環は壮五のことが
すきで、壮五も環のことが恐らくす
きで。例えば壮五がそれをすぐに言
ってくれなく
ても、それを願う事ができるのはこれまでの
いつより幸せだ。あとは壮五が言
えるように、た
まきが頑張るだけなのだから。それだけで
すべてが頑張れる。世界中が輝いて見える。
よ
うやく、伝えられたんだから。次は絶対
に、壮五にも好きだって言わせてやる。
「ッ……!」
書き終えるや、環はガタリと立ち上がり、来た道をまた戻る。壮五が息を飲んだのには気付かないフリをして背を向けた。
だって、楽しいのだ。壮五が環のことでどきどきしてくれていると思うとたまらない。
「あ、」
だが少しだけ意地悪をしたくなって振り返る。
きっと今、俺すげー悪い顔してる。
「そーちゃんも一緒行く?」
手を差し出す。きっと握り返してはくれないだろうから、数秒だけ待って手を引こうとした。
「なーんてな。別に──」
環は手を引こうとした。絶対にだ。だから壮五の手が重なるなんて思いもしなかった。
「……あんた、言ってることとやってることちげーの分かってる?」
壮五は固まったまま動かない。そんな反応すら愛しくてたまらないのは、惚れた弱みというやつだろうか。
「ま、いーや。ほら、行こ」
手を引くと、壮五は存外素直に着いてくる。
やっぱどう考えたって好きじゃん。俺のこと。
あ、そっか。
気が付いた。
壮五も環のことが好きだから、きっとあんなことを書いたのだ。
笹の前で立ち止まり、壮五の短冊をもう一度手に取る。
『環くんが理ちゃんと一緒に暮らせますように』
お世辞にも綺麗とは言えない男性らしい文字で書かれたその願いは、よく考えずとも壮五が環のことを精一杯考えてくれた証拠だった。
お互い様、なんだろうな。
二人揃って、相手のことしか考えていない。だからケンカしたのだ。考えてみればなんて幸せで愚かなんだろう。少しおかしくなる。
「そーちゃん、ありがとな」
「え……?」
環の言葉が突然だったのか、壮五は顔を上げた。
「そーちゃん、俺のこと考えてこれ書いてくれたんだよな。そこまで俺考えらんないで頭カッてなって、めっちゃ怒った。あんな言い方して、ごめん」
「環くん……」
ふるふると双葉が揺れる。
「僕の方こそごめんね。勝手なことを書いたよね。それに、君が僕のことを考えて言ってくれた言葉も、否定するような態度を取ってしまった」
環の手を握る力が少し強くなる。
「いーよ。そーちゃんが俺の願い事、叶えてくれんなら」
「ええと……」
どうしてこの歳上の相方は、からかいたくなるほどこんなにも可愛いのだろう。
「じょーだんだって」
種明かしすれば壮五は勘弁してくれと顔を手で覆う。覆いきれていない耳がバラ色に染まるのを見て、環は満足する。
「ぜ、善処させていただきます……」
その小さな声は星空に吸い込まれていった。