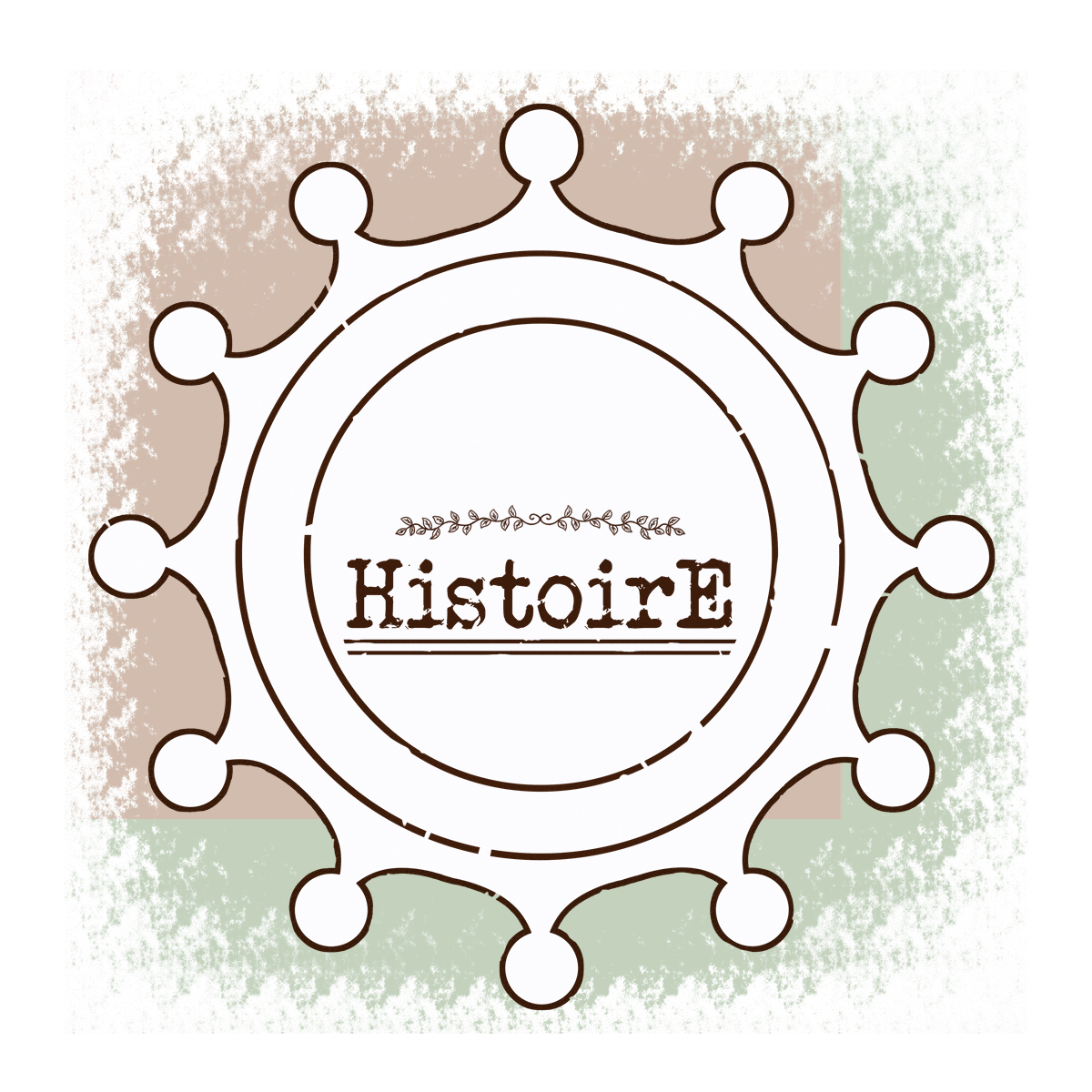最近、ティナリは世にも奇妙な経験をしている。
教令院の学生学者が恐れるマハマトラ、その頂点に立つ大マハマトラと交友を深めていることだ。
大マハマトラは学生たちに論文の相談を受けたり写真撮影に誘われたりしているティナリを、徒党を組み学術を腐敗させようと目論んでいるのではないかと怪しんで、長い間監視していた。もちろんティナリにそのような気はまったくなく、大マハマトラの杞憂だったのだが。疑いが晴れ、大マハマトラがティナリを信頼に足る人物だと認め、ティナリに事情を明かしてくれたことであの監視生活は終わりを告げた。
はずだった。
いや、終わりを告げたのは事実だ。だがそれ以来、なぜかティナリは大マハマトラとの交流が増えていった。教令院の中で、スメールシティの街中で、時にはフィールドワークに出た森の中で鉢合わせることまであった。
もしかしたらこれまでもティナリが意識していなかっただけで、こうやって彼とはあちこちですれ違っていたのかもしれない。教令院の学生である以上、ティナリにとっても大マハマトラは知らぬ存在ではない。だが、だからといって過度に怯える必要もなければ、そもそも自分が関わる相手になる可能性など考慮していなかったのだ。あの監視生活さえなければ。それが知らぬ間柄でもないのだからと、顔を見れば挨拶を交わす仲になり、そのうち他愛もない会話をするようになった。どちらからともなく、互いにだ。
そうして話すようになって、大マハマトラは案外話しやすい相手で、七聖召喚なるカードゲームを趣味に持つという、その役職と彼の眼光の鋭さ故の恐ろしさからは想像もできない一面まで知るようになった。自分と同じように血の通った人間であることも知ったし、謎のジョーク――これは周りの空気を和ませようとして編み出した方法だそうだが、ティナリにとっては和むどころかむしろ悪化するのではないかと思うものばかりだった――を披露されたこともある。表情の変化こそ乏しいが、彼にも感情は確かにあるし、それを殺して生きているわけでもない。マハマトラとしての職務にあたる時の彼のことは分からないが、少なくともティナリと一緒にいる時の彼からはむしろ親しみやすさすら感じた。
それがティナリにとっては興味の対象であり、同時に彼のことを好ましく思い始めたきっかけでもある。
簡単に言えば「面白いな」と思ったのだ。
■■■
「セノでいい」
「え?」
大マハマトラとの会話が増えてきた頃、彼は徐にそう言い出した。それが何を指しているのか、ティナリは咄嗟に分からなかった。
「俺の名前だ。おまえはいつも大マハマトラと呼ぶが、言いづらいだろう」
そこで一瞬言葉を切った彼は、少しだけ煮え切らない口調でそれに、と続ける。
「……それに、おまえとはマハマトラとして会っているわけじゃないからな」
そう言葉を紡ぐ彼の表情からは僅かな照れが見て取れた。
え、なにその顔。
彼の名前は当然聞いたことがあったが、まさかその名を自分が本人に向かって呼びかけることになるなんて、誰が想像できただろうか。少なくとも、ティナリは自分にそんな日が来るとは露ほども思っていなかった。おまけに言い出した本人は今、目の前で恥じらうような態度だ。脳の処理が追いつかない。
だが、確かに彼の言うことはもっともだった。「大マハマトラ」は正直なところ彼の言う通り少し言いづらいしやや長い。それにティナリとて、彼がマハマトラとして自分と会話しているとは考えていなかった。もっと言えば、ティナリは彼を知人の枠に収めるには些か無理があると感じる程度には親しくなっていると思っていたし、これから先、距離を置くという選択肢もなかった。ならば、彼を役職で呼ぶのもおかしな話だ。
それなら、と納得したティナリは頷く。
「分かった。じゃあ……」
――セノ。
その名前は独特の響きを持っていた。自分の口から出て、空気中を伝って彼の耳に届く。
彼の――セノの朱い瞳が一瞬、煌めいたように見えた。
「……あぁ」
嬉しそうに、セノの声は弾んでいた。もしも本人が否定したってティナリには分かる。だってこの大きな耳が拾った声なのだから。
「なんだか嬉しそうだね」
そんなセノの反応が何だか可笑しくて、こちらまで笑ってしまう。同時に、そんなに嬉しそうにされると照れてしまう。
「そう、だろうか……?」
だがどうやら本人にはその自覚がないようで、少し驚いたような顔で首を傾けた。
「そうだよ。ふふっ、ちょっと照れちゃうな」
でも、悪くない。
ただ一度名前を呼んだだけだ。これから先、何度も呼ぶことになるだろうとティナリは何となく感じていた。だが頭のどこかで、最初のこの響きは忘れられそうにないな、とも思っていた。
セノ。そう呼ぶことを許され、求められた名前。そのことに僅かな優越感と喜びを感じる。
悪くない、そう思えるほどには。
芽生えかけた感情に、ティナリはまだ気づかない。