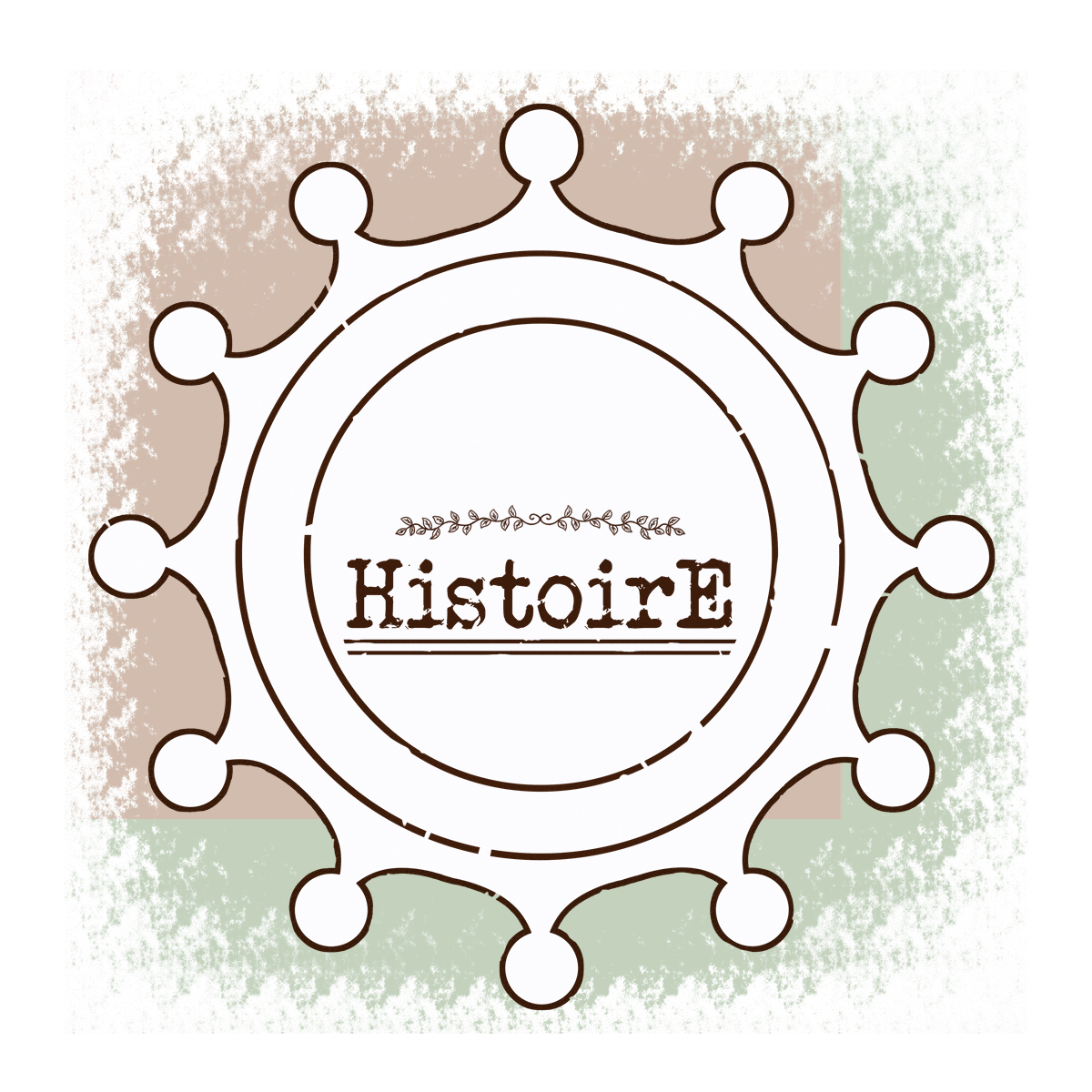その日、壮五はひまわり畑の中にいた。隣には相方の環。三百六十度を自分の身長よりも環の身長よりも高い、太陽を写し取ったような花に囲まれている。昨日は地方でレギュラーのロケがあり、そのまま現地で宿泊となった。今日は東京へ戻るためにと用意された移動日だが、仕事が入っていないため実質的にはオフだ。せっかくならどこかへ寄ってから帰りたいなと思っていたところへ、このフラワーパークのひまわり畑が有名だと情報を得た環が声をかけてきた。もちろん二つ返事で了承し、東京へと戻る前に二人でやってきたという次第だ。
「そーちゃん見て! どれも俺よりでけー。ナギっちよりもでかいんじゃね? ひまわりってこんなでかくなんだな!!」
はしゃぐ相方を見て壮五は自然と口角が上がる。
あぁ、好きだなあ。
その感情が果たしてどのような類のものなのか、正直なところ壮五自身も分からない。環のことは好きだ。だがそれが友情や仲間意識かと問われれば少し違う。かといって恋愛感情なのかと聞かれても恐らく首肯くことはできないだろう。ラブかライクか、そのどちらでもないこの気持ちを、壮五はひとまずディアと呼ぶことにした。親愛。それがこの想いに最も近い言葉なのだと。
「そーちゃんほら、周り全部ひまわり! 空しか見えねー! はははは!!」
くるくると回る環の笑顔は満開の花のようだ。ひまわりがよく似合う。環の空色の髪と瞳が眩しく反射して、壮五は目が眩んでしまいそうだ。
日焼けしないようにと壮五はパーカーを羽織っているが、ジリジリと照りつける太陽を思えば正しい判断だと思う。対する環は日焼けもお構いなしの半袖で、そのたくましい二の腕を惜しげもなくさらけ出している。壮五もそうだが環も元々色が白いため、そのことも相まって眩しさが増す。日焼けが少々心配だが。
「あまり回って転ばないようにね。ほかの人にも当たらないように周りを見るんだよ!」
一応声をかけてみるが、環の耳に入っているかは疑問だ。それほど環は楽しそうだったし、壮五自身の声もいつものような尖りはなかった。むしろ、どちらかといえば楽しげに弾んでいる。
「ここさ、ひまわり切り売り? してんだって。一本から買えるんだってさ」
一面のひまわり畑でひとしきりはしゃいだ後、環は売店に向かいながら得意げに言う。植えられた花を切ったり持ち帰ったりするのは禁止されているが、売店で販売されているものは一輪から購入して持ち帰ることができるらしい。そういえば壮五もホームページの案内でそのような文章を読んだ気がする。
「じゃあ寮にも買って帰ろうか。玄関やリビングに飾ったら綺麗だよね」
「おー! めっちゃいい! あ、でもその前に俺、そーちゃんにあげたい」
後頭部に手をやりながら、環は前を見つめている。視線の先には話に出ている売店の生花売り場。
「そーちゃん、ひまわり似合うから」
数歩前に飛び出して、環は振り返って壮五の瞳を覗き込む。悪戯っぽく笑うその表情の奥に、真剣な炎が灯るのを壮五は見逃さなかった。
「おばちゃん、ひまわり十一本ちょーだい」
「十一?」
環の言葉に壮五は首をかしげる。売店の老婦人が用意をしてくれている間、環は財布を取り出しながら答える。
「みんなの部屋に一本ずつ置いてくれっといいな〜ってのと、玄関に一本、リビング一本、事務所一本と、これからそーちゃんにあげるので、合わせて十一」
「ま、待ってくれ。それだと僕だけ二本になっちゃうよ」
「え? あ、そっか。まぁいーんじゃね?」
「いや、よくな」
「あ、おばちゃん、一本だけ短めに切ってくれる?」
壮五の言葉に耳を貸さないで環がまた婦人に声をかけると、はいよと笑って、婦人は花用のハサミをカシャンと動かす。
「いーから、もらっといて」
振り返りもせず環は静かに、だがノーとは言わせない空気を纏わせて言うものだから、それ以上壮五も拒否できなかった。
「わかったよ」
「へへっ、あんがと」
振り返った環は、それは嬉しそうに笑っている。肩越しのその笑顔は、陽射しを受けて咲き誇るひまわりすらも霞んでしまいそうなほど眩しい。
「こないだSNSで流れてきたんだけど、ひまわりって本数で花言葉変わるんだって」
再びひまわり畑の中へ向かいながら環はそんな話をする。
「そうなんだ。バラの花が本数や色によって変わるのは有名だけど、ひまわりもなんだね」
「バラのやつってどんなの?」
「たしか花を九十九本にして、そこへ彼女を加えて百パーセントの愛、だったかな? 昔観た映画に毎日バラの花を持ってくるけどフラれ続けて、百日目に受け取ってもらえる……そんな感じの話があった気がする」
「え、百日間毎日バラの花届けんの? すげー」「かなり前に観たから僕も記憶が曖昧だけど、そうだったと思う」
「まじかよ…………」
環が手で顔を覆ってなにかぶつぶつと呟いている。負けた……と聞こえたような気もするが、なににおいてどう負けたのか分からない上、本当にそう言ったのかも分からなかったため追求はしなかった。
「…………や、まあいーや。俺ひまわりだし」
最終的にはそのよく分からない発言をしたが、上げた顔があまりにも爽やかで清々しいものだったため、壮五はなにも言うまいと黙っていた。そんなことよりもその環の横顔を見て、サイダーの炭酸がパチリと弾けたような感覚を覚えたから。
「で、さ」
陽が傾き始め、人が少し減ったひまわり畑の真ん中で。環は壮五の方へと向き直る。纏う空気が先ほどまでと違うことに気がついた時にはもう環の手が壮五の髪に伸びていた。サラサラと流れる前髪を撫ぜて、耳の横へと移動する。
その瞳に囚われて逃げられない――
「俺、さ。IDOLiSH7で最初に会ったのって、そーちゃんだし、そーちゃんも俺だと思うんだけど」
うん。
「初めて見た時、そーちゃんのこときれーな人だなって思って」
うん。「今思ったら最初っからそーだったんかなって思う。あんな、一本のひまわりの花言葉はな――」
ビニールの袋から短めにカットしてもらったひまわりの花を取り出し、壮五の髪に挿す。
――ひとめぼれ。
「え…………」
見上げた空色の瞳は、一度囚われたらもう放してはくれなかった。視線を外すこともできず、ただその熱を見つめることしかできない。二人の間に射し込む西陽も、昼間のジリジリと照りつけるような太陽も今の環の瞳の熱には敵わないだろう。
「あの、さ。俺………………そーちゃんが、好き、だよ」
いつも通りの不器用な言葉で、けれどあまりにも真っ直ぐなその「好き」はじんわりと壮五の中を満たしていく。パチパチと弾けるサイダーに、鼓動が呼応する。
パーカーのフードを被せられ、引き寄せられる。あっ、と思った時には遅かった。
「んっ……」
唇に触れたそれはあまりにも熱い。なにが起きているのか理解した時にはもう環の唇は離れていたが、数秒間の記憶が飛んでいた。だがそれを嫌だと思う気持ちは不思議と湧き上がることはなく、ふよふよとした意識のまま、勝手に口元へと手が動く。
「た、ま……きく…………?」
「ちょっ…………!? そーちゃんそれやめて!」
顔を真っ赤に染めた環が壮五の手首を掴む。
「へ……?」
「へ、じゃないから! なんでそんな……なぞ、ったり、すんの…………めっちゃはずいじゃん…………」
瞳に幕を張りながら、環はもう一方の手をぶんぶん振る。
「…………嫌じゃ、ねーの?」
ややあって、環はうつむき加減で問うてくる。長い前髪の隙間から覗く瞳は不安に揺れていた。
「……うん。嫌じゃない。驚いたけど……自分でも不思議だけど、嫌じゃないよ。むしろ嬉しかった」
言葉にすることで、壮五自身も確認することができた。
親愛だと思っていた……いや、思い込もうとしていたこの気持ちは、どうやらそうではなかったらしい。これまで幾度も否定し続けてきたのに、突然降りつけてきた恋のシャワーには成すすべもなく、それを認めざるを得ない。
自分でも知らなかった壮五自身の気持ちに気づかせてくれるのは、いつだって隣にいる環だ。だから、たまにはその気持ちを口にしてみるのもいいかもしれないと思ったのだ。
だって、君には言わなきゃ分からないんだろう?
「僕も、環くんが好きです」
めいっぱいの愛をこめて。