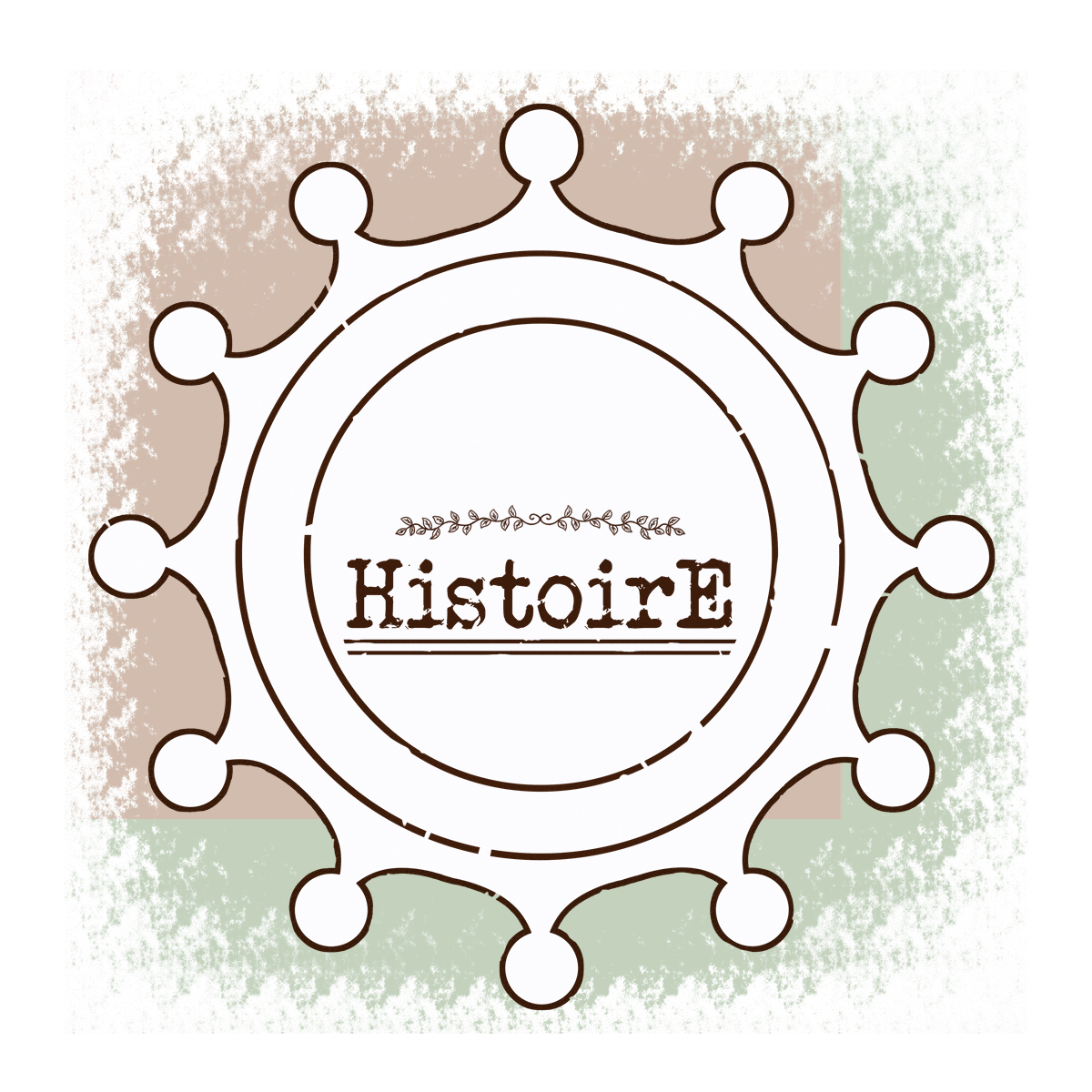どうしてそうなったのか、皆目見当もつかないけれど。
きっと、なるべくしてなったのだろうということだけは分かる。
運命だったというのなら、たとえ魔法使いであろうとそう容易く変えられるものではないのだから。
✧✧
オーエンがカインを見つけたのは中央の市場にふらりと立ち寄った時だった。
人の心を魔力源とするオーエンは、市場をマナエリアとしている。特定の市場でなくともそれはある程度有効に働いてくれる。だからあちこちの町で、ふらりと市場を覗くことはよくある。そのうちの一つで、赤みがかったココアブラウンの髪と蜂蜜色の瞳を持つ男を見つけた。
ふわりと魔法の匂いがして、振り返ったところに、彼はいた。特段強くはないけれど、弱くてどうしようもないという程でもない。オーエンの手にかかれば赤子の手を捻るよりも容易く殺すことはできるだろうが、別に気にするような相手でもないなと背を向けた。わざわざ手にかけてやる程の相手ではない。そう、思っていた。この時までは。
「カイン騎士団長!」
ざわざわと人の話し声がひしめく中にいても、その声はいっとう強くオーエンの意識を引いた。
騎士――。
その言葉は猛烈にオーエンを惹きつける。反射的にカイン騎士団長と呼ばれた男を探していた。
「どうした?」
そして名を呼ばれて返事をしていたのが――先程の魔法使いの男だった。
騎士団長ということは中央の国の騎士団を率いているのだろう。人間の政治に興味はないが、そういえば新しく中央の騎士団長になった男はまだ若く、二十いくかいかないか程の歳だと耳にしたことがあった。
もし目の前の男がそうなのだとしたら合点がいく。魔法使いであることは確実だ。見た目が二十程で止まっている可能性も捨てきれないが、感じる魔力の強さや揺れ方から推察するに、恐らく実際にその程度しか生きていないのだろう。
中央の騎士団は人間の騎士集団のはずだ。中央には魔法科学兵団が別に組織されているし、なにより魔法使いに排他的な体制をとっていたはず。騎士団に魔法使いを入れるとは考えられない。王子が魔法使いであるのに、ほとほと呆れたものだ。
しかし、つまりこの男は魔法使いでありながら、魔法を使わずに騎士団の団長になったということだろうか。
にたり、と無意識に口端が吊り上がる。まるで新しいおもちゃを見つけた時のような高揚感が、オーエンの胸を支配していた。先程まで無関心だったはずの騎士団長――カインのことが知りたくてたまらない。
カインにしてみれば、この時オーエンに興味を持たれてしまったことが最も運が悪かったことだと言えるだろうが。
おもちゃを見つけたついでに、少しからかってやろうと思った。だがどうやらカインが魔法使いであることを騎士団の者は知らないらしい。それを知ったオーエンは、隠し事をして国に仕えるカインを滑稽だと、一人嗤い、同時に激しい憤りを感じた。まるで大切にしていたものを汚された時のように。おまえが魔法使いだと、国中のやつらに教えてやればいいよと。おまえは自らの手で騎士というものを地に堕としたのだと言ってやりたかった。
人間は魔法使いを嘘つき呼ばわりする。そのことをオーエンは今更何とも思わないが、魔法使いの間では根強い人間との溝として、共通意識の根底にある。そのことをカインも分かっているだろうに、あの男はあろうことか城に仕える身でありながら嘘をついているのだ。馬鹿みたい。騎士団だなんだと正義を振りかざしておきながら、自分が一番そこから外れているじゃないか。
騎士団にちょっかいをかけて、そしてそのついでにその太陽のような目玉を、自分の、西でとれるルージュベリー色の目玉と交換してやった。カインにオーエンの目の色はまったく似合わなくて、また一人で嘲笑ってやったのを憶えている。
ほどなくして、国を欺いていたと騎士団を追われたカインが、何の因果か賢者の魔法使いとして召喚され、魔法舎にやってきた時にオーエンと再会する。
「ねえ騎士様」
「なんだ」
時は流れ、厄災に十人の仲間を奪われ、また新たな賢者と魔法使いが魔法舎に集った後のこと。
「いつになったら勝負を挑んでくれるの?」
「……またその話か」
カインはうんざりだと言うように、形の良い眉をひそめて振り返る。魔法舎の中庭でトレーニングをしているカインに、ふらりと姿を現したオーエンが早く目を奪い返してみせろと言い寄ってくるのはもはや日常と化している。実際、ある夜に部屋まで押しかけてきて以来、毎日のように声をかけてくるオーエンに、カインはうんざりしていた。
「うるさい。ねえ、今すぐやってよ」
何かあったのか、誰かに何か言われたのか知らないが、付き纏われるカインにとってはいい迷惑だ。
「やらない」
「どうして」
「今の俺はまだ、おまえに勝てない」
「知らないよ、そんなの」
問答を繰り返しても繰り返してもキリがない。今日で何日目だ?
「とにかくやらないからな」
一体なんだってこんなことに気を揉まなければいけないんだと辟易しながら、カインはぴしゃりと言い捨ててトレーニングを切り上げた。
「この意気地なし」
「なんとでも言え」
背中を追いかけてくる声にひらひらと手の甲を振って見せて建物の中に引っ込む。
まったく、なんだってんだ。
北の魔法使いはすぐに実力行使に持ち込もうとする。実戦が己の力を高めるのに何より有効なのはカインも騎士団時代に身をもって知っていることだが、今ここで争うのはわけが違う。どれだけ反りが合わない相手であろうと、憎い相手であろうと、自分たちは〈大いなる厄災〉と戦う仲間なのだ。こんなところで戦っていたずらに仲間を減らすようなことは、少なくともカインにはできない。そもそもオーエンは分かっているのだろうか。奪い返せと言うが、カインが目を取り返すというのはつまりオーエンがカインに敗れることを意味する。それとも返り討ちにするつもりなのだろうか。もしそういう魂胆なら、やはりカインはまだ挑むわけにはいかない。負けるつもりで戦うなんて、あってはならないから。
「分からない……」
あいつは一体、何を考えているんだ。
その日、カインはオズの爪痕近くの町に任務で向かうことになっていた。
なんてことはない、簡単な任務。自分のことではないのでオーエンは詳しい内容までは憶えていないけれど、とにかく先程中庭で別れた相手が、鬱陶しいほどの大きな声で今日の任務がどうだとか、朝食の席で話していた。
昼前に中央の魔法使い達が出かけて行ったのを横目に、やることもないオーエンは魔法舎の裏手の森で木にもたれてうたた寝をしていた。その時だった。
パキン――
「え……?」
聞き慣れた石の音が響いた。地面を見れば、草の上に小さなマナ石が転がって、そして自分の頬を何かが伝っていた。
何か、なんて。生温かくてどろりとしているこの感覚はよく知っている。いやという程、他人のも自分のも見てきた。――血だ。
「なんで……」
なんで。だなんて、そんなこと。分かりきっているはずなのに、どういうわけか間抜けな言葉しか出てこない。
分かっているのはこの左目の本来の持ち主――カインが死んだということだけだ。
「……オ……、ン…………オ……エン……!」
どれくらい時間が経ったのか。眠っていたらしく、名前を呼ばれたような気がして目を覚ますと、そこには賢者がいた。顔を動かすと乾いた血が皮膚の上でパリパリと割れるのが分かる。
「オーエン! その目、どうしたんですか!? それにこのマナ石は……」
問われて現実に引き戻される。そうだった。
「……カインが死んだ」
「…………え……?」
顔を引きつらせた賢者は何もおかしなことはないのに笑うみたいな顔をしていた。それがおかしくてどうしようもなくて、それなのにいつもみたいな笑いはこみ上げてこなかった。
「見て分からない? 僕の左目に嵌ってたのはカインの目だよ。それが石になったんだからあいつが死んだに決まってるでしょ」
言葉には苛立ちが滲んでいた。こんなことをわざわざ僕に言わせるなよ。そうは思えても、自分が苛立っていることには気がつけない。
「どうして……」
「そんなの僕が知ったことじゃないよ」
立ち上がって、石を拾い上げる。
「……何の用?」
「……オーエンは、平気なんですか?」
質問には答えず、別の問を投げかけてくる賢者にまた苛立ちながら、オーエンはなにが、と問い返した。
「カインが、その……」
「死んだこと?」
躊躇いがちに、それでもこくんとうなずく賢者の瞳は揺れていた。恐らくその目には涙が浮かんでいるのだろう。知ったことじゃない、僕に意見を求めるな。そう思いながらも最近よく起こるように心が不思議に動くのを感じた。こういう時はいつも不本意なのに何かしなくてはいけない気持ちにさせられる。それがまた不愉快なのに、そうしなければ後悔するような気がして、結局応えてしまう。その繰り返し。
「……別に。人間や魔法使いと死に別れることに、今更いちいち何か感じたりしないよ」
「そんな……仲間じゃないですか」
「そんなの、ここにいる間の話でしょう。だいたい、ミスラなんかしょっちゅう僕のこと殺してるじゃないか。僕が死なないのをいいことにさ」
そう言ってやれば賢者は黙り込む。返す言葉がないのか、口を結んでまた泣きそうなのを必死に堪えている表情になる。馬鹿みたい、と心の中でつぶやく。
「…………まあ」
風が吹いて、木が揺れる。ざぁっと葉が音を立てて、木漏れ日がオーエンの頬の上で踊る。手の中のマナ石に視線を落とすと、光を受けてきらめいて、目が眩しい。
「似合わない僕の目が嵌まった騎士様の顔、もう拝めないのは残念だけどね」
任務先から帰ってきた中央の魔法使いたちから、カインのマナ石が賢者に渡された。彼らから語られた事の顛末はこうだった。
討伐の任務は滞りなく終わり、帰路につこうという段になって事は起きた。
「助けて!!」
子どもの声が正面から響いてくる。涙まじりになりながらも、必死に助けを求める声。
「ノアを助けて!!」
助けてという言葉に誰より反応するのはいつもカインとアーサーだ。
「どうしたんだ!?」
姿の見えない子どもにカインは声をかける。
「おまえは昼間の……!」
呼び止めた少年を見とめたアーサーが言い漏らしたのをカインは聞き逃さなかった。
「昼間の……もう一人か?」
「ああ……」
昼間、町に立ち寄った際にカインは子どもとぶつかっている。二人組だったようで、今目の前にいるはずの子どもの姿がカインに見えないということは、彼が助けてほしいと言うノアが、ぶつかった子どもだろう。
「何があったんだ?」
「っ、川に……落ちて……!」
「っ!」
「カイン!!」
「待て」
気づいた時にはもう身体が動いていた。リケとオズの声が重なって背中を追いかけてくるが、もう止まることはできない。
「ぶつかった子どもなら俺にも見える! そいつを頼んだ!」
誰もが、その背中をまた見れるものだと思っていた。
「……私たちが川辺に到着した時、子どもがこの石を抱いて泣いていました。「助けてくれた目の色が違うお兄ちゃんが突然消えちゃった。代わりにこれを持ってた」と」
「目の色が違う……」
アーサーの言葉を受けて誰かがつぶやいた。誰でもよかった。
差し出されたマナ石をよく見ると丸い球体が埋まっている。琥珀の中に虫が閉じ込められているのと同じように。
「これって……」
「オーエンの目だ」
オズの言葉に、珍しくその場に同席していたオーエンが動く。
「へぇ……」
白い外套を靡かせながら、コツ、コツと靴音を鳴らして歩み寄ってくる。
「こんな姿になっちゃったの、騎士様。ほーんと……似合わないね」
次の瞬間、パッと目の前から消えたオーエンと共に、いつの間にかマナ石もなくなっていた。
誰も――ミスラやブラッドリーでさえ、オーエンを探そうとはしなかった。カインのマナ石を食べたところで何の得にもならないと考えているのかもしれないけれど。賢者も、オーエンを探そうとは思わなかった。目の前で自分の目玉が埋まったマナ石を見つめるオーエンの、伏せられたまつ毛の下の表情と、似合わないと吐き捨てた声が頭から離れないままだったから。
✧✧
カインがいなくなったところで、世界にも魔法舎にも朝はやってくる。
「……最悪」
双子が部屋に乗り込んできて目覚めたオーエンはつぶやいた。
「これ、朝から最悪とは何じゃ」
「これ、我らが親切に起こしてやったというのに」
「うるさい。いいから出てって」
スノウとホワイトはやれやれと顔を見合わせて部屋を後にする。
オーエンはカインのマナ石と自らの左目から落ちた小さなマナ石を食べることなく、部屋の棚にまるで飾るように寄り添わせて載せていた。窓から差し込む朝の陽射しが石に反射して、天井にプリズムを映し出している。
「……馬鹿みたい」
食べなかったのはただの気まぐれだ。夕陽に翳した石があんまり綺麗で、こんなに綺麗な石なら少しぐらい眺めているのもいいかもしれないと思っただけ。マナ石を目の前にこんなのは自分らしくないと分かっている。気が変わったらいつでも食べてやるつもりだ。だけど、それまでは――
僕の目をそうやって抱え込んでる騎士様のこと、見ていさせなよ。
――eques mendax.
ほんと、つまらなくて最悪な気分。