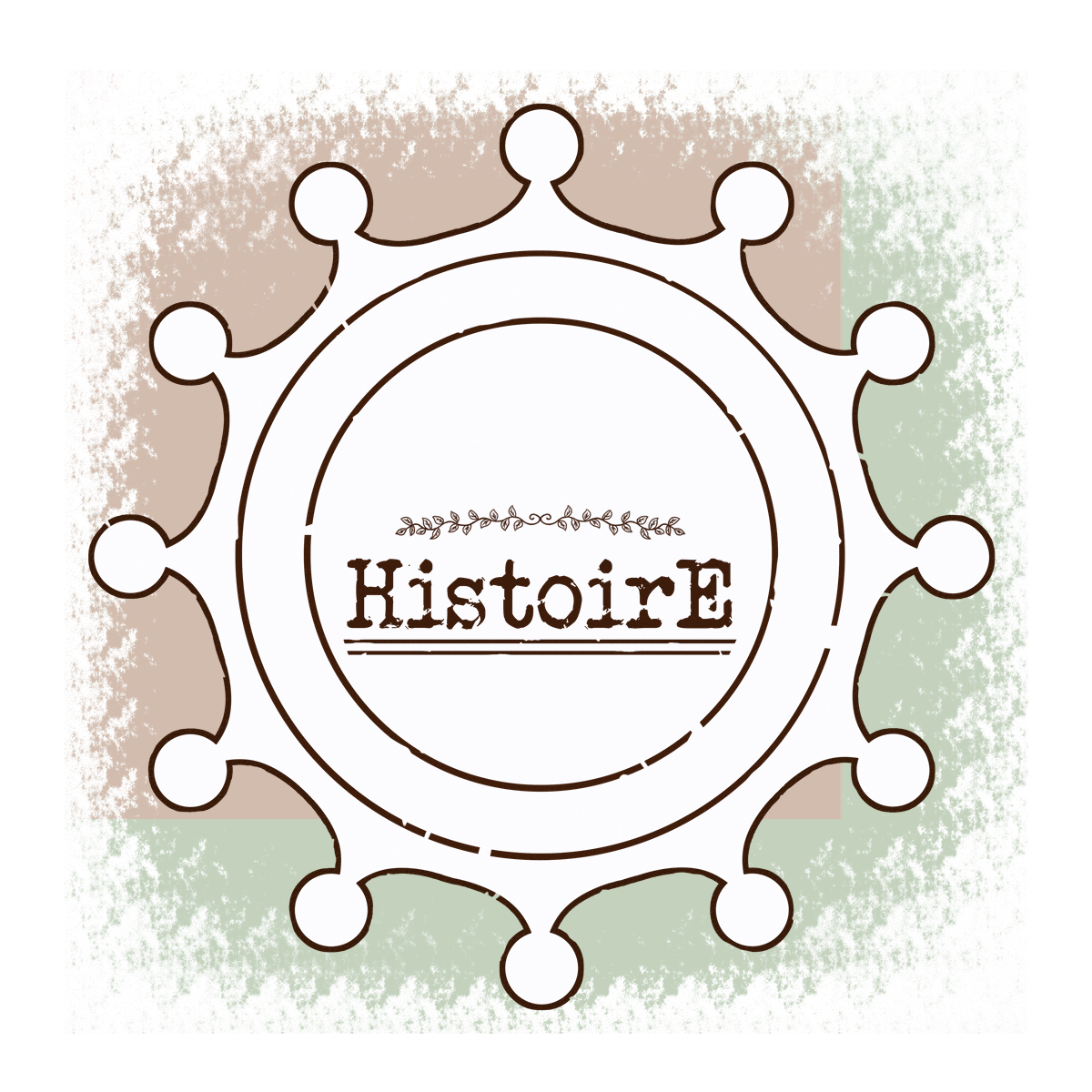「ホタル見に行きたい」
環がそう言い出したのは歌番組の収録が終わった夕方十六時前のこと。今まさに梅雨に入ろうかという時期で、瑞々しい紫陽花が咲き乱れる六月の半ばだ。
収録はIDOLiSH7ではなくMEZZO”のもので、他のメンバーも今日は各々ソロであったりペアで仕事だったはずだ。
「今日これで仕事終わりだし、ちょっと寄り道して帰ろ」
楽屋で帰り支度を整えながら環はそんなことを言うが、そもそもこの大都会にホタルなど飛ぶのだろうか。
疑念が顔に出ていたのか、壮五を見て環は少し得意げに笑う。
「いーとこ、あんだ」
壮五の返事も待たず環は寄り道を決めてしまったようで、彼はそそくさと万理に電話をかけ、迎えはいらないと伝えてしまった。
いつもとは違う電車に乗り換えて数駅。閑静な住宅街を抜けた先に小さな川が流れていた。
「こんな所があったんだね……」
川が流れていたことやその静けさに驚きと感動が入り混じり、壮五はただシンプルにすごいと呟いていた。
「こないだ撮影の帰りになんか歩きたくなって、このへん歩いてた。そしたらみっけた」
撮影終わりにフラフラと歩くのは褒められたことではない。道に迷いでもしたらどうするんだとか、トラブルに巻き込まれたらどうするんだとか、環に言いたいことを壮五はこの瞬間にも軽く十は思いつく。けれど今だけは、それを言ってこの空気を壊してしまうことの方が惜しかった。ガラスのように澄んだ、透明な空気。けれど決して冷ややかではなく、持ちすぎた熱を少しずつ冷やしていってくれるように優しくて。穏やかで少し肌寒い風が二人の間を吹き抜けて、環の長い横髪を撫ぜた。
「今日はホタルいねーのかなぁ……」
川沿いの植え込みに足をかけて、川面を覗き込む環の背をじっと見つめる。
平凡だ、と壮五は心の中で呟いた。そう、平凡なのだ。ゆったりと流れる時間は、目の前を流れる川よりも緩やかで。子どもの頃のどんな夏休みよりも心休まるのを感じた。
付近に居を構える住民にとってはきっと何気ない日常の風景なのだろうが、壮五にとってはこの一瞬一瞬が非日常だ。それが愛おしくてたまらない。
「……なにわらってんの?」
環の声に、壮五は現実に引き戻される。声の主はこちらを振り返って首を傾げていた。
「わら、ってたかな?」
「なんか、公園とかで遊んでるちっせー子ども見守ってるかーちゃんみてーな笑い方してた」
分かるような分からないような例えを出され、今度は壮五が首を傾げる番だった。
「俺、そんなガキっぽい?」
壮五が答える前に続けた環の言葉には、少しの不安と、拗ねたような音が混ざっていた。
そんなつもりで環を見つめていたわけではない。たしかに日常の中で彼を可愛らしいと感じる瞬間は度々ある。それは王様プリンをスプーンで掬っている瞬間だったり、映画やテレビ番組を見て笑っている瞬間だったり、一織に課題をやれと言われてむくれている時だったりと様々だ。今こうして拗ねた環のことも、本人に言えばまた怒るだろうから口には出さないが可愛らしいなと思ってしまった。
しかしそれとは対照的に、仕事中には大人びた表情を覗かせるし、それこそ大人すら顔負けの色気を放つ瞬間が度々ある。壮五はそんな環を見ては決まってドキッとしてしまうのだから、おちおち子ども扱いなどしていられない。何より環には妹がいる。本当はとても優しくて面倒見がいい、兄らしい側面があることを壮五は間近で見ていたし、何より身をもって知っていた。
いずれにせよ、環のことをむやみに子ども扱いしているわけではないし、そんなつもりもないが、環がそれを感じ取ることができていないのならば壮五の態度に問題がある可能性も大いにある。
「……確かに環くんを見ていて、微笑ましいな、可愛らしいなと思うことはあるよ。だけどそれ以上に、僕は君に助けられてるし、これからも……歳上としては情けないけれど、君に助けてもらう場面が出てくると思うんだ。そのことを純粋に頼もしく思うし、誇らしい気持ちにもなるよ。でも……もし僕の言動が君のプライドを傷付けてしまっているのなら、謝るよ。ごめんなさい」
壮五は言葉を慎重に選んだつもりだったが、環相手では逆効果だったかもしれないと、そこまで言い切ってから気付いた。環の首が徐々に傾いていったからだ。長々と言葉を並べ立てても、彼には伝わらないことの方が多い。シンプルに、簡単に、短く……環に理解してもらうにはそれが一番なのに。
「……つまりそれ、どゆこと?」
「つまりええと……環くんのことを子ども扱いしているつもりはないよ、ってことかな」
そう端的に答えれば環が嬉しそうに笑うものだから、なんだかこちらまで嬉しくなってしまう。同時に、少しだけ心臓が跳ねた気がした。
環が笑ってくれることが壮五は嬉しかった。環を一番大事だと言った気持ちに嘘はない。
「あ」
「へ?」
声を上げた環につられ、壮五は素っ頓狂な声を出してしまう。
「ホタル飛んでる。あそこ、ほらそーちゃん見て」
環が片手で川面の上を指差して、もう片手を壮五へと差し出す。
手を伸ばしかけてあれ? と思った。その手を取ってしまったらなんだか戻れないような気がしたのだ。……戻れない? どこへ? 川に落ちるわけでもないだろうし、このあとも環と二人で寮へ帰るのだろう。アイドルの仕事も順調で、IDOLiSH7もMEZZO”も、もちろん壮五個人も活躍の場を広げている。それはたしかに、こんな穏やかな日々へと戻る道が断たれることに繋がるのかもしれない。けれどそれは壮五が望んだことだ。小鳥遊プロダクションの敷居を跨いだあの日から、壮五の腹は決まっている。
それなら僕は一体、何に戻れないことを恐れているんだ?
「そーちゃん?」
壮五の手が途中で動きを止めたことを不思議に思ったのか、環は壮五の名を心配そうに呼ぶ。優しく、労わるような、けれど少しの不安を孕んだ声。
「あ……ううん、なんでもないよ」
心配をかけまいと、やんわりと笑って環の手を握る。もう随分と暗くなってきたため、環が壮五の表情をしっかりと捉えることができたかどうかは壮五の知るところではない。握り返した環の手は、彼の優しさを写し取ったように温かい。
「ふーん……? まぁまたなんかごちゃごちゃ考えてたんだろうけど、これ見て忘れたらいんじゃね」
言われて顔を上げれば、そこには明るい黄緑色の光が舞っていた。四つ……いや六つ程のわずかな数だが、尾を引く光はあまりに幻想的だ。
「わぁ……!」
実を言うと壮五はホタルをこの目で見たことがなかった。写真で見たことはあったし、それを綺麗だとは思っていた。しかし実際に飛んでいる風景を見ると、感嘆の言葉以外を忘れてしまうほど不思議な景色だ。
綺麗なのに、どこか寂しい。
「……そういえば」
ふと思い出したことをぽつりと呟く。
「ホタルが光るのは、仲間に対して『自分はここにいるよ』って伝えるためなんだよね」
「え、そーなん?」
「あれ? 知らなかった?」
「俺が知ってんのは、プロポーズするためってやつ」
「ああそうか。たしかそういうのもあったよね」
たしかにホタルに限らず、生物には一つの行動にいくつかの意味を持つものが多い。人間の言葉だって、他の生物からすれば聞き分けられない「ただの音」かもしれない。
「それがどーかした?」
「あ、うん。それってなんだか、環くんみたいだなあと思って」
「俺みたい?」
「うん」
環はそのまま黙っている。壮五の言葉を待っているらしい。
「環くんは理ちゃんを探すために……見つけてもらうためにアイドルになっただろう? 『俺はここにいるんだぞ』って伝えるために。そうやって輝いている君の姿がホタルとよく似ているなと思ったんだ」
「…………そっか」
たっぷり三秒、いや、もしかしたらもっと長い時間だったかもしれない、環はそれだけの沈黙ののちそれだけをまるで呟くように、あるいは噛みしめるように口にした。しかしその音色は決して嫌悪するような熱も、蔑むような冷たさも持っていない。それが答えだと言わんばかりの温度を秘めていた。
だから少し調子に乗って、キザなセリフを口にしてしまったのかもしれない。
「それに、君がアイドルになってくれたから、僕も君を見つけられたんだよ」
「なんだそれ。そーちゃんもアイドルじゃん」
からかうような音を奏でて、環はからからと笑う。
「ふふっ、それもそうだね」
つられて壮五も笑うが、ふと、再び落ちた静寂がまた心細さを連れてくる。
「……環くんは、寂しかったよね」
たまらなくなって、そんなことを口にした。
「僕らはなにもかも正反対だけど、寂しさを抱えていたことは共通していたと思うんだ」
それは小鳥遊事務所に入る前。環はたった一人の妹が居なくなった施設で、壮五は唯一の理解者だった叔父を失った家で。膝を抱えて寂しさに震えていた。
「きっと一人じゃどこか足りない僕らは、二人だからここまで飛んでこられた。だから、その……なんというか…………これからもずっと、僕の隣にいてほしい、な……?」
そこまで少し熱っぽく語っておいてなんだが、自分が何を言いたかったのか分からなくなってしまった。結果、謎の告白のような言葉を発してしまう。
「……ぷっ、ははっ!なにそれ、告白みてー」
思ってていたこととまったく同じことを言われ、恥ずかしさで顔に血液が集まってくるのを感じる。
「し、仕方ないだろう!? 途中から、何が言いたかったのか分からなくなってしまって……というか笑いすぎじゃないか?」
腹を抱えて、ヒーヒー言いながら笑う環に、壮五は失礼だと非難の視線を向ける。
と、視線が交差する。
「あ……」
気付いたのだ。その瞳の奥に、わずかに揺れる熱に。
「ていうか、そーちゃんさっきからそんなばっか言ってんな。アイドルになったから見つけれたとか、ずっと一緒にいてとか」
しかしそれはすぐに引っ込んで、いつもの優しいタレ気味の目に戻る。水色のビー玉の向こう側には、もう何も見えない。
「そ、それは……」
「俺がそーちゃんのこと一人にするわけねーじゃん。ばーか」
言い訳を口の中で捏ねようとして、環の声に遮られる。それは温かい色を帯びている。
「へ……?」
「ばかじゃん。そーちゃんはばか。頭いーのに、変なとこばか。でも、仕方ねーから俺が一緒にいてやんよ。そーちゃんがまた一人で泣いてんのとかやだから」
ばかって三回も言ったな、などと心の中でカウントをしていたら、痛いところを突いてきた。それでも一緒に降ってきた優しさの雨がその棘を溶かしていくから、不思議と痛みは感じない。
「そんなにばかって言わなくてもいいだろう……」
結局、それだけのわずかな抗議に留め、でも、と続ける。
「ありがとう」
「ん」
環は短い返答だけして、壮五の頭にその大きな手を載せ、すぐに下ろす。
「……帰ろっか」
環の言葉に壮五もうなずく。
先に植え込みから出てほれ、と差し出された環の手に、今度は躊躇いなく自身の手を伸ばす。
どこへ行こうと、どこから戻れなくとも、この手があればきっともう寂しくはないだろう。壮五の胸には、根拠はないがそんな確信があった。
握った環の手は夜風に触れて少し冷たくなっていた。
「少し冷えちゃったね」
「早く帰って風呂入ろーぜ」
「そうだね」
他愛もない会話をしながら駅へ向かう。
三年ののち、同じ場所で同じようにホタルを見ながら環から告白されることになるとは露ほども思わずに。