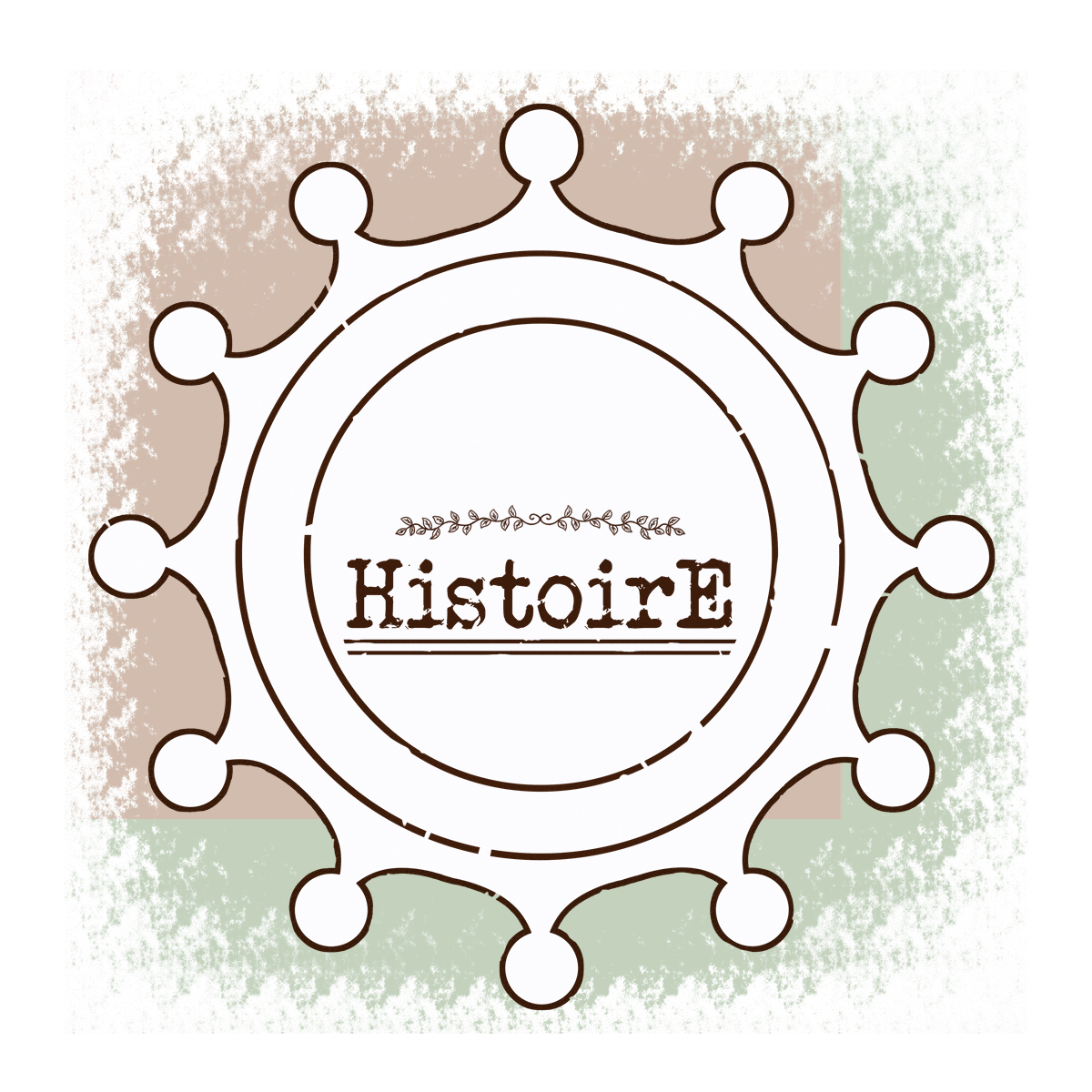新曲のデモを聴いた時、新しい曲調だなと思った。今までのIDOLiSH7のどこにもない。熱狂的で、色っぽくて、エキゾチックな曲。
歌詞を読んだ時、引っかかった箇所があった。痛みと言うほどでもないが、飛び出した釘やささくれ立った木材に洋服の裾が引っかかったような感覚。
『つまらない自分バイバイ』
昔、環に言われたことがあった。
つまんねーやつ──
だから無意識のうちに自分を重ね合わせていた。
心のどこかで自分が歌うと信じて疑わなかった。
だが実際にその部分を歌うことになったのは陸だ。
当然だ。陸はIDOLiSH7のセンターなのだから。ワンコーラス目の最後を歌うべきは彼を置いて他にない。
それなのに、分かっているのに……そのことにひどく失望した自分がいた。
なぜ自分ではない。
家を出て。歌って踊って。アイドルとして活動して。ドラマに出て演技をして。バラエティに出てコメントを述べて。
環が『つまんねー』と吐き捨てた自分はここにはいない。きっと。そんなつまらない部分も含めて逢坂壮五なのだから完全に切り捨てていくことはできないだろう。それでも自分が大嫌いで仕方がなかった自分はもういないはずだった。
もう、バイバイしたのだ。
それなのに──
コンコンッ
レッスンが終わり、夕食も終わり、自室に籠って歌詞カードを穴が空くほど睨みつけていると部屋の扉をノックする音が聞こえた。
「ソウ、ちょっといいか?」
聞き慣れたアルトが独特の名で壮五を呼ぶ。
訪ねてきたのは大和のようだ。
「どうぞ」
傍に歌詞カードを置き、扉の方へ顔を上げる。なるたけ怖い顔をしないようにと眉間と頬を動かす。
「……」
しかし大和は部屋へ入ってくるも、そのまま何も言わず壮五の顔を眺めるだけだ。
「……あの、大和さ」
「大丈夫か?」
「え?」
斜め上から降ってきた言葉は予想もしなかった心配のそれだった。
「今日レッスンの時、様子がおかしかっただろ? いつもならクールダウンのストレッチをするはずのおまえさんが今日はしてなかった。ほかにも、いつもならソウが気付いてフォローしてくれてるところにもミスが目立ってた。ま、それに関してはあいつらが自分で気付いてくれりゃ問題ねーんだけどな」
最後に少しだけ茶化すように歯を見せて笑う。その顔を見て、あ……と気付く。
「……そんなに、怖い顔をしていましたか?」
おずおずと訊ねると、おぉと大和は大きく頷いた。
「これから魔神でも倒しに行くのかってくらいは険しい顔してたな」
その言葉を聞いた瞬間、情けなさで死にたくなる。
何がつまらない自分にバイバイしただ。今もこんなにつまらないことで心配をかけている。子どもじみたことを気にしている。
僕はまだこんなにもつまらないじゃないか。
「隣、ちょっといいか?」
大和の言葉に、隣に置いていた歌詞カードを退けようと手に取る。
しかし大和は歌詞カードを持った壮五の手首を掴む。驚いて大和の顔を見上げると、何故か彼は眉を歪ませている。今にも泣き出しそうだ。
「……なぁソウ。お兄さん、真面目な話すんのは苦手なんだけど、ちょっとだけ話聞いてくれるか?」
黙って頷くと、大和はありがと、と蚊の鳴くような声で呟く。掴まれた手首が少しだけ痛い。大和は壮五の手からカードを取り、自身の視線の高さまで持ち上げる。
「『つまらない自分バイバイ』」
吐き出すように、あるいは噛みしめるようにか、呟くようにか。口を開いて八分休符ののちに大和はその歌詞を声に出した。
「ソウさ、この歌詞見た時どう思った?」
「どう、って……」
「俺は「これ、俺が歌うのかな」って思ったよ」
「っ……!?」
思いもよらぬ告白に壮五は言葉に詰まる。大和は自嘲めいた笑みを浮かべ、続ける。
「つまんねぇ理由でアイドルになって、つまんねぇ理由でミツと喧嘩して、つまんねぇ理由でおまえらに迷惑かけた」
「つまらなくなんて──!」
「つまんねぇよ。ただの親子喧嘩だ。……いや、喧嘩ですらなかったかもな。俺が勝手に拗ねて、不貞腐れて、復讐だなんだって息巻いてただけだ。独りよがりの、つまんねぇ理由」
「ッ!!」
そんなふうに言ってほしくなかった。だって大和も壮五と同じように、父という人と戦うためにここへやってきたのだから。それがつまらない理由だったなんて言わせるものか。ほかの誰が許そうと、壮五だけはそんなこと、絶対に許さない。
「そんなつまんねぇ俺が、おまえさんたちと一緒に歌って踊って、ドラマや映画なんかで演技をして。ここで生きてく理由を見つけた」
え……?
「つまらない自分に、バイバイ……とまでは行かずとも多少はまぁ、マシになったんじゃねぇかと思った。だからここ、俺に歌わせてくれんじゃないかって、ちょっとだけ期待してたんだ。っま、現実はやっぱ、センターだからリクだけどなぁ」
そこまで話して、大和はようやく壮五の隣へ腰かける。歌詞カードをこちらへ差し出し、そこへ落とした視線を上げながら優しい音色を奏でた。
「ソウは、つまんなくないよ」
菫色の瞳が貫かれる。
その言葉だけで充分だった。